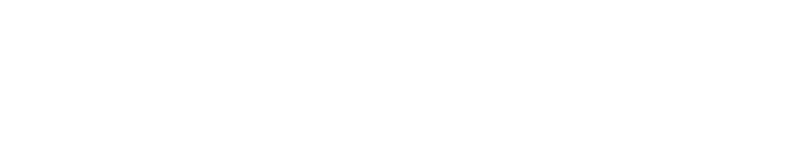ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第二十二回となる今回のインタビューでは、ご自身のDJとしての経験を武器に、音楽と交流が渦巻くナイトクラブというフィールドへ分け入り、そこに集う人々の生の声をすくい取る、研究者の下川詩乃さんにお話を伺います。
遊び場がフィールドに変わる時
——社会心理学から社会学へ。その二つの学問は、どのような点が違うのでしょうか。
一言で言うのは難しいですが、大きな違いは方法論かもしれません。社会心理学は、統計などの量的データを用いて、科学的な厳密さを非常に重視します。研究の進め方や論文の書き方もある程度体系化されている。一方で社会学は、インタビューや参与観察といった質的なデータも多く扱い、テーマ選びから方法論まで、研究者の自由度が非常に高い学問です。
——なるほど。そうした方法論の違いから、二つの学問の間で緊張関係が生まれるようなこともあるのでしょうか。
そうですね。社会心理学は科学であろうとする姿勢が強いので、社会学の方法論に対して批判的な見方が生まれることはあります。ただ、私自身が量的研究の中で感じたのは、そうした「科学か、そうでないか」という二元論的な議論とは少し違う、もっと個人的な違和感でした。データと向き合う中で、「この『3.5』という数字は、本当に『人』を表しているのだろうか」という問いが、どうしても頭から離れなくなってしまって。人の生の声をちゃんと聞きたい。そう思った時に、それを受け止めてくれる器が、私にとっては社会学だったんです。
——そして、ご自身の研究テーマとして「ナイトクラブ」を選ばれた。
社会学で研究するなら、絶対に「私だからできる研究」がしたいと思っていました。社会心理学の研究では、誰がやっても同じ結果が得られる「再現性」が非常に重視されます。それは学問としてとても重要なことだと理解しつつも、私個人の性分として、「この研究は、私でなくてもできるのではないか」という思いがどうしても拭えなかったんです。その点、ナイトクラブは、私自身が大学時代にDJサークルに所属していて、馴染みのあるフィールドでした。
——ご自身の経験が、研究のフィールドに繋がったのですね。
はい。当事者としての経験があるからこそ、見えてくるものがあるはずだと。特に、私が調査対象にしているようなアンダーグラウンドなクラブは、そもそも情報が少なく、コミュニティに入り込むこと自体が難しい。その点、私にはアドバンテージがありました。
——かつて遊び場だった場所が、研究の対象になったことで、見え方は変わりましたか?
大きく変わりましたね。一つは、これまで自分が敬遠してきた、いわゆるチャラ箱に対する見方です。以前は好きになれませんでしたが、研究のために通ってみると、そこにはそこの楽しさや人間関係のあり方がちゃんと存在していることに気づきました。今ではチャラ箱も良い場所だなと思いますし、それを一方的に軽蔑している人を見ると「そんなに単純な話じゃないよ」と思えるようになりました。
——ご自身の過去の経験とも、向き合い直すきっかけになった。
ええ。実は大学時代、サークルの中で自分の好きな音楽ジャンルが少し変わっていて、仲間外れにされているような疎外感を感じていた時期がありました。今回、研究者として改めてクラブという場所に戻ることで、当時は感情的に傷ついていた出来事も、より俯瞰して捉えられるようになりました。薬物の問題など、目を背けたくなるような現実も含めて、そのすべてがクラブという文化を構成しているんだと、冷静に受け止められるようになったんです。
——好き嫌いとは別の、新しい物差しを手に入れたような感覚でしょうか。
まさにそれです! 良い言語化ですね。遊び場だった場所が研究対象になり、寛容になれたというか、自分の中の物差しが増えた感覚です。
——最後に、今後の夢や野望についてお聞かせください。
実は、これまでのクラブ研究は、文化としての音箱ばかりが対象で、チャラ箱は学問的にほとんど無視されてきたんです。でも、都市の現実として両者は間違いなく存在している。だから私は、その両方をきちんと記述して、これまでのクラブ研究をアップデートするような、リアルなナイトクラブ研究を切り拓いていきたい。それが今の最大の目標です。
——研究者としての活動と、ご自身の音楽活動も両立されていますね。
はい。DTMもDJも続けていますし、どちらも私にとってはすごく大切なものです。研究だけに没頭するのではなく、音楽活動も頑張って、自分の機嫌を自分で取れるような、バランスの取れた研究者でいたいと思っています。そして、学会に行ってきた様子などをSNSで発信することで、「大学院って面白そうだな」「学問って楽しそうだな」と思ってくれる人が一人でも増えたら、これ以上嬉しいことはありません。