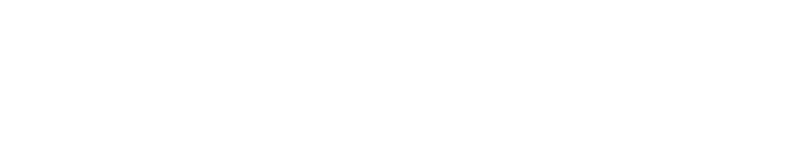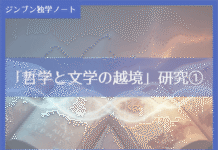ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三十九回となる今回のインタビューでは、オペラとマンガを横断する「アダプテーション(翻案)」の可能性を追究されている、笠原真理子さんにお話を伺います。
理想と現実の狭間、そして舞台の裏方へ
——ここでようやく、オペラ研究への道が定まったわけですね。
はい。文化資源学研究室には、演劇や音楽学の素晴らしい先生方がいらっしゃいましたし、何より「オペラを文化的な資源としてどう活かすか」「どう人々に届けるか」という視点で研究ができる環境でした。
私が特に惹かれたのは、「オペラにおけるアダプテーション」です。たとえば、原作小説がオペラになるとき、あるいはオペラが漫画になるとき、そこには必ず「作り手の葛藤」があります。
——葛藤、ですか?
ええ。私たちはオペラを作曲した大巨匠たちを「神がかった天才」だと思いがちですが、実際は彼らも「興行として成功させなければならない」「大衆に受け入れられなければならない」というプレッシャーの中で生きていました。
私が研究対象としてきた作曲家ジュール・マスネ[1]ジュール・マスネ(1842-1912):フランスの作曲家、〈タイスの瞑想曲〉などで知られる。もそうです。彼は常に「どうすれば大衆に受けるか」「どうすれば批評家に叩かれないか」という板挟みの中で、自分のオリジナリティをどう出すかに苦悩していました。いわば、現代の商業クリエイターと同じ悩みを抱えていたんです。
——なんだか親近感が湧く視点ですね。「高尚な芸術家」ではなく、「悩める職業人」としての作曲家像が見えてきます。
そうなんです。学生や一般の方にその話をすると、皆さんすごく驚かれます。オペラというと、どうしても「優雅な人々が楽しむ、浮世離れした世界」と思われがちですが、作っている人たちは泥臭い努力を重ねていた。原作をどうアレンジすれば観客に喜ばれるか、あるいは検閲を通せるか、そういった「大人の事情」と「芸術的野心」のせめぎ合いが、作品のあちこちに痕跡として残っています。それを読み解くのが、たまらなく面白いんです。
——なるほど。笠原さんが漫画や現場での体験を通して感じてきた「物語の面白さ」や「裏方の視点」が、そのまま研究の独自性につながっているのですね。
そう言っていただけると嬉しいです。博士論文まではマスネを中心とした原作からオペラへの翻案を研究していましたが、今は一周回って、私の原点である「漫画」と「オペラ」の関係に注目しています。
——具体的にはどのような研究を?
「オペラの漫画化」ですね。たとえば、松本零士先生[2](1938-2013)漫画家。『銀河鉄道999』などが有名。がワーグナーの『ニーベルングの指輪』を漫画化されていますが、あれは宇宙を舞台にしたSF的な設定になっています。これはある意味、松本先生による「新演出」なんですよね。
また、オペラは音楽が主体の芸術ですが、漫画には音がありません。その「聞こえない音楽」を、漫画家さんたちがどう表現しているか。コマ割りや描き文字でリズムを作ったり、あるいは歌詞をあえてセリフとして処理したり。作家によってアプローチが全く違うんです。
——「音のないメディアで音楽を表現する」というのは、究極のアダプテーションですね。
はい。そこにこそ、日本独自のオペラ受容の面白さがあると思っています。日本人は、ヨーロッパの人々とは違う文脈でオペラを受け入れ、独自の形で楽しんできました。私はその「日本的な楽しみ方」を肯定したいですし、もっと広めていきたいんです。
今、オペラの観客層は高齢化が進んでいて、若い人がなかなか劇場に足を運んでくれません。でも、かつての私がそうだったように、漫画やアニメといった身近なメディアが入り口になれば、オペラの世界はもっと広がるはずです。
——笠原さんの研究そのものが、オペラという敷居の高い芸術を現代に開くための「アダプテーション」のように感じます。
ありがとうございます。私自身、「考古学者になって秘宝を掘り出す」という夢は叶いませんでしたが(笑)、オペラという広大な遺跡の中から、まだ知られていない魅力を掘り起こして、皆さんに「これ、面白いですよ」と手渡す仕事ができているなら、それはそれで幸せなことだなと思っています。
これからは、中高生のような若い世代に「オペラって意外と人間臭くて面白いね」と思ってもらえるような、そんなきっかけを作っていきたいですね。
——漫画好きの少女が時を経て、今度は新しい世代にその扉を開こうとしている。とても素敵な循環だと思います。本日は貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。