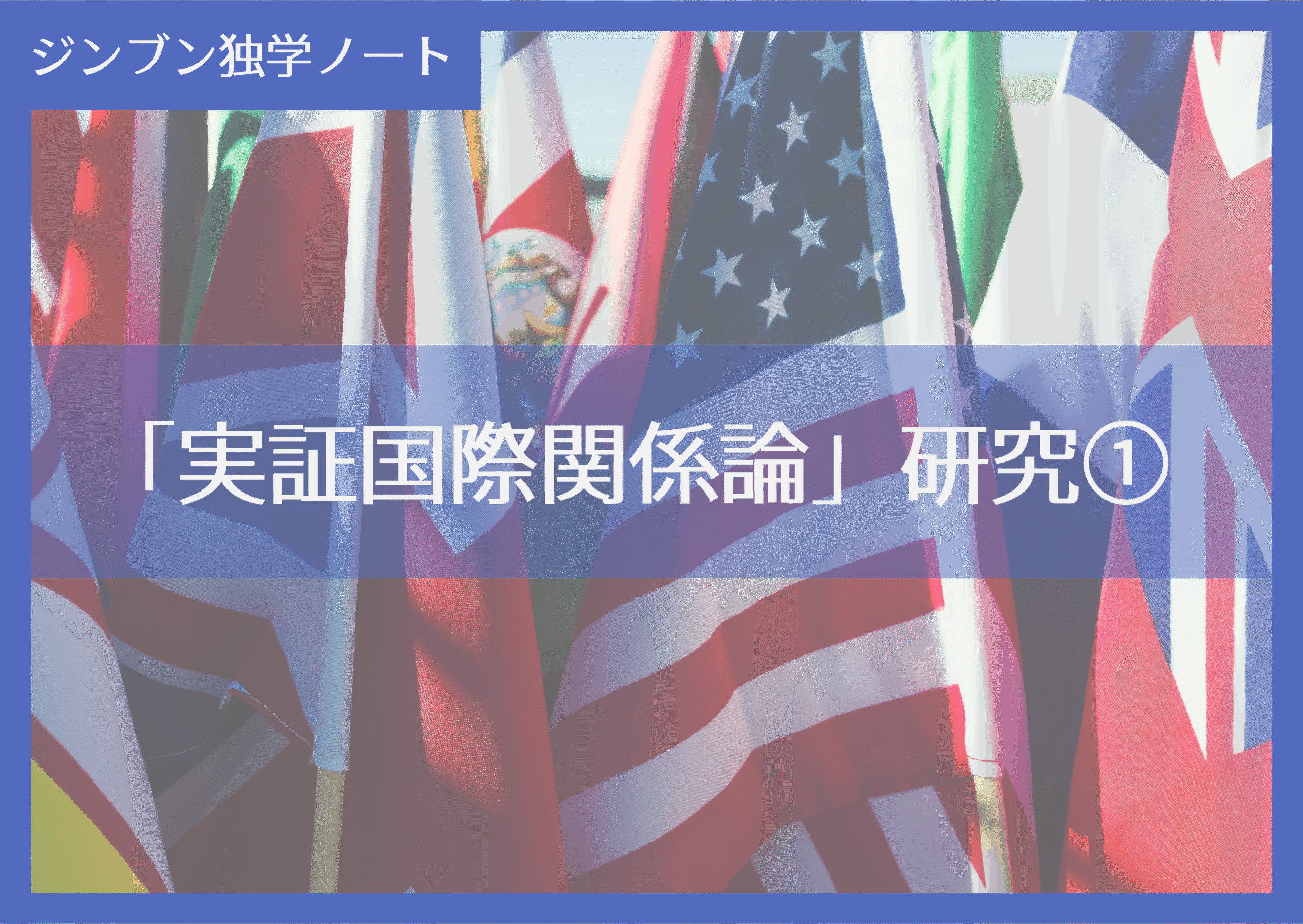——その客観性へのこだわりは、どこから来ているのでしょうか。少し遡って、洲脇さんの学生時代のお話を伺えますか。
国際関係に興味を持つ直接のきっかけになったのは、2010年の出来事です。当時、私はまだ中学1年生でしたが、ニュースで「中国のGDPが日本を抜いて世界第2位になった」と大きく報じられていたのを今でも鮮明に覚えています。
——2010年というと、中学1年生。その頃に、すでに国家間の関係性に関心があったのですね。
当時は「【中国脅威論】」といった言葉も盛んに使われ、これまで世界第2位の座を守ってきた日本が、その地位を明け渡したという事実に、子どもながらに大きな衝撃を受けました。そこから、「台頭する中国と、日本は、そして世界はどう向き合っていくべきなのか」という問いが自分の中に生まれ、自然と世界史が好きになりました。その関心は高校時代も一貫していて、大学選びもその延長線上にありました。
——それで、大学ではアジア地域を専門的に学べる学部を選ばれたのですね。
はい。同志社大学の【グローバル地域文化学部】に進学しました。高校生の頃から漠然と、「19世紀はヨーロッパの時代、20世紀はアメリカの時代、そして自分が生きる21世紀はアジアの時代になる」と考えていました。これから最もダイナミックに動くであろうアジアという地域に絞って研究したい、という思いが強くあったのです。その学部に「アジア太平洋コース」という専門課程があったことが、進学の決め手になりました。
——高校生の段階で、そこまで明確な問題意識と将来像を描けていたというのは慧眼ですね。
いえいえ、そんな大したものではありません。ただ、当時から興味の対象が一貫していたのは確かです。しかし、実際に入学してみると、少し期待とのずれもありました。学部名に「文化」とある通り、講義内容は文化研究に寄ったものが多く、私がより強く関心を抱いていた国際政治学のようなテーマに深く触れる機会は、想定していたよりは少なかったのです。「もしかしたら、法学部の政治学科などに行った方が良かったのかもしれない」と感じたこともありました。
——大学生活そのものはいかがでしたか。
授業に出て、サークル活動をして、アルバイトをする。そんな日々を1年ほど繰り返した頃、ふと、ある種の虚無感に襲われました。私は大学名で進学先を選んだわけではなく、学びたいことがあってこの学部を選んだはずなのに、このままでいいのだろうか、と。周りの学生との温度差も感じていて、もっと勉強に打ち込める環境に身を置きたい、という気持ちが日に日に強くなっていきました。ちょうどその時、大学の派遣留学プログラムの存在を知ったんです。「これだ」と思い、そこから猛烈に中国語の勉強を始めました。
——その情熱が、中国への留学につながるのですね。
はい。大学3年生の秋から4年生の夏までの1年間、北京に留学しました。とにかく必死でしたね。私は大学から第二外国語として中国語を学び始めたので、現地の学生や他の留学生に比べて圧倒的にビハインドがありました。朝起きて授業に出席し、それが終わると深夜まで自習室にこもって勉強する。そんな毎日でした。特に、古典漢文を現代中国語に訳す授業は、現代中国語もおぼつかない身には本当に骨が折れる作業で、辞書を片時も手放せませんでした。
——想像を絶するような生活ですね。なぜそこまで打ち込めたのでしょう。
これは理由をうまく説明できないのですが、私の中に「純粋でありたい」という、ある種の哲学のようなものがあるんです。好きな学問に対しては、ただひたすらに、没頭したい。余計なことを考えず、その対象と真摯に向き合いたい。その思いが、当時の私を突き動かしていたのだと思います。勉強にのめり込みすぎて、蕁麻疹が出たこともありました。
——その経験が、研究者の道を志すきっかけになった。
そうですね。留学中は学業に専念していたので、日本の学生がするような就職活動は一切していませんでした。帰国が近づくにつれ、留年するか、大学院に進学するかという選択を迫られましたが、迷いはありませんでした。せっかく身につけた語学力や、中国の歴史や文化に関する知識を、もっと深めたい。そう考えて、大学院への進学を決意しました。最終的には、台湾の【国立台湾大学】の修士課程に進むことになります。
次回は研究者への道について伺います。