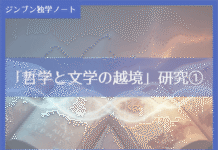ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第六回は東アジア考古学研究の折茂克哉助教授です。折茂先生は東京大学の駒場博物館にて、ご自身の考古学の研究を行いながら、展覧会の準備などの博物館業務にも携わっていらっしゃいます。
研究の方法
Q1-1. 本日はよろしくお願いいたします。まずは簡単にこれまでの経歴を教えてください。
よろしくお願いします。まず大学では考古学専攻に入りました。そのときは学者になるつもりで、「旧石器時代」を専攻しようと思っていましたが、大学卒業時は考古学を続けていくかは分からず、結局1年ふらふらしていました。
その後違う大学の大学院に入学し、第二外国語がロシア語というのもあり、「日本の旧石器時代からシベリアを中心とした中期旧石器時代」を研究対象とし、ユーラシア大陸をフィールドに、中期旧石器時代における制作技術や現生人類が東アジアでどう展開していったのかを研究していました。
ロシアに留学した際には『マンモスハンター』等の著述で有名な加藤晋平先生に師事しました。大学院時代は、サンクトペテルブルクで研修生をしたり、発掘調査に同行したりと、様々な経験を積み、2002年に博士論文を提出しました。
-1024x680.jpg)