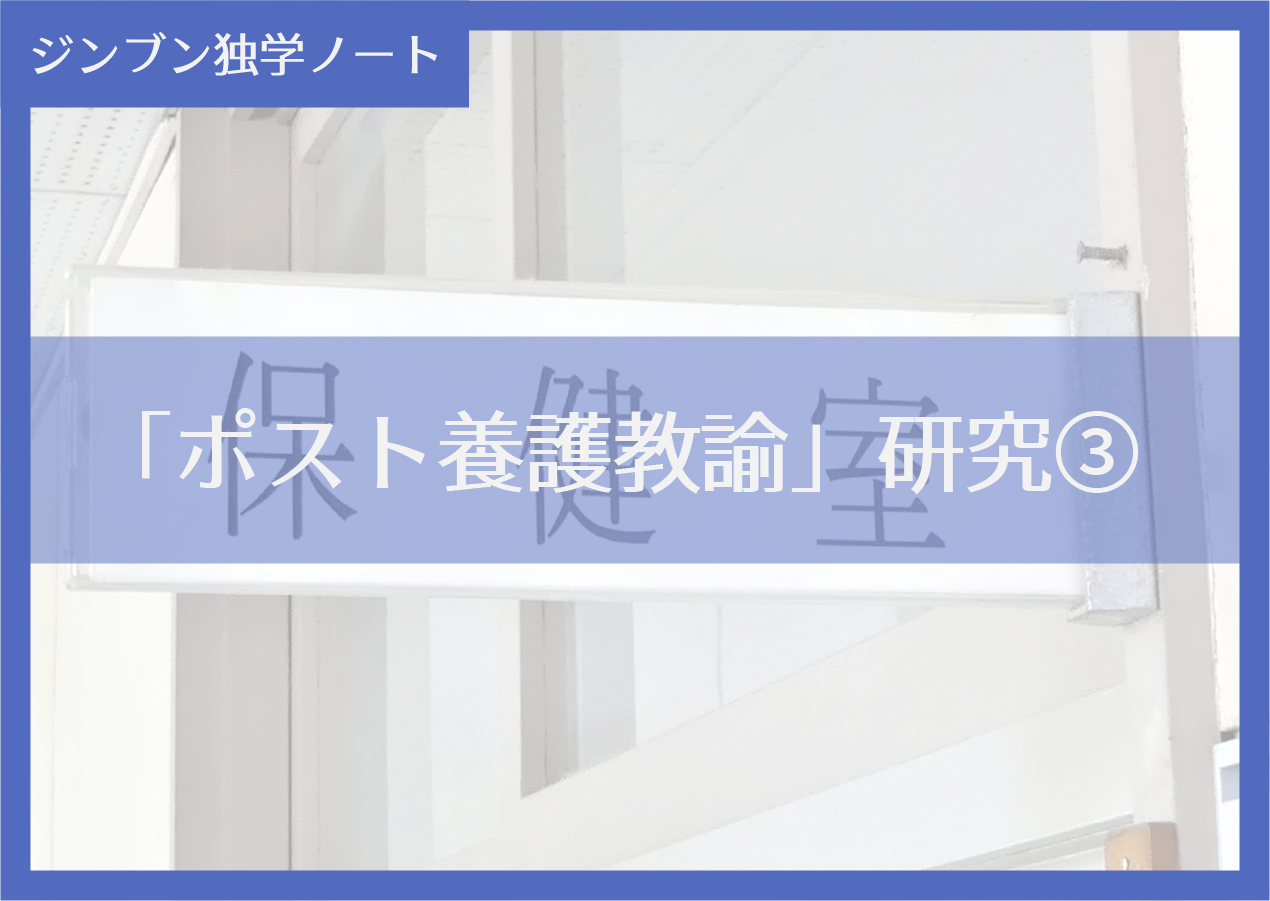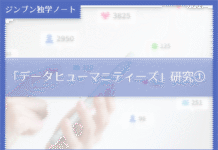ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第二十六回となる今回のインタビューでは、看護と教育、臨床と研究という複数の領域を越境した独自の視点から、学校が抱える構造的な問題に迫る、教育学研究者の柏木睦月さんにお話を伺います。
「任せる」ことで始まる信頼のバトン
——不思議な縁が繋がったのですね。研究分野は、どのように決められたのですか?
実は、大学院の試験には一度落ちているんです。最初の年は、養護教諭の仕事を「ケア」という概念から捉え直したいと思い、教育哲学を専攻しようと考えていました。アメリカの教育哲学者ネル・ノディングズが提唱した「ケアリング」の概念を知り、日本独自の職種である養護教諭の存在を、哲学的に考えられないかと思ったんです。
でも、結果は不合格。上京の準備も進めていたので途方に暮れていたのですが、またしてもご縁が繋がりました。不合格の10日後くらいにあった研究会で、池田先生と、後に私の指導教員となる小国喜弘先生が話す機会があったそうで、小国先生が「研究生として来てみてはどうか」と声をかけてくださったんです。
——なんと……!
もう、その話に乗るしかありません。でも、小国先生の専門は日本教育史。その瞬間から、私は日本教育史の人間になる覚悟を決めました。
振り返れば、それで良かったと思っています。養護教諭という職は、学問としての歴史がまだ浅く、研究者も非常に少ない。その中でも特に養護教諭の歴史を専門にする研究者は本当に少ない。中途半端に概念整理をするよりも、まずは歴史研究を通して、誰にも揺るがすことのできない事実を積み重ねる必要がありました。感情や経験論で「養護教諭は大事なのよ」と語るベテランたちに、論理的に納得してもらうためには、哲学的な思索よりも、歴史史料という動かぬ「証拠」を固めていくことが、私には必要だったんです。
——現場での問いを携えて大学院へ進まれたわけですが、あえて養護教諭養成の専門コースがある大学院ではなく、東大の教育学研究科という、いわば「アウェイ」な環境を選ばれたのはなぜだったのでしょうか。
はい、それには明確な理由が二つありました。一つは、自分の問いを守るためです。
養護教諭を養成するコースは、どうしても「養護教諭は素晴らしい仕事だ、学校に必要不可欠な存在だ」という前提から出発することが多いです。そこで私が「そもそも、養護教諭は学校に必要か?この仕事のあり方は本当に正しいのか?」なんて問いを投げかけたら、きっとアンチだと思われるだろうな、と。自分の純粋な問いが、その場の空気に飲まれて歪められてしまうのが嫌でした。
もう一つは、養護教諭の研究が、あまりに養護教諭の世界だけで完結しすぎていたからです。教育学の一分野であるはずなのに、教育学全体の中では周縁に置かれ、他の分野からまともに論じられることも、批判されることもほとんどなかった。いじめや不登校といった問題が深刻化する中で、その受け皿を養護教諭が引き受けてしまったがゆえに、学校というシステム全体が変わらないまま存続できてしまったのではないか。その構造を解明するには、閉じた世界から出て、教育学というより大きな視座から光を当てる必要があったんです。
——なるほど。実際にその環境に飛び込んでみて、いかがでしたか。
もちろん、大学院のゼミで養護教諭の存在を知っている人なんてほとんどいません。いたとしても、「保健室にいる優しい先生」くらいのイメージです。ですから、ゼミのたびに、私の問いの背景や、養護教諭がいかに教育学の議論から抜け落ちているかを説明し続けなければなりませんでした。それは大変な作業でしたが、その「揉まれる」環境こそが、私には必要だったと思っています。
——そこで、また新たな出会いが生まれるのですね。
博士課程で同期だった堀越さんとの出会いは、私の人生を変えたと言っても過言ではありません。歴史研究の奥深さを知れば知るほど、私は歴史の人間としてやっていこうと覚悟を決めていました。そんな時、彼が「子どものための哲学(P4C)」の実践について、養護教諭の研究をしている私に助言を求めてきたんです。
私はいつものように「私はアンチ養護教諭なので、あなたの研究を損ねるかもしれないですよ」と返したのですが、彼は「何それ、面白いですね」と(笑)。そのやりとりが始まりでした。
彼と話すうちに、思ったんです。私がやりたいことの「哲学的な側面」は、専門家である彼に「任せよう」と。
——「任せる」、ですか。
はい。私が片手間に哲学を研究したところで、ずっと哲学の世界にいる彼に敵うわけがありません。それは単なる分業ではなく、彼の専門性に対するリスペクトです。そして、任せるからには、お互いの価値観や研究への熱量を深く共有する必要がある。彼と二人で書いた論文があるのですが、どこからが私が書いて、どこからが彼が書いたか、たぶん読んでも分からないと思います。それくらい、分かちがたく一緒に作れた感覚があるんです。
——それはすごいですね。ご自身の研究と哲学が、そこで深く結びついた。
ええ。哲学対話の研究者でもあり実践者である土屋陽介先生が「哲学対話の空間は、保健室に似ている」と書かれているのですが、この言葉は私の中にずっとあります。保健室が、学校の中の「逃げ場所」や「隠れ家」として機能している。でも、そもそもそんな特別な場所(アジール)がないと成り立たない学校というシステム自体がおかしいのではないか。
それと同じで、わざわざ「哲学対話」という特別な時間を設けないと本質的な対話ができない日常もまた、豊かとは言えません。保健室がなくても子どもたちが安心して過ごせる学校、哲学対話という看板がなくても人々が対話できる社会。その二つの理想は、私の中で深く繋がっています。
——最後に、「誰かに任せる」という言葉が非常に印象的でした。
研究って、全部自分でやらなくてもいいんですよね。誰かに任せるというのは、その人へのリスペクトであり、未来への「信頼」の表れなのだと思います。過去の実績を元にする「信用」とは違います。
そもそも、誰かを信頼できない時って、相手に問題があるんじゃなくて、「その人を信頼できない自分」を信頼できていないだけだと思うんです。
私がここまで来られたのも、恩師たちが「お前ならできるだろう」と、ある意味で私を信頼し、道を繋いでくれたからかもしれません。その信頼のバトンを、私もまた誰かに渡していく。研究者として、そして一人の人間として、そうありたいと思っています。