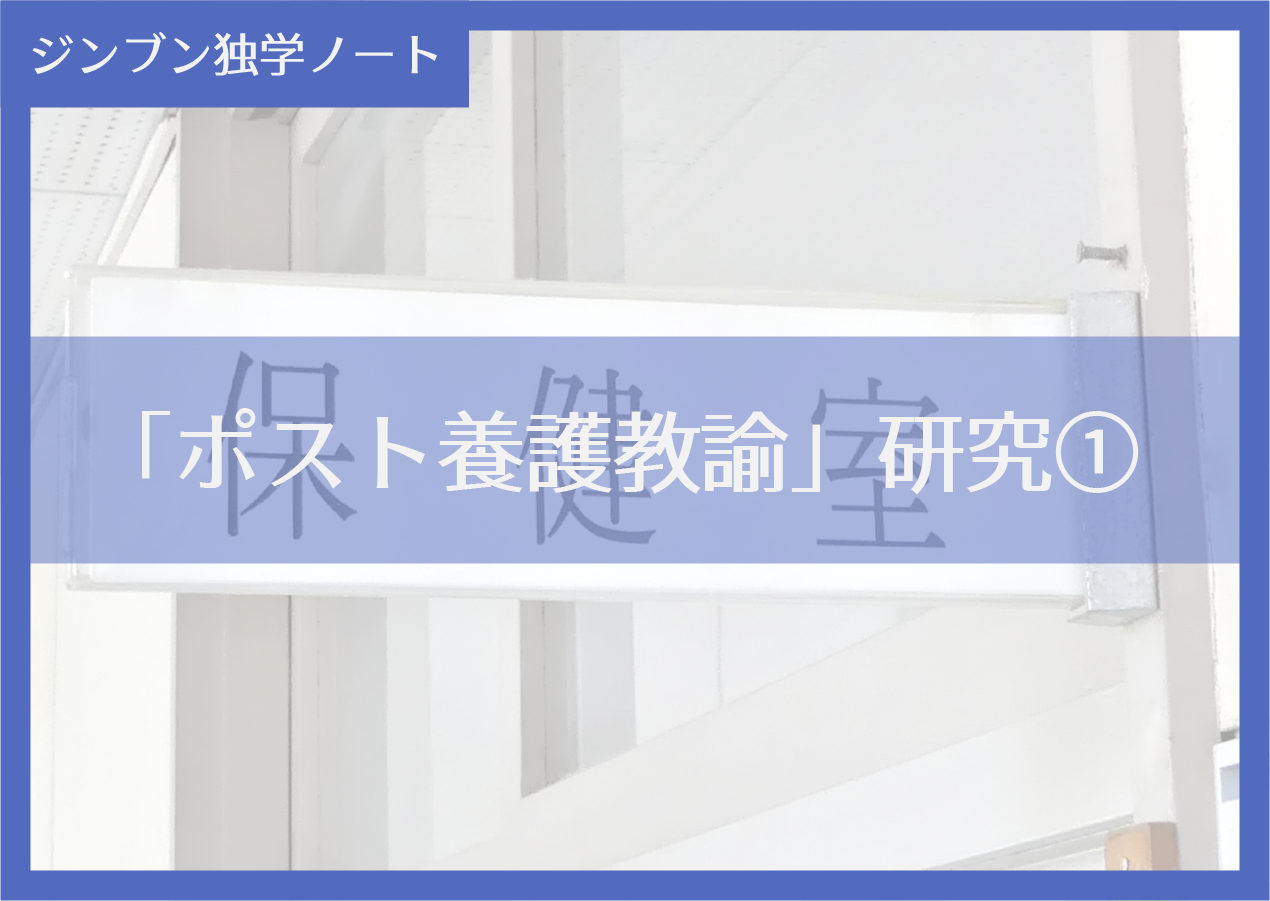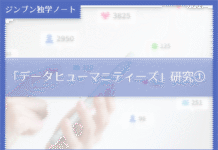ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第二十六回となる今回のインタビューでは、看護と教育、臨床と研究という複数の領域を越境した独自の視点から、学校が抱える構造的な問題に迫る、教育学研究者の柏木睦月さんにお話を伺います。
私の居場所は、ここじゃない
——本日はどうぞよろしくお願いします。
お声がけいただいたものの、ご無沙汰しすぎていて「本当に私で合っているのかな?」とメールを何度も読み返してしまいました(笑)。
——(笑)。もちろんです。今回は、柏木さんがどのような道のりを経て、現在の研究や実践に至ったのか、そのあゆみをじっくりとうかがえればと思います。まず、いつも皆さんにうかがっているのですが、「柏木さんは何の人ですか?」と聞かれたら、普段どのように答えていますか?
ええ、やばいですね。何の研究してるんやろう……。いつも考えていることで言うと、「養護教諭や保健室がなくてもいい『学校』ってどんな学校かな」って、ずっと思っています。
——いきなり核心に触れるような、非常に興味深いお答えです。その問題意識に至るまでには、どのような経験があったのでしょうか。幼少期のお話からお聞かせいただけますか。
幼少期で言うと、養護教諭を目指す上では王道かもしれません。私は体が弱くて入退院を繰り返していたんです。手術もたくさんしましたし、当時は「死にそうな病気」だったらしくて。病院で過ごす時間が長かったので、自然と医療従事者に憧れるようになりました。
それに加えて、少し教育方針の変わった親の影響もありました。「将来、どんなことがあっても自分の力で生きていけるように」と、「手に職をつけること」と「良い大学へ行くこと」を、子どもの頃から強く勧められていたんです。
——なるほど、ご自身の思いとは別に、親からの期待もあったのですね。
はい。まあ、私自身ももともと医療に従事する人間になりたかったので、親が強く願っていた「手に職をつける」という方向性と、私の希望が良くも悪くも合致してしまった。それで、医療看護系の学部を目指すことになったんです。
——なるほど、二つの思いが重なって、看護の道へ進まれたのですね。
でも、いざ看護学部に入ってみると、少し思っていたのとは違いました。一番面白かったのが、養護教諭の一種免許を取るために追加で履修した教育学の授業でした。当時、兵庫県立大学にいらっしゃった柏木敦先生(現在は立教大学教授)の授業が、本当にとんでもなく面白くて。他の学生は「厳しい」って言っていましたけど、私はこの先生の授業がきっかけで、本格的に教職課程を履修しようと決めました。うちの大学では100人中5人くらいしか取らない、かなりマイナーな選択でしたけどね。
——学問との面白い出会いが、一つの転機になったのですね。
そうですね。ただ、その一方で、病院実習が始まると、色々と葛藤を抱くようになりました。大学で学んでいる看護学の理論と、現場の実践があまりにもかけ離れていることに、どうしても納得できなかったんです。
実習先の看護師さんに「あなたの実践には、どういう理念があるんですか?」なんて真面目に聞くと、「そういうことを聞くな」と叱られてしまう。しまいには、実習担当の教員から「お願いだから、この病棟で穏便に実習を終えたいから黙っていてくれ」とまで言われました。
目の前の患者さんをケアすることが大事なのは分かるけれど、当時の私には「実践の根拠となるはずの理論が実際にはあまり重要視されていないのでは?」というように受け取ってしまいました。「ここは私の働く場所じゃない」という思いが、学年が上がるにつれて強くなっていきました。
——理論と実践の乖離という、非常に根源的な問いにぶつかったのですね。
このまま看護師になっても、自分がダメになると思いました。それなら、もっと自分の判断と責任で、学問と実践を繋げられる立場にいこうと。自分の判断や責任が重ければ重いほど、目の前の実践に対する深みも増すだろうと当時は考えたんです。それで、元々高校時代に医学部進学も視野に入れていたこともあって、「やっぱり医者になりたい」と決めたんですよ。大学4年になると、周囲の高校生には「高校3年生」だと嘘をついて紛れ込み、予備校の夏期講習に通っていましたね。
次回は彼女の転機について伺います。