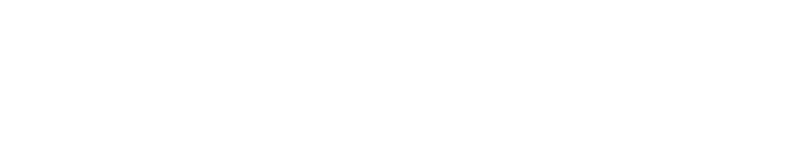ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三十二回となる今回のインタビューでは、国際交流基金での実務経験と中国駐在を経て、日中外交史における文化交流の歴史を新たな視座で読み解く、金子聖仁さんにお話を伺います。
実務の現場で直面した「板挟み」と研究への回帰
——歴史を学びたい学生の多くは、文学部で歴史学を学べる学科・コースを選びますが、金子さんは教養学部の国際関係論コースを選んだのですね。。
はい。世界の中の日本ということにも関心があったので、駒場の国際日本学やアジア研究とも迷いました。結局、国際関係論をメインにしつつ、アジア研究をサブメジャー(副専攻)で取ることにしました。
——そこでもう一つの壁があったそうですね。
語学の壁がありました。国際関係論コースには英語が堪能な学生が多くて。英語が苦手だった私は、ここでも「このままでは勝てない」と(笑)。それで、第二外国語で履修していた中国語を本気で頑張ろう、と。ある種の生存戦略でしたね。
——卒業論文で扱われた「戦間期の対中国文化政策」ですが、これはどのように見つけられたテーマなのでしょうか。
まず、就職先として意識していた国際交流基金のルーツを調べてみたんです。すると、戦前の国際文化振興会(KBS)という団体に行き着きました。国際交流基金の前身の一つにあたる組織です。さらに先行研究をたどると、そのKBSの源流の一つに、義和団事件の賠償金を使った「対支文化事業」(対中国文化事業)があると知りました。戦前の日本の文化事業において中国が占める比重は非常に大きかったので、その源流であり中心であったこのテーマは、自分の関心とも合致しました。
——当時、すでに国際交流基金への就職が決まっていたそうですが、卒論執筆のモチベーションはどんなものでしたか。
大学院に進む気持ちは当時あまりなかったので、これから自分が飛び込む国際文化交流という仕事の「歴史」、特にその「限界」をちゃんと知っておくべきだ、という問題意識が強かったですね。
——その後、国際交流基金で9年間勤務され、うち2年半は中国にも駐在されています。歴史として学んだことと、実務の現場で感じたことの間に、違いはありましたか。
想像はしていましたが、現場で体感する「板挟み」の感覚は、知識として知っている以上に強烈でした。
文化交流は、外交政策として公金を使って行う以上、当然ながら国益や国民への説明責任を考えなければなりません。一方で、文化交流は相手がいて初めて成り立つもので、そこを疎かにすれば単なるプロパガンダになってしまう。自分たちの国益と、現場の相手との信頼関係。この二つの間でしばしば緊張関係が生じます。
——その葛藤の中で、実務から再び研究の道へ、修士課程に進まれています。
中国駐在が大きかったですね。私は日本語教育や日本研究の支援を担当していました。中国各地を訪れ、日中関係を少しでも良くしよう、日本への理解を深めようと日々奮闘されている現地の研究者や、先生方と直接お会いしました。その姿に、純粋に「かっこいいな」と。
——現場の担い手たちの、熱量に直接触れたんですね。
はい。一方で、自分は学部卒のまま「所長輔佐」という立場で彼らと接している。それがどこか申し訳ないというか……。自分も学問的な専門性を磨き、それを寄り所にして日中関係に貢献したいという思いが、駐在中に日に日に強くなっていきました。
そこで、駐在を終えて帰国後、働きながら大学院で学ぶ道を選びました。
職場も、指導教員の先生も、働きながら学ぶということに対して非常にご理解があり、本当に人に恵まれていました。
修士課程では「スーパーバイズド・リーディングス」という、いわば「書評20本ノック」のようなカリキュラムがありまして。
——書評20本……なかなかのボリュームですよね?
そうですよね。1冊あたり4,000字から5,000字のレビュー論文を課されるので、もちろん大変です。でも、キャンパスに通わなくても取り組める課題だったので、社会人には助かる制度でした。
印象に残ったのは、小熊英二先生の『〈日本人〉の境界』(新曜社、1998年)ですかね。800ページ近い大著です。他にも、沈志華先生の『最後の「天朝」』(上下、朱建栄訳;岩波書店、2016年;毛沢東時代の中国と北朝鮮の関係を扱った本)など、分厚いですが、国際関係史・日本外交史を研究する上でお手本になる、非常に面白い文献を読み込みました。このトレーニングは大きかったですね。
最後は実際の研究について伺います。