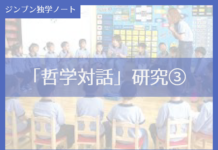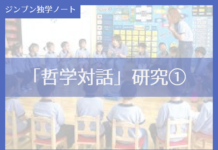──ヘルマン・シュミッツ、検索してみたら、梶谷先生のご著書と、小川侃(ただし)さんという方のご著書がたくさんヒットしました。1991年に京都大学大学院人間・環境学研究科が設置されると同時に、小川先生は教授に就任されています。
そうです。ちょうど私が博士課程に進学した年、小川侃先生のもとに、シュミッツの弟子にあたるギド・ラッペさんという研究者が来ていて、それでシュミッツという哲学者について詳しく知りました。日本では、ほとんどシュミッツを研究している人はいません。小川先生も授業で言及していてオリジナルで面白い思想だと言っていたのですが、その時は魅力がよくわかりませんでした。、ラッペさんがしきりに勧めるので、拒み切れずシュミッツの著書『哲学の体系(System der Philosophie)』の1巻を読み始めてみました。
──梶谷先生のご著書『哲学対話の冒険日記』に、『哲学の体系(System der Philosophie)』のドイツ語原書の背表紙の写真が載っていましたが、1冊がずいぶん分厚い……しかもこの厚さで10冊シリーズ。もちろん原語のドイツ語で読んだんですよね。読んでみてどうでしたか?
最初の100ページくらい読んで「なんだこれ、めちゃくちゃおもしろい!」と衝撃を受けました。目の前が明るく開けて、光が差してくる感じ。「知性は光だ」という言葉をそのまま体験した気がしました。哲学って、「わかる」んだ! これでいいんだ! と。
これまで、哲学とは難解で、「わかる」なんて簡単にはとても言えないものだと思っていました。でもシュミッツの著書を読んで、哲学は「わかっていい」と初めて気づいたんです。
そしてこの『哲学の体系(System der Philosophie)』、日常的なドイツ語が辞書なしですらすら読めないと太刀打ちできない。カントやヘーゲルのような、他のドイツの哲学書は、使っている語彙はそんなに多くないので、辞書さえあればなんとか読めます。でも『哲学の体系(System der Philosophie)』は一日に10~20ページくらいのペースで読み進められる語学力が必要です。10巻合わせると5000ページ以上もあるので、速くたくさん読んでいかないといけません。でも、読んだら読んだだけちゃんとわかるから、それでいいんです。ドイツで大学にもいかず、家でずっと新聞や雑誌を読んでいたおかげです。
──シュミッツとの偶然の出会いと、ドイツで身に着けた語学力が、ここで結びついたんですね。ということは、博士論文のテーマを途中で変更してシュミッツに?
そうです、テーマをシュミッツに変えて、2年で博士論文を書き上げました。日本でシュミッツを専門で研究している人は誰もいなかったので、何を言っても大丈夫!という気持ちで。面白いのでどんどん読んで研究もペースアップして、毎年学会発表もやったし、博論提出までの2年で短い論文も5~6本くらい発表しました。
この経験からつくづく思ったのが、研究って、本当に自分が面白いと思っているテーマに取り組まないといけないな、ということです。もちろん、一般的に認識されている問題点にフォーカスして研究を進めるというやり方もあります。でも、本当に自分がそれに興味があるかは別問題。私は、ハイデガーを6年研究して、ようやく「自分、ハイデガー全然好きじゃなかった!」とわかりました。
最終回は今につながる哲学対話との出会いについて伺います。
-300x57.png)