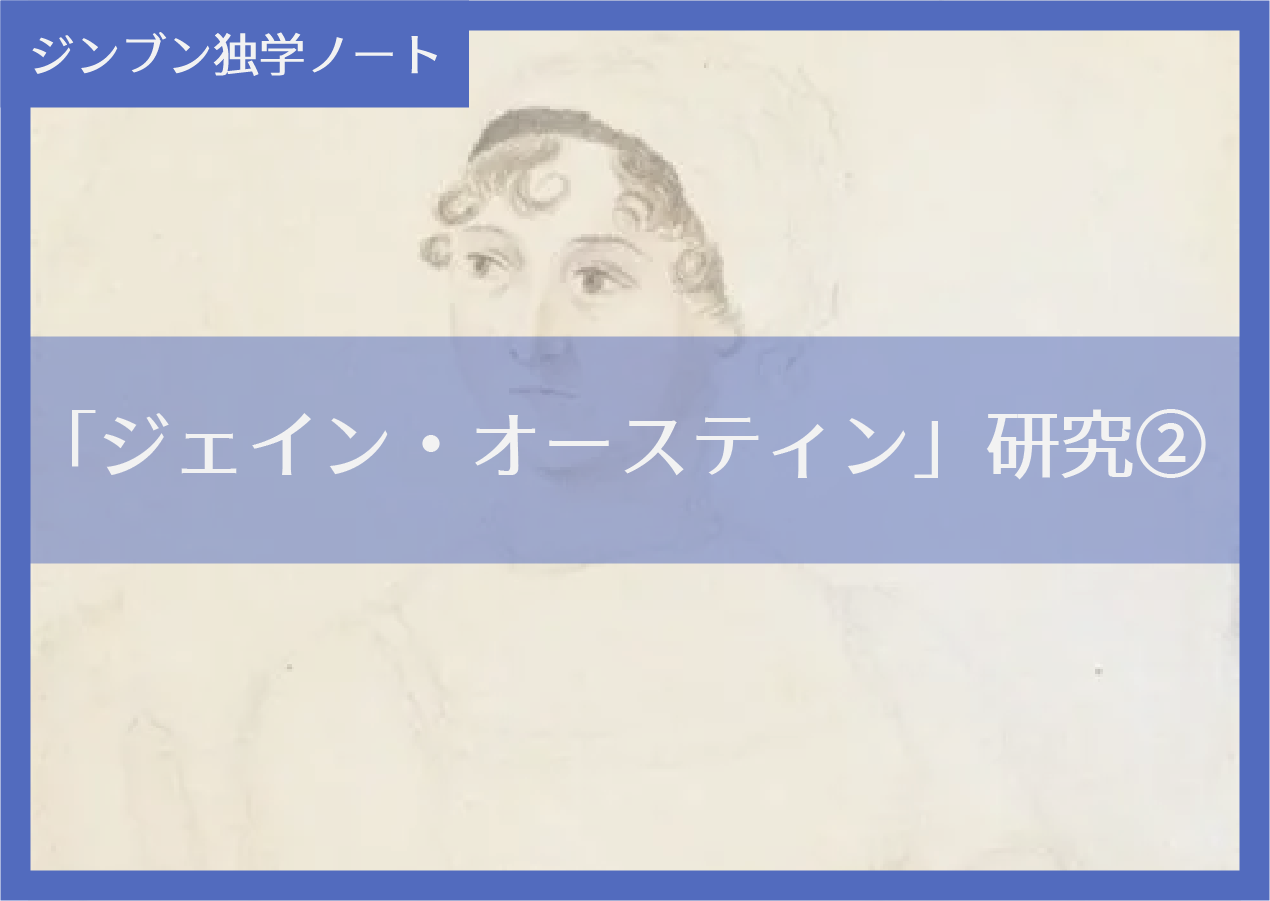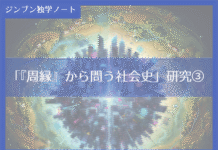ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十九回となる今回のインタビューでは、歴史が「何を」語るかではなく「いかに」語られるかという視点から、ジェイン・オースティンの作品を読み解き、文学の新たな価値と可能性を切り拓く、英文学研究者の広本優佳さんにお話を伺います。
歴史の「中身」から「語り方」へ
——そもそも、大学選びの時点では、どのようなことを考えていらっしゃいましたか?
かなり迷いましたね。周りにロールモデルもほとんどいなかったですし。最終的に東大に決めたのは、これもまたミーハーな理由なのですが、「歴史」への強い憧れがあったからです。
——歴史、ですか。
はい。私は東京の郊外、いわゆる新興住宅地で育ったので、自分自身の故郷やルーツというものにコンプレックスがありました。たとえば、京都出身の友人が羨ましくて。自分の人生という物語ともっと大きな歴史のあいだに連続性を錯覚したかったんです。よく考えれば歴史の全く存在しない場所などないと思いますが、いつも形にこだわる単純明快な私は、古い町並みのような、目に見える「歴史」というシンボルに強く惹かれました。後に留学先としてオックスフォード大学を選んだのには、いろんな理由がありますが、そうしたやや不純な動機が混入していたことも認めなければなりません。
——なるほど。ご自身のアイデンティティを位置づけるための、人工的な「歴史」を求めていた。
そうかもしれません。ジブリの『耳をすませば』という映画で、同じく新興住宅地出身の主人公が故郷への郷愁を歌ったアメリカの曲「カントリー・ロード」を翻訳する場面で、「ふるさとって何か、やっぱりわからない」とつぶやきます。それに強く共感していました。だからこそ、歴史や伝統といった、自分にはない(と思っていた)ものに憧れました。その憧れが、私にとっての原動力だったのだと思います。
——学部選びでは、迷いはありませんでしたか?
文学部、という点だけは決めていました。ただ、併願した私立大学は、フランス文学科や史学科などで、実は英文学科は一つも受けていなかったんです。
——現在は英文学が専門なのに、ですか。
当時は、受験勉強のための、それ自体が目的化した英語が嫌いになってしまっていて。外国語を話せること自体への憧れはあったので、どうせなら違う言語を学びたい、と思っていました。東大のように、入学後に専門を決められるモラトリアム期間がなければ、今頃フランス文学を研究していた可能性も十分にあります。
——では、様々な学問に触れるなかで、やはりオースティンに帰ってきた、と。
その通りです。西洋史やドイツ文学など、色々な授業に顔を出しては浮気を繰り返しましたが、結局、やっぱりオースティンを読みたい、という気持ちが一番強かった。オースティンがもし違う言語で書いていたら、私はその言語を専門にしていたと思います。私にとって英語は、もともと彼女の作品を読むための「手段」であって、「目的」ではなかったんです。
——博士課程で、オックスフォード大学へ留学されています。本場のイギリスでオースティンを研究するという経験は、どのようなものでしたか。
印象に残っているのは、韓国出身の友人に言われた一言です。「アジア系で、イングランドの文化の中核をなすような作家を専門にするのは珍しいね」と。彼女自身は【ポストコロニアリズム】、つまり、かつての植民地支配がもたらし、現在も持続する影響を、批判的に問う研究をしていました。彼女は、自分のアイデンティティと関連するテーマを選ぶ研究者が多い、ということを伝えたかったのだと思います。
——ご自身の出自と研究テーマの関連性を問われたわけですね。
その時、思ったんです。自分の研究は、自分の出自と関連していなければならないのだろうか、と。もちろん、マイノリティとしての経験から研究テーマを見出す、というプロセスは重要だと思いますし、意義深いものです。でも、それは誰もが通る経験ではありません。
——確かに、そうですね。
イギリスの大学院に出願する際には、なぜこの研究をしたいのかという「志望理由書」のようなものを書かされますが、そこでは自身の人生と研究を結びつけたストーリーが求められがちです。でも私は、むしろオースティンが、自分とは全く違う時代、違う文化に生きた「異質」な存在だからこそ、強く惹かれたところもあります。自分と違うものを通して、初めて自分自身の輪郭も見えてきます。その距離感を楽しむことに、研究の面白さを感じていたんです。