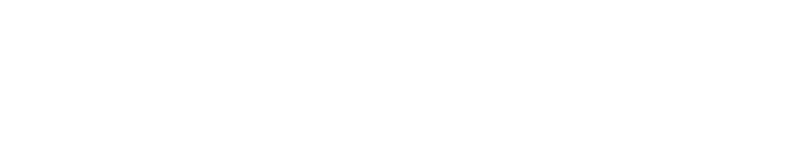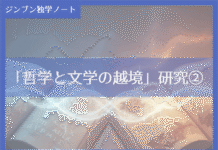ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三十二回となる今回のインタビューでは、国際交流基金での実務経験と中国駐在を経て、日中外交史における文化交流の歴史を新たな視座で読み解く、金子聖仁さんにお話を伺います。
原点としての南京体験と国際関係論への転向
——本日は、東アジア国際関係史をご専門とされる金子さんのお話を伺います。現在の研究テーマにたどり着くまでの歩みや、一度社会人を経験されてから研究の道に進まれた経緯について、詳しくお聞かせください。
よろしくお願いします。
——ご専門は「東アジア国際関係史」「日本外交史」と伺っています。歴史や国際関係には、いつ頃から関心を持たれたのでしょうか。
高校生の頃から歴史は好きでしたね。特に世界史が得意で、大学でも歴史を勉強したいと思い、東大の文科三類に入学しました。
——当初から、研究者になりたいという思いもありましたか。
いえ、それが大学2年生の時に転機がありまして。2013年の春休みに、大学の交流プログラムで中国の南京大学に行ったんです。それが初めての中国でした。
——2013年というと、2012年の尖閣諸島国有化問題の影響で、日中関係がかなり緊張していた時期ですね。しかも南京という場所で。
そうなんです。行く前はメディアの報道もあって、正直少し怖いイメージも持っていました。ところが、現地でフィールドワークとして市内の人たちにインタビューしてみると、皆さんものすごく優しかった。
そのギャップに、自分の無知を恥じました。もっと中国のことを知りたいと強く思ったのが一つ。もう一つは、当時の私のような若者同士の文化交流が、国家間の安定的な関係を築く上で重要なんじゃないかと実感して。そこから「文化交流を仕事にしたい」と思うようになりました。
——よい意味でカルチャーショック。それが原点になったのですね。
ええ。そこから外交政策としての文化交流に関心が芽生え、就職活動では国際交流基金(The Japan Foundation)を志望しました。
卒業論文も、その関心からテーマを選びました。戦前の日本が中国に対して行っていた「文化交流」事業の歴史を扱ったんです。
——戦前の、ですか。
日中戦争に向かっていくあの時代にも、もちろん双方向性や水平性はなかった点で今日とは様相が異なりますが、「文化交流」は行われていました。今日的発想では平和に結びつきそうな「文化交流」を推進していたにもかかわらず、なぜ戦争に至ってしまったのか。あるいは、その複雑な日中関係において、「文化交流」が果たした役割や限界は何だったのか。その歴史を知りたいと思ったんです。
——少し遡りますが、そもそも東大の文科三類を選ばれたのは、どのような理由からだったのでしょう。
私は山形県の酒田市出身で、周りに東大に進学する人はほとんどいない環境でした。私自身は高校2年の春まで東京に行ったこともなかったですし。ちょうど当時、漫画の『ドラゴン桜』が流行っていまして、その影響もあって(笑)。文系の中で、当時は合格ラインが比較的ねらえそうな科類、という感じで文三を選びました。
——歴史好きの入り口は、何かあったのですか。
NHKの大河ドラマが大好きでした。特に高校生の頃からよく見ていましたね。ちょうど『坂の上の雲』が放映されていた時期でもあり、様々な人物との出会いを通じて主人公が成長していく人間ドラマがすごく面白かった。もちろんドラマなのでフィクションが含まれますが、歴史上の「こことここが繋がるんだ」という感覚は、もしかしたら今の研究の面白さにも通じているかもしれません。
——大学に入学されてからは、すぐに歴史の道へ?
いえ、それがまたカルチャーショックを受けまして。文三には、歴史にものすごく詳しい、いわば「歩く教科書」みたいな学生がいたんです。今にして思えばツッコミどころ満載の思考回路ですが、これは歴史学では彼らに勝てないかもしれない、と。
——歩く教科書!(笑)それは圧倒されますね。
それで、歴史を土台にしつつ、現代社会を考えるような学問はないか、と探し始めました。私が入学したのは2011年で、当時はアラブの春など政治変動が激しい時期でした。そんな時、法学部の藤原帰一先生の『デモクラシーの帝国』(岩波新書、2002年)を読んで感銘を受けました。世界情勢に対して抱いていた漠然とした疑問と、本の内容がリンクしたんです。
そこから国際政治や国際関係に関心を持ち、教養学部の国際関係論コースに進みました。
次回は中国駐在中の体験について伺います。