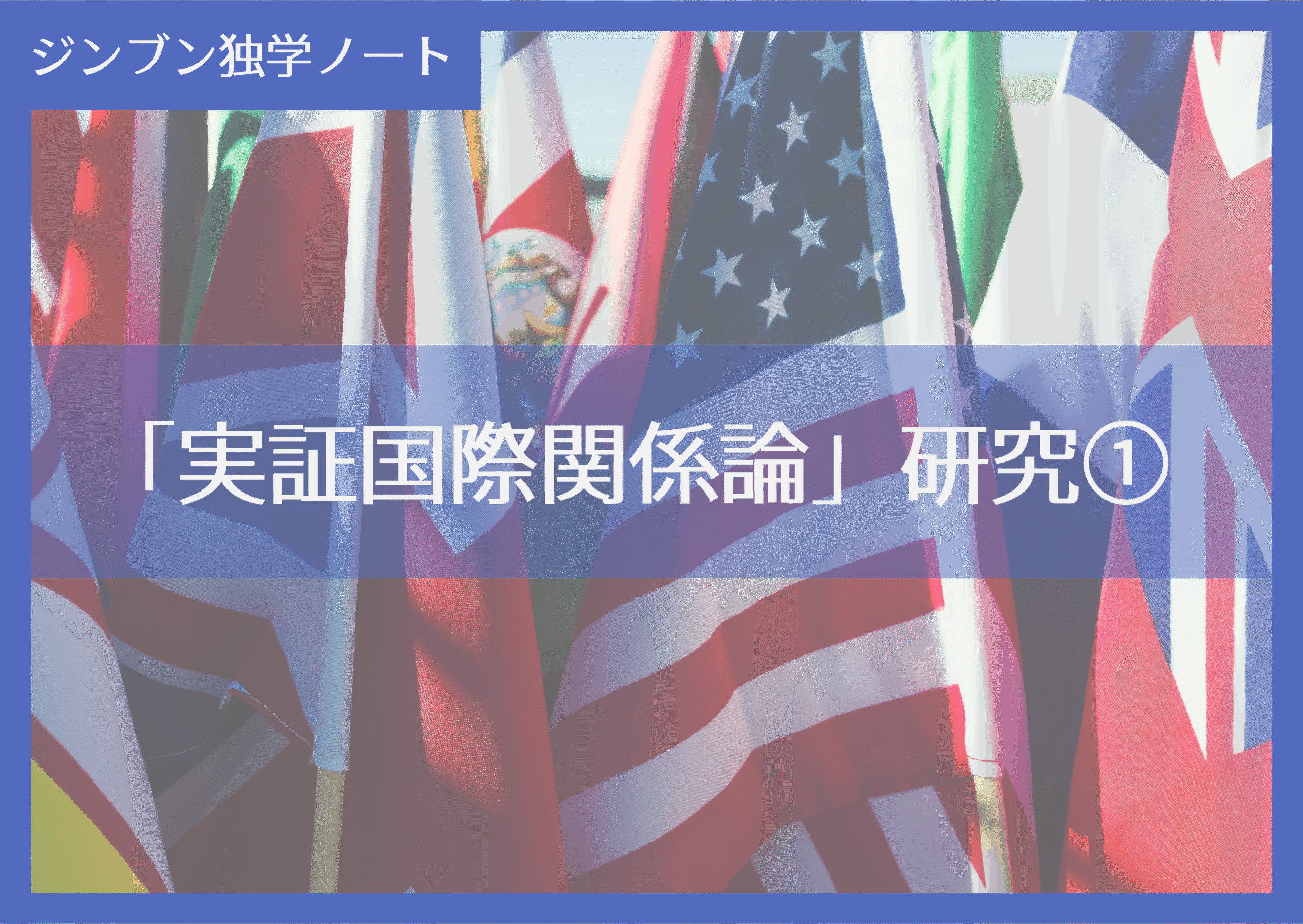ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第二十八回となる今回のインタビューでは、様々な理論が論争を繰り広げる国際関係論の世界に、歴史をデータとして分析する「実証」的アプローチを持ち込み、現代における米中関係の行方を探る、研究者の洲脇聖哉さんにお話を伺います。
人文学から量的分析へ:研究者への道
——本日はお時間をいただきありがとうございます。洲脇さんは、お仕事をされながらご自身の研究にも深く関わっておられます。その独自の歩みや研究の世界について、今日はじっくりお話を伺えればと思います。どうぞよろしくお願いします。
お世話になります、よろしくお願いします。そんなにたいそうな話ができるか分かりませんが、精一杯お話しします。
——早速ですが、洲脇さんは様々な場でご自身の研究について話される機会があるかと思います。「何の研究者ですか?」と尋ねられた時、どのように自己紹介をされていますか。
最もシンプルに表現するなら「国際関係論の研究者です」と答えることが多いです。もう少し詳しく説明を求められた際には、「量的手法も用いています」と付け加えることで、少し専門性を出すようにしていますね。
——国際関係論と一口に言っても、歴史学や社会学に近いアプローチなど、様々な手法があります。その中で、洲脇さんが用いられている量的手法というのは、この分野では伝統的なものなのでしょうか。
いえ、伝統的にはむしろ逆かもしれません。国際関係論は社会科学に属しながらも、人文学との関わりが深い学問です。そのため、例えば世界史の出来事をモデル化して分析するといった、歴史学に近い質的なアプローチが主流でした。統計などを用いる量的手法は、どちらかといえば重視されてこなかった側面があると思います。私自身も、学部時代は人文学の領域にいたので、その感覚はよく分かります。
——なるほど。ご自身の出自は人文学にありながら、なぜ量的手法という異なるアプローチに関心を持たれたのですか。
大学院で本格的に【国際関係論】を学び始めた頃、学界では「イズム論争」とでも言うべき状況がありました。【現実主義(リアリズム)】や【リベラリズム】といった、様々な「〜主義(イズム)」が存在し、「自分はこの理論に属しているから、このように世界を見る」という立場が乱立していたのです。
——それぞれの理論的立場から国際関係を分析する、ということですね。
はい。しかし、それが私にはどうも主観と主観のぶつかり合いのように見えてしまって。もっと客観的に、誰もが納得できる形で結論を導き出すことはできないだろうか、という思いが募っていきました。ちょうどその頃、大学院の必修科目で統計学を学んだのですが、これが非常にしっくりきたのです。
——統計学が、客観性への渇望と結びついた。
その通りです。もちろん、どのデータを選ぶかといった部分に主観が入り込む余地はゼロではありません。それでも、一度データを揃えてしまえば、あとは手法に則って分析するだけ。そこから導き出される結果は、誰が見ても動かしようのない客観的なものです。例えば、アメリカの学者が自国に有利な主張をし、中国の学者がまた自国に有利な主張をする、といった「国益を代弁する」ような議論が散見される中で、統計学という手法は、そうした主観のぶつかり合いから抜け出すための強力な武器になるのではないか、と感じました。それが、この道に進んだ大きなきっかけです。