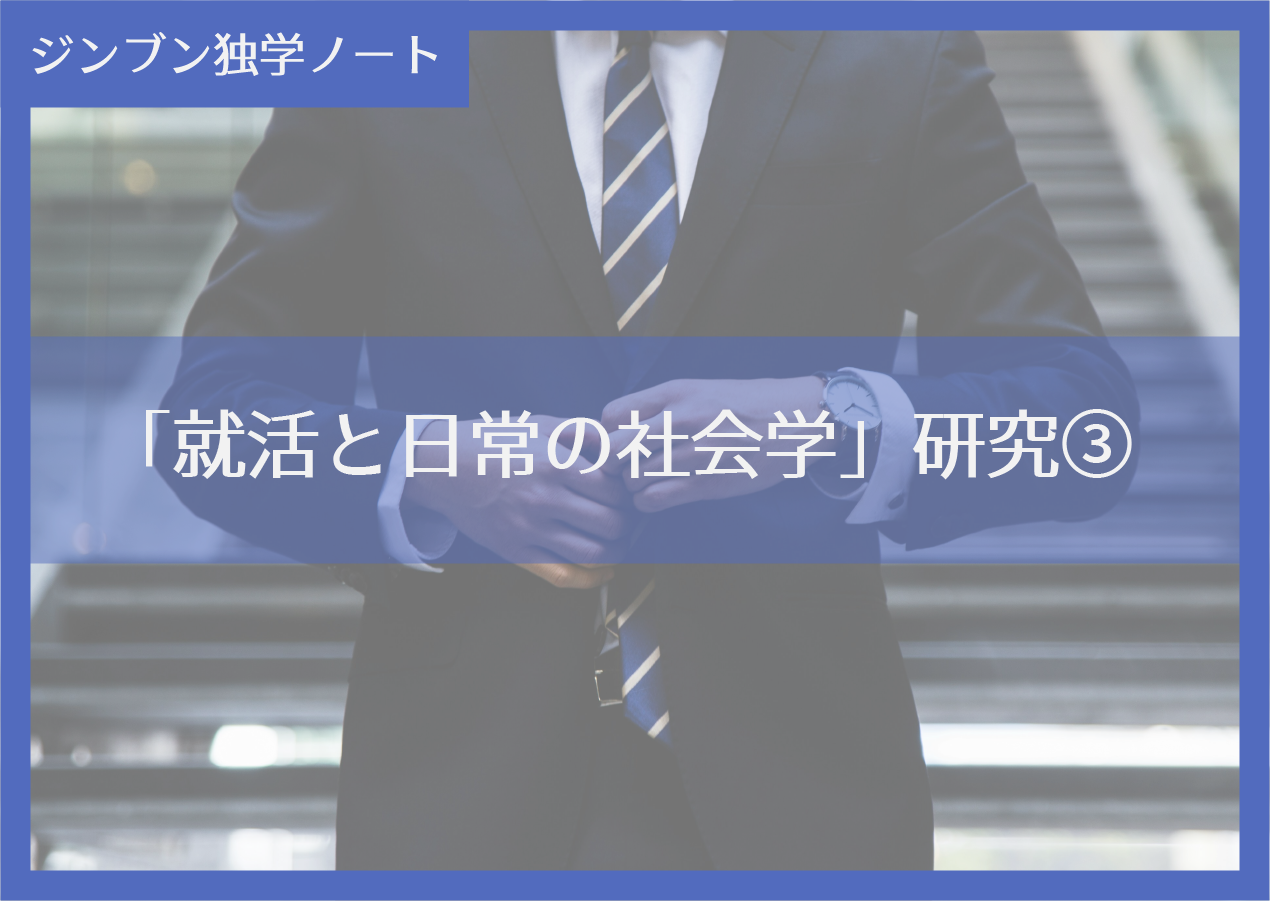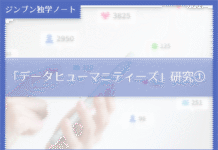ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第二十一回となる今回のインタビューでは、就職活動という日常に潜む「謎」を、社会学の視点から解き明かし、複雑な社会の新たな見取り図を描き出す、研究者の和藤仁さんにお話を伺います。
「わからない」から世界は面白くなる
——なるほど。日常の些細なコミュニケーションの謎から、社会の構造を読み解いていくのですね。最近は「やりたいこと」というテーマにも取り組まれているとうかがいました。これもまた、就活生を縛る厄介な言葉です。
そうなんです。「この会社に入って、やりたいことは何ですか」と聞かれる。私たちは、何か行動を起こす際に、意欲や意思といった「動機」を「やりたいこと」という言葉を通して説明することを求められます。
実は「やりたいこと」というテーマは、ここ20年ほど、社会学で断続的に研究されてきました。その源流は、【就職氷河期】のフリーター研究に遡ります。
——フリーター、ですか。意外な繋がりです。
バブルが崩壊し、良い大学を出て良い会社に就職するという、かつての成功物語が崩れ去った時代。就職したくてもできなかった若者たちが、自らの生き方をどう意味づけるか。その時に「やりたいこと」という語りが用いられました。例えば、バンドマンのような夢を追うタイプのフリーターは、「自分にはやりたいことがあるから、今はフリーターなんだ」と語ることで、自らの選択を正当化し、アイデンティティを保っていたわけです。
——自分のための物語、ですね。
はい。しかし、当時の就職氷河期と、現在の学生が置かれている状況は全く異なります。そこで私は、90年代から2013年頃までの就職難の時代を「就職氷河期」と捉え、それ以降の売り手市場の時代を【ポスト就職氷河期】と名付けて、両者を比較する研究を進めています。就職が困難だった時代に語られた「やりたいこと」と、今、売り手市場の中で学生たちが語る「やりたいこと」は、きっと違うはずだと考えているんです。
——時代状況を捉えるために、新しい概念を提案されているのですね。まさに社会学の役割そのものです。
ありがとうございます。まだ検証中の仮説ではありますが。こうした研究を通して私が一貫して試みているのは、個人の問題を個人の「弱さ」や「判断ミス」に帰結させない、ということです。
——自己責任論に陥らない、と。
はい。まず、私たちが生きている社会の構造、個人が抗おうとしても抗えない大きな力から物事を考えたい。もちろん、全てを社会のせいにしてしまうのも違う。かといって、全てを個人の意思決定の問題にしてしまうのも、あまりに窮屈です。そのどちらにも偏りすぎず、社会のメカニズムと個人の経験がどう関わり合っているのかを丁寧に記述する。このようにして、複雑で見通しのよくない社会の論点整理をするというのは、社会学の大事な仕事だと思います。
——ご自身の内側からではなく、あくまで客観的な視点を保ちつつ、社会という複雑なものを描き出す。
私たちは社会の中にいるので、完全に客観的になることはできません。だからこそ、自分がどのような視点から社会を語ろうとしているのかを自覚的になる必要があります。その上で、社会の新たな見方や見立てを提示する。
【打越正行】さんの『【ヤンキーと地元】』という本がありますが、これは著者がヤンキーたちと生活を共にすることで、彼らの世界を描き出した名著です。この本を読むと、これまで知らなかった世界を知ることができると同時に、自分たちが生きる社会やコミュニケーションのあり方を、全く違う視点から見つめ直すことができる。
私の研究も、そうありたいと思っています。就活生の「進捗」の話も、「思いやりと陰口」の話も、それを読んだり考えたりすることによって、自分の日常が少しだけ違って見え始める。その瞬間に、私は社会学の面白さを感じ続けているんです。
——お話をうかがっていると、和藤さんはまるで、魚が自分が泳いでいる「水」そのものに気づき、それを語ろうとしているかのようです。社会という当たり前の環境の、何に違和感を抱くか。その感性が研究の源になっているのですね。
そうかもしれません。社会学という学問の枠組みの中にいると、あらゆるものが面白く見えてくるんです。ただ、「社会学面白い」に至るために必要な「考える」という作業は、実は昔からとても苦手でしたね。
——そうだったのですか。
ええ。昔は、嫌なことがあっても、何が嫌なのかを言葉にできず、ただモヤモヤしているだけでした。読書感想文も大の苦手で。「面白かったんだから、それでいいじゃないか。放っておいてくれ」とずっと思っていました。小学生の時、先生から「和藤くんには理性がない。本能で生きている」と言われたこともあるくらいです。
——それは先生の言葉が過ぎますね……。
でも、大学院で研究をするようになって、少しずつ「考える」とはどういうことなのかが分かってきたんです。社会学の言葉を通して、世界や自分自身の経験を記述する、という技術を身につけたのだと思います。
——新しい言語を獲得されたのですね。
はい。今なら、『【ぼくらの七日間戦争】』の読書感想文を、「廃墟に立てこもる彼らの姿に、現代社会における〇〇という構造を見ることができる」といったように、何かを「見立てて」書くでしょうね。良くも悪くも、社会学というフィルターを通して世界を見るようになっている。でも、そのおかげで、かつては分からなかったことが分かるようになり、世界が格段に面白くなりました。飽きることがないんです。
——やりたいこと、というよりは、もはや苦なくできてしまうことになっている。
そうですね。もちろん、学会前などは苦しい時もありますが、幸いにも、この面白さから興味が尽きることはありません。結果的に、自分に合っていたのかもしれないですね。
——では最後に、その尽きることのない探究心は、今、何に向かっているのか、うかがってもよろしいでしょうか。
そうですね、深く考えているわけではないのですが、「〇〇活」という言葉が面白いなと思っています。就活、婚活、保活(保育園を探す活動)、そして終活。最近では「推し活」なんて言葉もあります。
——あらゆるものに「活」がつきますね。
「〇〇活」という名前がついた瞬間に、それは「活動」そのものが目的になっていく。つまり【自己目的化】するのだと思います。かつて私たちの生活の一部であったものが、切り出され、名前をつけられ、市場に投入されていく。葬式が葬儀社の産業になり、ファンが個人的に応援していた行為が「推し活」という産業になる。
——日常が産業に回収されていく感覚は、よく分かります。
そこは、資本主義という大きな構造と、私たちのミクロな日常生活が出会う結節点です。「〇〇活」という言葉を切り口にしたとき、現代社会のどのような姿が見えてくるのか。まだ漠然としていますが、強い関心を抱いています。結局のところ、よく分からないんですよね、社会って。
——その「よく分からない」という感覚が、和藤さんを突き動かす原動力になっているのですね。
そうなんだと思います。これからも、きっと何かを「よく分からないな」と思いながら、ぬるっと研究を続けていくのでしょうね。