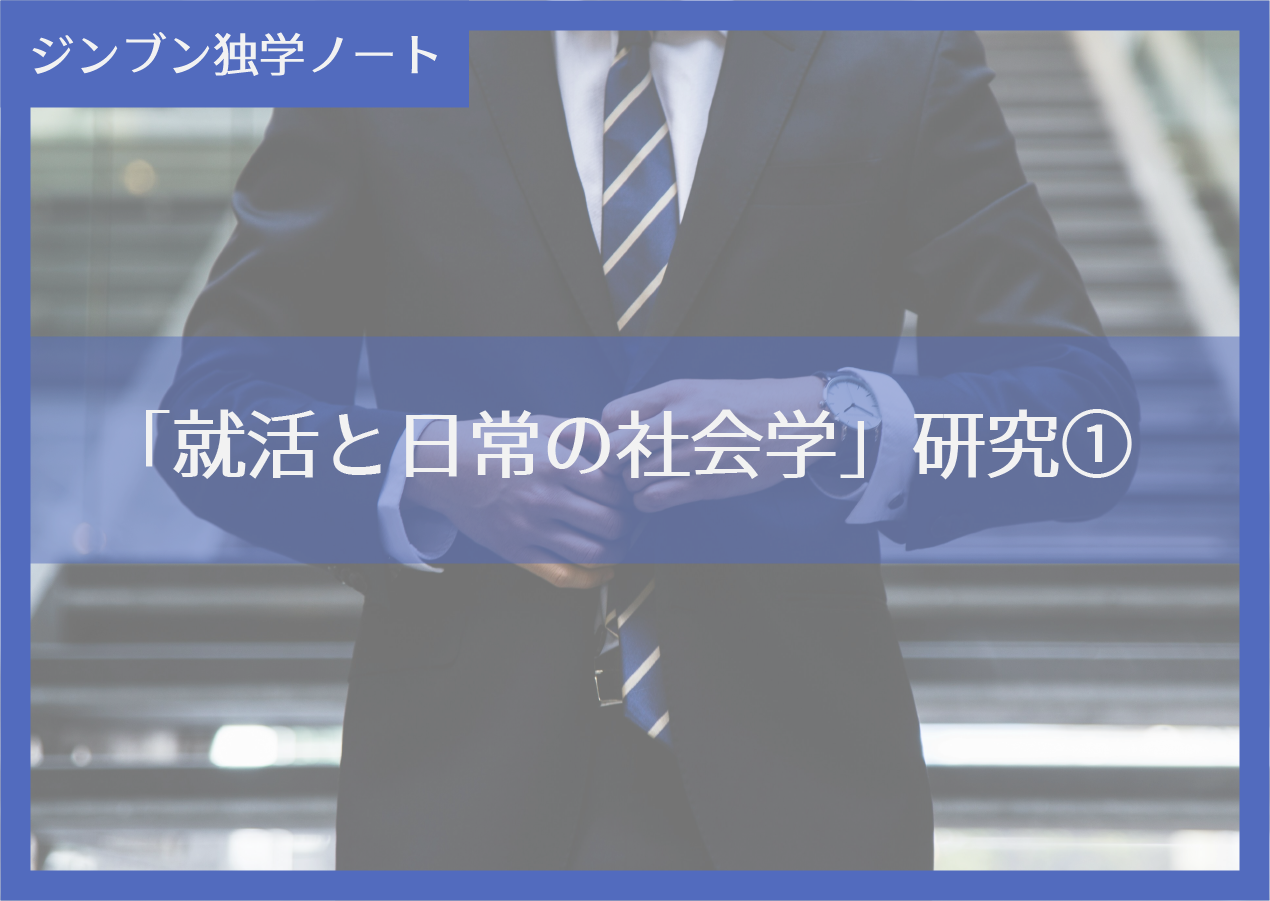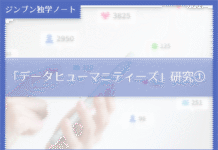ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第二十一回となる今回のインタビューでは、就職活動という日常に潜む「謎」を、社会学の視点から解き明かし、複雑な社会の新たな見取り図を描き出す、研究者の和藤仁さんにお話を伺います。
社会の見取り図を描く学問
——本日はよろしくお願いします。まず、和藤さんご自身についてうかがわせてください。研究者として自己紹介をされる際、ご自身のことを「何の専門家」だと説明されることが多いですか?
そうですね、相手によって説明の仕方は変わりますが、一つはシンプルに「社会学者」あるいは「社会学をやっています」と答えることが多いです。
——社会学、というと非常に幅広い分野ですが、あえて「〇〇社会学」のように領域を限定されないのですね。
ええ、意識しているところはあります。他の社会学者は、例えば「教育社会学」や「労働社会学」といったように、自分の専門を名乗ることが多いんです。私たちの間では、それを俗に「連字符社会学」と呼んだりもするのですが。
私の研究対象は主に就活生なのですが、彼らは教育と労働のちょうど中間にいるような、特定の領域では捉えきれないマージナルな存在です。ですから、自分を「〇〇社会学者」と名乗ろうとすると、どうも自分的にしっくりこない。それで、学者の前では今のような説明をしますが、分野外の方にはシンプルに「社会学をやっています」と伝えることが多いですね。
——なるほど。就職活動を研究されている、と。
はい。ただ、これも他分野の研究者、例えば自然科学や認知科学の方に「就活生の研究をしています」と話すと、「それをどうやって研究するんですか?」と不思議そうな顔をされることがよくあります。
——確かに、素人からすると、インタビューをするのか、データを分析するのか、何をどうするのだろうと興味が湧きます。
そう思われるのも無理はないなと、最近、他分野の方と話していて感じるようになりました。中にいると当たり前になってしまうのですが。ですから、対象から説明する時は「就活の研究者です」と名乗ることもありますね。話す相手や状況に応じて、分野で自己紹介するか、対象で自己紹介するかを使い分けている感じです。
——和藤さんがおっしゃるように、就職活動という現象は、学生側から見るか、企業側から見るか、あるいは私たちのような採用に関わるサービスを提供する側から見るかで、全く様相が異なります。様々な立場からの声が飛び交う中で、社会学という学問はどのような役割を果たすとお考えですか。
まさにおっしゃる通りで、社会は見る角度によって全く違う姿を見せます。就活一つとっても、学生、企業、プラットフォーマー、それぞれが見ている現実は異なりますし、それぞれの立場から「自分たちが一番大変だ」という声が大きくなることもあります。
——分かります。それぞれの主張がぶつかり合って、誰も幸せにならないような状況に陥りがちです。
そうなんです。みんなが大変そうだ、で終わってしまっては、社会のことはよく分からないままです。その点から社会学に与えられる説明として、そうしたバラバラに見える現象を、迂闊に単純化することなく、社会全体の「見取り図」として捉えようとする学問だということができます。
経済学が経済という明確な視点から社会を見るのに対し、社会学は「社会から社会を見ます」と言う。一見すると何も言っていないようで、情報量ゼロに聞こえるかもしれません。だからこそ、他の学問に比べて厳密さに欠けたり、複雑でわかりにくいと思われることも少なくありません。
——複雑なものを、あえて複雑なまま捉えようとするのですね。
はい。他の視点ではこぼれ落ちてしまうものを拾うために、あえて視点を広げてから、どこに切り口を設定すればその事象を捉えられるのかを探る。そういうモチベーションがあるように思います。ですから、社会学は社会科学であろうとしながらも、非常に【人文学】的な側面も持っています。社会に対する新しい見方や価値観のモデルを提案できる。それが社会学の面白さであり、いいところだなと感じています。
——既存の価値観では生きづらさを感じている人にとって、新しい視点を与えてくれる、救いのような学問かもしれませんね。
そうですね。【ジェンダー・スタディーズ】やセクシュアリティ研究、あるいはケアの研究なども、まさにそうした役割を担っていると思います。
次回は研究者への道について伺います。