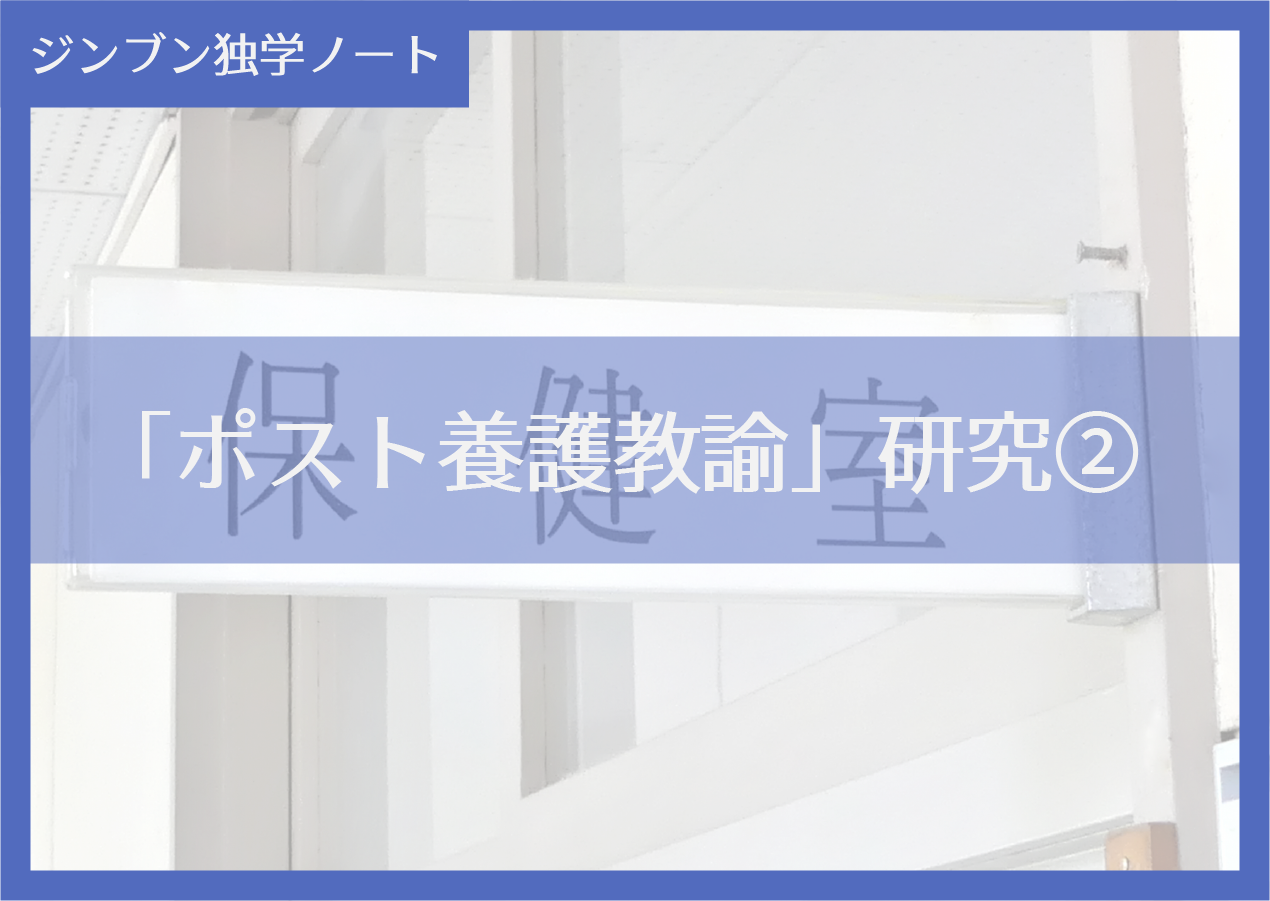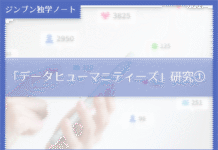ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第二十六回となる今回のインタビューでは、看護と教育、臨床と研究という複数の領域を越境した独自の視点から、学校が抱える構造的な問題に迫る、教育学研究者の柏木睦月さんにお話を伺います。
「私がいないと困る」学校への違和感
——すごい転換ですね。そこからまた、どのようにして養護教諭の道へ?
大学4年の9月に、教育実習に行ったんです。そこで、私の人生がまた大きく変わりました。
私自身、子どもの頃はずっと入院していて、周りの子たちもみんな「学校に行きたい」と泣きながらリハビリを頑張っていました。抗がん剤で髪が抜けていくような子たちでさえ、学校に復帰することを願っていた。
なのに、教育実習で保健室にいると、「学校に行きたくない」「クラスがしんどい」と言って、五体満足で学校に通えるはずの子たちが逃げてくるんです。このギャップは一体何なんだろう、と。学校というのは、子どもたちにとって一体どういう場所なんだろうか、と強烈に考えさせられました。
子どもたちに優しく寄り添いたいとか、共感したいとか、そういう気持ちからではありません。この不思議な場所で働きながら、その正体を探ってみたい。そう思って、実習が終わった10月には「養護教諭になろう」と決めていました。
——運命的な出会い直し、という感じがします。
ただ、その時点で教員採用試験は終わっていますし、何より看護師や保健師の経験がないまま養護教諭になるのは違うな、と。求められるであろう看護系の知識に、自信を持って応えられるようになりたかった。
そこで、看護師と保健師の国家試験に合格したことが確定した日に、まだ紙媒体だった「タウンワーク」をめくって、4月1日から雇ってくれるところを探しました。片っ端から病院や保健所に電話して、「この3月に卒業する新人です。養護教諭になるために学ばせていただきたいです。1年後には養護教諭になるために辞めます。それでもよければ雇ってください」と正直に伝えたんです。
——その正直さと行動力がすごいですね。
それで雇ってくれた病院と保健所で、1年間だけ臨床経験を積みました。その1年間は、常に「この知識や経験を、学校という場でどう活かせるか」ということだけを考えていましたね。働いていた脳神経内科のクリニックでは、受付からレセプト(診療報酬明細書)、検査技師の役割まで何でもやらせてもらいながら、院長先生に「学校でこういう子どもがいたらどう対応すればいいですか?」としつこく質問していました。保健所でも、1歳半や3歳児の健診を担当させてもらい、学校に上がる前の子どもたちのことを学んでいました。いわゆる「新卒」というカードを全て捨てるわけですから、その1年間を棒に振るわけにはいきませんでした。
——その濃密な1年を経て、いよいよ学校現場へ。
はい。ただ、養護教諭は学校に一人しかいないことが多く、採用の倍率がものすごく高いんです。私が受けた時は20倍くらいありました。兵庫県で30人の枠に500人、東京都だと100人の枠に1000人近くが応募するような世界でした。なので、私も一度では合格できず、最初は産休に入られた先生の代わりとして、高校で働き始めたのがスタートでした。
——ご自身のレンズを通して見た学校現場は、いかがでしたか。
働き始めてしばらくは、「先生がいて助かる」「頼りになる」と言われることが、自分の承認欲求を満たす「餌」になっていました。でも、3〜4年経った頃から、現場で「養護教諭らしくないね」とか、会議などで積極的に発言すると「養護教諭のくせに(前に出ないで)」と言われることが増えてきて。どうやら、養護教諭には何か暗黙の「らしさ」や「フレーム」があるらしい、と気づき始めたんです。
——「らしさ」の押し付け、のようなものでしょうか。
ええ。私は教育職の一員なのだから、生徒会活動などにも積極的に関わりたいと思っていました。でも、どうやら養護教諭は、担任の先生より前に出てはいけないポジションらしい。市内の年齢の近い養護教諭の中には、少し保健室を不在にしただけで「子どもが行ったのにいなかった」と保護者から責められた上に、管理職からも「あなたが悪い」と言われて悩んでいる人もいました。
そんな中で、ぼんやりと「養護教諭って、何のためにいるんだろう」と考え始めたんです。この問い自体は、実はこの分野で50年以上も前から議論されていることだと後から知るのですが、当時は知る由もありませんでした。
——その問いが、さらに深まるきっかけがあったのですね。
はい、決定的な転機がありました。ある時ふと、「私がいないと困るよ」と言われる状況って、裏を返せば「私がいないと回らない学校」ということだよな、と。それは、私の怠慢なんじゃないか、と思ったんです。
研修に行くと、ベテランの先生方が「私がいなくなったら、この学校は困るのよ」と、どこか嬉しそうに話している。若手は「養護教諭が頑張ってこそ学校は支えられるんだから、もっと努力しなさい」と叱咤激励される。最初はそれでいいと思っていたけれど、だんだん違和感が大きくなっていきました。私が頑張るべき方向は、そっちじゃないんじゃないか、と。
この問いは、もう現場の研修では答えが見つからない。そう感じた時、大学院へ行こうと決意しました。
——そして、数ある大学院の中から東大を選ばれた。何かご縁があったのでしょうか。
もともと、いつかは大学院で学びたいと思っていました。ただ、「現場で解決できない問い」が見つかった時に行こうと決めていたんです。
その頃、母校(兵庫県立大学)にゲストティーチャーとして呼ばれる機会があって。そこで、学生時代に授業を担当してくれた先生とエレベーターの中でばったり再会したんです。その先生から「今年からあなたが卒業した後に教職の先生が変わって、東京の大学から新しい先生が来たんだけど、こちらで養護教諭の知り合いがいないからあなたを紹介して良い?」と言われて。紹介されたのが、東大の基礎教育学コース出身の池田雅則先生でした。
池田先生とお話をする中で、基礎教育学コースで学ぶ面白さを知っていきました。池田先生とのやり取りと並行して、大学時代のもう一人の恩師である柏木敦先生にも大学院の相談をしに行ったら、「お前は絶対相談に来ると思ってた。その時は、絶対に東大を勧めようと決めていた」と言われて。池田先生からも「僕の後輩になりますか?」と。ここまで来たら、もうご縁だな、と。それで東大を受けることにしました。
最終回は今に繋がる気づきについて伺います。