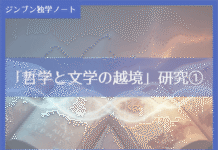ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十三回となる今回のインタビューでは、山田理絵先生にお話をうかがいます。山田先生は東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属共生のための国際哲学研究センター(UTCP)上廣共生哲学講座の特任助教として、摂食障害やタトゥーの研究を行う傍ら、シンポジウムやワークショップの企画を行っていらっしゃいます。
これからの取組
——修士論文を完成させた後は、博士課程に進学して、研究テーマもさらに広がったそうですね。
筑波大学の人文社会系研究科を2014年3月に修了しました。
その後、同年4月に東京大学の総合文化研究科の博士課程に進学し、科学史・科学哲学研究室で、現象学、精神医学の哲学などの研究をなさっている石原孝二教授にご指導いただきました。
博士課程では、摂食障害に限らず、様々な精神障害やそれに関する医療、福祉、当事者の実践について学ぶ機会をいただきました。
例えば、当事者研究の実践で知られる、北海道浦河市にある「べてるの家」に研修でまいりまして、べてるの家のメンバーやスタッフさんと1週間ほど過ごすという機会をいただきました。
また、国外においては、イギリスの Recovery College というプログラムの視察、イタリア・トリエステや、デンマークにおける精神保健医療関連施設の視察、ワークショップの参加などを行いました。これらの視察内容は、雑誌に記事として投稿されています。
また研究論文としては、精神疾患からの「リカバリー」という概念についての考察、日本の精神医療システムにおける家族の位置付けに関するものを書きました。
最後に、博士論文での研究課題としては、引き続き摂食障害を取り上げました。特に、摂食障害の原因を家族に求めるような考え方がどのように流通してきたのか、批判されつつも生き残ってきたのはなぜなのかということを歴史社会学的に検討しました。ちなみに2017年9月に博士課程を単位取得満期退学しました。その後、2021年10月に博士論文 「摂食障害の歴史社会学―食行動の逸脱はどのように語られてきたのか―」を提出しました。
——山田さんの研究が、これからどんな広がりを見せるのか、とても楽しみです。現在は、UTCP(東京大学大学院総合文化研究科附属共生のための国際哲学研究センター)で活動をされていますが、どんなテーマに取り組んでいるのですか?
東京大学UTCPでは、シンポジウム等の企画・運営と、様々なフィールドの専門家や活動団体との社会連携を主たる業務としています。これまでに、メンタルヘルス、身体、環境、ジェンダーなどに関する企画を実施してきました。また、近年はシリーズ企画をいくつか実施しています。
そのうちの一つは2023年からスタートした「Second View」という企画です。
——具体的に、どんなことが考えられるのでしょうか。
シリーズ企画「Second View」は、<現代社会の中でいかにして多様な人たちが共生していけるか>というテーマについて、これまでとは違う別の観点(Second View)から検討することを目的としています。このシリーズの中で特に焦点を当ててきたのは、受刑者であってさまざまな生活上の困難をかかえてききた人々(疾患、障害、暴力をふるわれた経験、貧困など)についてです。彼らが犯罪に至るまでのプロセス、刑務所中での処遇、社会復帰における課題などについて、さまざまな立場・専門の観点から議論することが、このシリーズの特徴になっています。タイトルは、UTCPの同僚のライラ・カセムさんの発案です。
私は司法や矯正の専門ではありませんが、こうした企画を構想したのは、摂食障害の調査をしていて、女子受刑者のなかに一定数、摂食障害を持つ人がいることを知ったという背景がありました。
私のインタビュー調査では、なかなかこの問題にアプローチしづらかったのですが、なんらかの方法で遷延化した摂食障害の人に窃盗が生じることがあることやその処遇について取り上げたいと思っていました。
——社会学のインタビュー調査では、なかなか届かなかった範囲ということですか?
そうです。私がインタビューした方々も、大変な苦しみや痛みをかかえていらした方、何十年と症状と付き合ってきた方がいらっしゃいました。しかし同時に、症状をかかえながらも、社会の中で生活を続け困難を乗り越えることができた方も多くいらっしゃいました。
他方、摂食障害が遷延化し、その過程で窃盗を行うようになり、それを繰り返し、受刑にまで至ってしまったという方にはお会いできませんでした。色々な考え方があると思いますが、私としてはこのような方にもアプローチしなければ摂食障害の全体像は見えてこないと考えています。そこで、博論以降に、刑務所に関する企画を実施することで、摂食障害を含めた精神疾患・さまざまな生きづらさと受刑との関係について検討をしております。
——本日はありがとうございました。
ありがとうございました!