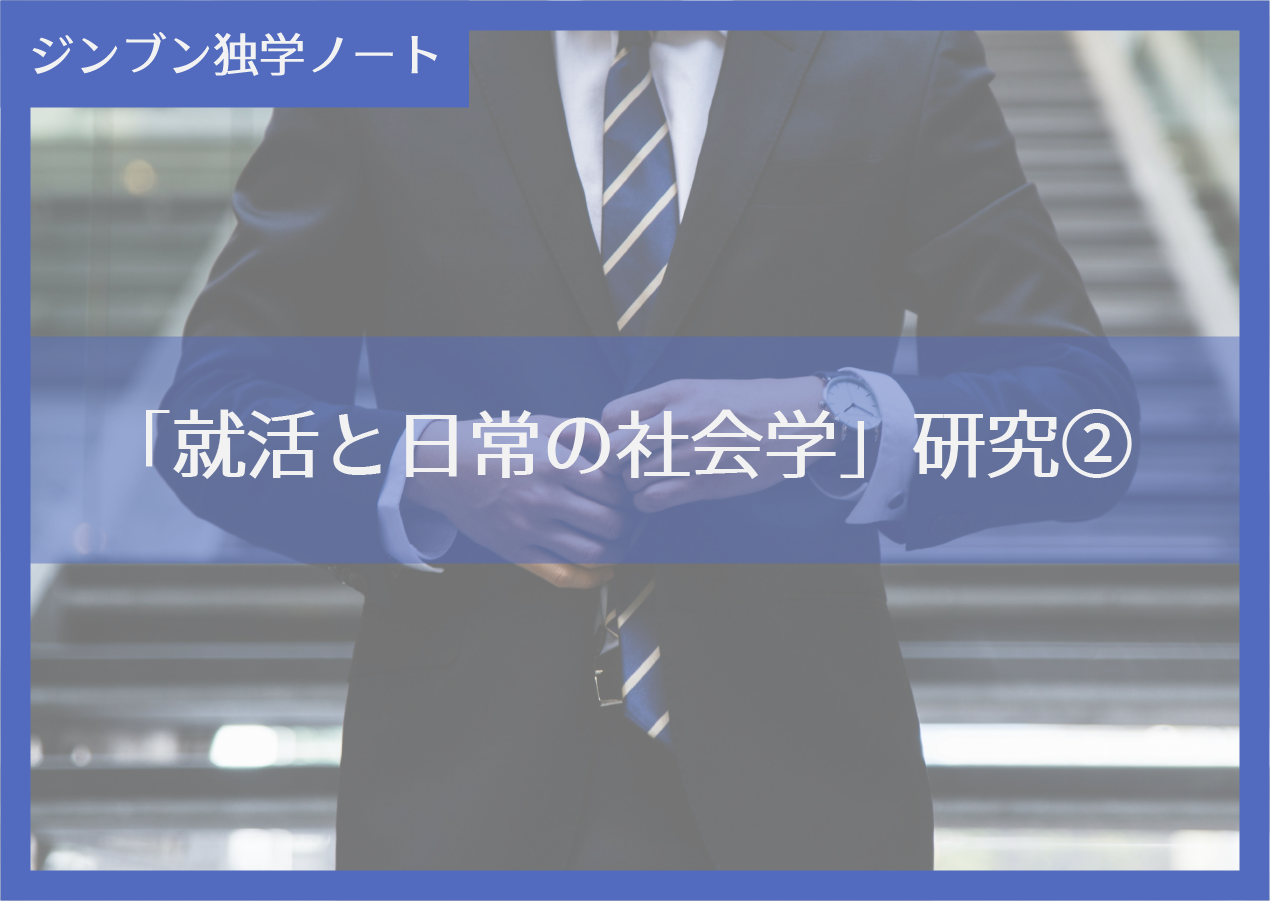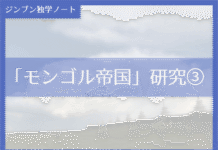ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第二十一回となる今回のインタビューでは、就職活動という日常に潜む「謎」を、社会学の視点から解き明かし、複雑な社会の新たな見取り図を描き出す、研究者の和藤仁さんにお話を伺います。
「ぬるっと」始まった研究人生
——社会学の持つ可能性についてよく分かりました。では、和藤さんご自身は、どのような経緯でこの道に進まれたのでしょうか。当初から社会学的なものへの関心は強かったのですか。
いえ、それが全くなかったんです。大学で社会学部に入ったのも、社会学がやりたくて選んだわけではありませんでした。
——そうなんですか。それは意外です。
高校時代、大学受験を考え始めたとき、数学がからきし駄目だったので、英語・国語・社会の三科目で受験できる大学・学部に絞りました。その上で、経済学部や商学部は避けたい。かといって法学部や文学部に強く惹かれるわけでもない。そうやって消去法で探していった先に、社会学部というよく分からない学部が残ったんです。「社会のことが学べる学部」という、何だかごちゃごちゃしたところが。
——面白い選び方ですね。まるで社会学の本質を体現しているような。
本当に、残ったものを選んだら、たまたま社会学だったというだけなんです。ですから、大学に入ってすぐに社会学に夢中になったわけでもありません。一、二年生の頃は授業も面白いと思ったことがなく、単位も落としまくっていました。大学前半の記憶があまりないくらい、彷徨っていましたね。
——そこから、何が転機になったのでしょうか。
大学三年生になるタイミングで、周りが就職活動を意識し始めたことが大きかったと思います。自分も就活をするべきかと考えたのですが、どうにも気が進まなかった。かといって、大学院進学という選択肢も、真面目に勉強してこなかったので成績はボロボロ。全く現実的ではありませんでした。
ただ、漠然と知的なものへの関心はあったんです。小学生の頃に世界の歴史マンガを読んだり、小説を読んだりするのが好きだったことを思い出しました。あとは大学に入ってからだと、大学院に進学するというゼミの先輩がブルデューのディスタンクシオン概念についてお話されていたのを聞いたことがありました。解説を聞いている中で、自分もなんとなく考えていたことをピシッと論じている人がいることに面白さを覚えたということもありました。そういうことを思い出す中で、「社会学、面白かったかもしれないな」とふと思ったんです。
——就職という現実から目をそらすために、面白かったと後付けで意味づけした可能性も?
それも、両方あったかもしれません。よく分からないのですが、とにかくその頃に「大学院」という選択肢が、本当にぬるっと自分の中に現れたんです。何か衝撃的な出会いがあったわけでもなく、ただ、そういう道も残されているらしい、と。
——不思議な温度感で、人生の大きな選択をされたのですね。
ちょうどそのタイミングでコロナ禍が始まったことも影響しているかもしれません。大学三年生になる直前の2020年1月頃にダイヤモンド・プリンセス号のことがあり、そこから学校に行けなくなって、家にこもる生活が始まりました。
元々、あまり深く考えずに「えいっ」と決めてしまう性格ではあるのですが、様々な要因が重なって、ぬるっと大学院進学の意思を固めていきました。そして、指導教員の先生に「大学院に行こうかと思っているんですけど」と、ほとんど何も勉強していない状態で相談しに行ったんです。
——勇気がありますね。
先生は「あ、そうなの。いいんじゃない」という感じで。ただ、大学院に行くなら研究計画を書かなければいけない。「じゃあ何をするか」と考えたとき、周りのみんながやっている「就活」がテーマとして浮かびました。自分の将来を考える上で、無視できない大きなイシューでしたから。
——他のテーマは候補になかったのですか?
不思議となかったかもしれません。本当に、後先考えずに、ふっと湧いてきたものにしっくりきて、そのまま進んでしまう。考えるのが下手なのか、放棄しているのか……。
——いえ、結果としてその選択を正解にしているところが、和藤さんのすごいところだと思います。降ってきたものを面白がるのが上手、というか。
ああ、その節はあるかもしれません。何事も、一度はまると面白いと思えるのは得意な方だと思います。高校時代にラーメン二郎にはまって10年以上通い続けていたり、ルービックキューブやけん玉に夢中になったり。今の僕にとって、それが研究や社会学なんだと思います。
——そうして大学院を目指し、就活を研究テーマに据えたわけですが、そこからは孤独な戦いが始まったのではないでしょうか。
そうですね。特にコロナ禍で大学にも行けず、周りに大学院を目指す友人も一人もいなかったので。ただ幸いだったのは、インターネットで社会学系の大学院を目指す学生のコミュニティを見つけられたことです。そこで、読むべき本や研究の進め方について教えてもらうことができました。授業をまともに受けてこなかったツケが回ってきて、ほとんど独学からのスタートでしたから、あの時の繋がりは本当に大きかったですね。
——まずは先行研究を読み込むところから始められたのですね。
はい。社会学で就活を研究するとはどういうことなのか、そもそも研究とは何なのか、何も分からなかったので、まずは関連する論文や書籍を片っ端から読んでいきました。卒業論文の執筆も同時に進めていたので、指導教員からも「大学院に進むなら、卒論の段階である程度調べておいた方が絶対にいい」とアドバイスをいただいていました。
——手探りの中で、膨大な文献を読み解いていくのは大変な作業だったと思います。その中で、ご自身の研究の方向性はどのように見出していったのでしょうか。
指導教員の影響が大きいのですが、私が当時から関心があったのは、日本社会がどうだ、といったマクロな問いよりも、私たちの日常に潜んでいる「謎」でした。普段、何気なく過ごしているけれど、よくよく考えてみると不思議なことってたくさんありますよね。
——ありますね。当たり前すぎて、誰も疑問に思わないようなことの中に。
そうした日常の裂け目のようなものを深く掘り下げていくと、その向こうに社会的なものが見えてくる。そうした社会学のスタイルに強く惹かれました。きっかけになった論文が一つあって、関西学院大学の奥村隆先生が書かれた「思いやりとかげぐちの体系としての社会 ー存在証明の形式社会学ー」という文章です。これは後に『他者といる技法 ーコミュニケーションの社会学ー』という本に収録されたものです。この論文のことは、先ほど話したコミュニティにいらっしゃった、奥村先生から手解きを受けた研究者の方に教えていただきました。
——「思いやり」と「かげぐち」。一見、正反対のものが並んでいますね。
この論文では、人間関係における「思いやり」と「陰口」が表裏一体であり、コミュニケーションを成立させる上で重要な役割を果たしていること、そしてそこから社会のありようが見えてくることを論じています。これを読んだとき、ゾクゾクしたんです。自分たちが生きているこの世界の、ちょっと見られたくない部分を暴かれるような感覚。陰口は本人の前で言うと成立しない。当人のいない場所で行われることで、当人も含めた関係性やコミュニケーションに対して初めて効力をなします。ある種、「思いやり」にも似たコミュニケーションや関係性への貢献を、奥村先生は「かげぐち」にも見出すのです。
——確かに。本人の前で言えば、それはただの罵倒になってしまう。関係性を壊さないための知恵とも言える。
はい。人間関係や共同体を維持するために、むしろ優しい方向に作用しているとも読める。このように、些細なことに注目することで、社会の見方ががらりと変わり、見通しが良くなる。そういう研究がしたいと思いました。
卒業論文で「就活生の進捗意識」というテーマを扱ったのも、その延長線上にあります。「就活、どれくらい進んだ?」とか、「あいつはすごく進んでるのに、自分は全然だ」といった会話は、就活生の間で本当によく交わされます。
——私も経験があります。インターンシップに何社行ったとか、エントリーシートを何枚書いたとか、そういう数で一喜一憂していました。
でも、本来の就職活動の目的は内定を獲得することのはずです。インターンにたくさん行った学生が必ずしも内定を得られるわけではない。もっと言えば、OB・OG訪問をしたこと自体は、内定と強い因果関係はありません。
——それなのに、なぜ学生たちは「進んだ」「進んでいない」というコミュニケーションを取るのでしょう。
そこに問いが生まれます。そのコミュニケーションが成立しているということは、彼らはそれによって何かを獲得しようとしているはずだ、と考えないと説明がつかない。では、彼らが語る「進捗」とは一体何なのか。その語りは彼らに何をもたらしているのか。インタビュー調査を通して、そうした日常の謎を解き明かそうとしたのが、私の研究の第一歩でした。
最後は彼の探究心の源泉について伺います。