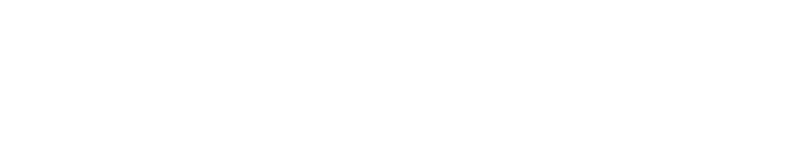ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三十一回となる今回のインタビューでは、アルベール・カミュの研究を専門とし、フランス各地の資料館を巡る「アウトドアな研究者」でもあるフランス文学者の渡辺惟央さんにお話を伺います。
「アウトドアな研究者」の原点とフランス文学への入口
——本日はお時間をいただきありがとうございます。武富さんから渡辺さんをご紹介いただいた際、「とてもアウトドアな研究者」だと伺いました。フランス文学の研究者というと、書斎にこもって文献を読み解くイメージがありますが、実際はどのようなスタイルで研究をされているのでしょうか。
確かに、文学研究というと、本と図書館さえあれば完結するようなイメージがあると思います。そのような研究も可能ですが、新たな資料を求めて資料館に足を運ぶことを主軸とする研究者もいます。私もそのタイプで、部屋にこもるというよりは、あちこちに出かけて考えるのが好きです。
私の研究対象は20世紀にノーベル文学賞を受賞したアルベール・カミュという作家です。研究の中心はもちろん、出版された作品なのですが、フランス各地の資料館を回って、その土地にいる人々と交流することも大事にしています。そのあたりが「アウトドアな研究者」なのだと思います。
——なるほど、ご自身でもそう感じられるのですね。
留学生としてフランスに8年間住んでいたのですが、ほとんどの時間を空の下で過ごしていた、と言えるかもしれません。少なくとも、図書館や学生寮にずっとこもっているタイプの学生ではありませんでした。
もともと家でじっと勉強するのが苦手な性分で、家にいるとつい寝るか、映画を観てしまう。だから、仕事をする時は必ず人の目がある場所に行くんです。カフェ、公園のベンチ、図書館。いつも家の外で作業をしています。
それから私には、素晴らしい論文やエッセイ、本に出会うと、その著者になるべく会いに行く、というモットーがあります。フランスにいた頃は、気になった人の講演会やイベントに行くだけでなく、共通の知人を通じて紹介してもらい、個人的に会いに行くことにも積極的にトライしていました。
——素晴らしい本を読んだら著者に会いに行く、というのはすごい行動力ですね。しかも、相手はフランスにいらっしゃるわけで。
それが、フランスの面白いところでもあるんです。パリはとてもコンパクトな街で、さまざまな出会いがあります。ある時、私が研究している作家のお墓を見に行くと、ちょうどご遺族がいらしていて。話しかけると、そこからさまざまなお話を聞かせてもらうことができ、その後も連絡を取り合う関係になりました。
フランスの特徴として、他人とコミュニケーションを取ることが当然だと考える文化があります。だから、赤の他人でも、誠意と熱意を持って話しかけると、どんどん新たな関係が築けていくんです。研究に役立つ新たな資料も、そういった意外なところから出会えたりする。それが本当に楽しくて。
気がつけば、現地を歩き回ってキョロキョロしているような研究者になっていましたね。
——そのフットワークの軽さや、人と関わることへの積極性は、学生時代からなのでしょうか。
昔から、基本的には内向的な人間だったと思います。本や漫画、映画が好きな子供で、小説を書いたりしていました。人並みに外で遊んで、スポーツをして、中学・高校時代にはバンド活動もしていましたが、非常に社交的かというとそうではなかった。
それでも、人一倍好奇心が強かったことが、人と会おうとする原動力になっていたと思います。「知らないこと」が気になるので、それについて詳しい人に会いに行こう、と。本や芸術作品だけでなく、外に出かけて人と出会い、そこから広がる新たな世界を知る喜びも大きかった。
中学・高校時代は、フランス文学に親しんでいたわけではありませんでした。将来専門にしようとは全く考えておらず、もともと大学では社会学か、あるいは人類学を学びたいと思っていたんです。
——文学ではなく、社会学や人類学ですか。
先ほど「本が好きな子供」と言ったのと矛盾するかもしれませんが、実は長い小説や古典文学を読むのが苦手で、それが文学に対するコンプレックスになっていました。日頃読んでいたのはSF小説やミステリー小説で、いわゆる純文学ではなかった。小説以外だと、現実の世界と直接結びついていると感じられる、社会学者が書いた本やエッセイを読むのが好きでした。
——研究者という職業は、その頃から意識されていたのですか?
親族に研究者がいるので、職業の選択肢としては自然と意識しやすかったと思います。ただ、もし研究者になるなら、自分が本当に納得できる、自分だけのテーマを見つけなければ意味がないと思っていました。それが見つからなければ、就職しようと思っていた。だからこそ、まずは調査対象となるフィールドを探すことから始めたんです。
——なるほど。研究者という選択肢は身近にありつつも、ご自身のテーマを探す旅が始まったわけですね。
研究者の他にも、本に関わることができ、人とも出会えるので、出版社で編集者になるという道も考えていました。研究者か、編集者か。その二つの選択肢でギリギリまで迷っていましたね。
——そこから、どのようにしてフランス文学の道へ進まれたのでしょうか。
大学は慶應義塾大学の文学部に入学しました。1年生の時点では専攻を決めず、2年生に進級する時に成績と希望に応じて各専攻に振り分けられるシステムでした。だから、1年生の間に自分のフィールドを探そうと、あちこち旅をしたり、いろいろな言語を学んだりしました。
——その頃から、すでに語学にも力を入れていたのですね。
当時は、トルコ語やアラビア語を勉強していました。自分の世界とは全く違う文化に触れたいという気持ちが強くて、中東〜アフリカ地域に興味があったんです。でも、これが難しすぎて……。
そこで、まずはヨーロッパの言語、特に社会学や人類学のルーツに近いフランス語を学んでおいて損はないだろう、と考え直しました。そして、どうせ学ぶなら一番集中的に学べる環境に身を置こうと、フランス文学専攻に進むことにしたんです。
——あくまでも語学を学ぶため、というのが出発点だったのですね。
今思えば、古典文学に対するコンプレックスがあったからこそ、フランス文学を学ぶことに憧れを感じていた面もあったと思います。とはいえまだ、文学を専門にすることは考えていませんでした。まだヨーロッパに旅行したこともありませんでした。
次回はカミュ研究の「発見」について伺います