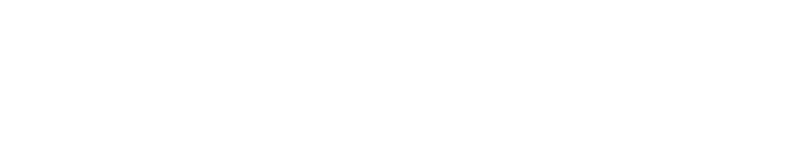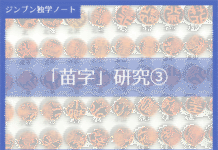ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三十八回となる今回のインタビューでは、奈良市教育委員会で発掘調査の最前線に立ちながら、測量技術やデジタル機器を駆使して古墳時代の社会構造解明に取り組む考古学者、柴原聡一郎さんにお話を伺います。
「手段としての古墳」とブルーオーシャン戦略:モノの研究から社会システムの解明へ
——大学では教養学部で様々な分野に触れられたと思いますが、考古学以外に心が揺らいだ分野はありましたか?
文化人類学や天文学の講義も面白かったですね。ただ、天文学は望遠鏡で覗くことはできても、現地には行けません。文化人類学も魅力的でしたが、ある先生のエピソードを聞いて諦めました。
海外の過酷なフィールドでの感染症や文化の違いに翻弄された話を聞いて、「すごい世界だけれど、自分にはそこまでのバイタリティはないな」と(笑)。
その点、考古学、特に日本の古墳であれば、国内ですし、自分の足で現地に行けますから。
——ところで柴原さん、つかぬことをうかがうようですが……ここまでのお話の中で、まだ柴原さんは古墳のことがそんなに好きそうではないですよね?
いや、実はその通りなんです。私が「古墳そのもの」を愛して研究しているかというと、そうでもない。
そういえば、以前も似たシチュエーションがあったな、と思い出しました。
——本当ですか。詳しく聞きたいです。
NHKのラジオ番組に出演したときのことです。アナウンサーの方から、「柴原さん、もしタイムマシンがあったら古墳時代に行きたいですか?」と聞かれたんです。私は即答しました。「絶対に行きたくないです」と。
——即答ですか(笑)。それはなぜでしょう。
私は現代の都市文明にどっぷり浸かっていますから、下水道が完備されていない場所では暮らせません(笑)。
というのは冗談半分ですが、本質的な話をすると、私は「古墳」という物体そのものへの愛着よりも、古墳という「手段」を通じて、過去の社会構造や人間の普遍的な営みを明らかにすることに興味があるんです。
——「手段としての古墳」ですか。柴原さんらしい視点な気がしますね。
考古学者の多くは、やはり対象への愛が深いです。土器の文様ひとつ、鏡の縁の形ひとつに魅せられ、それを極める。それは素晴らしいことですし、学問の基礎です。
ですが、私はもう少し引いた視点というか、それらのモノを作った人々が、どのような意図で社会を組織し、現代につながる社会の礎石を築いたのか、というシステムや構造の部分に関心があるんです。
ですから、極論を言えば研究対象は古墳でなくても良かった。たまたま自分が「測量」という武器を持っていて、当時の社会を解析するのに古墳という対象が適していた。そういう巡り合わせだったのだと思います。
——数ある時代の中で、縄文や弥生ではなく、あえて古墳時代を選んだ理由もそこにあるのでしょうか。
正直に言えば、戦略的な理由もあります。「ブルーオーシャン」だったんです。
縄文時代や弥生時代は、狩猟採集社会から農耕社会への移行や、集落の形成など、社会構造に関する研究の蓄積が非常に分厚い。私がやりたいような「社会システムの研究」は、すでに偉大な先人たちがやり尽くしている感がありました。
一方で、古墳時代はモノ(出土品)の種類が爆発的に増える時代です。埴輪、鏡、武具、装身具……。あまりにモノが多すぎるため、どうしても研究が「モノの分類や編年(作られた順序を決めること)」に集中しがちでした。
「鏡の研究」などはその典型ですね。たとえば鏡の裏側の模様については、極めて精緻な分類が行われています。その分野の先生方の知識や分析術といったら、もう神業といっていいようなレベル。一方で、一歩引いて「じゃあ、その鏡を持っていた人たちはどんな集団で、どんな社会を作っていたの?」という議論になると、まだ開拓の余地があると感じたんです。
——モノの研究にリソースが割かれていた分、社会構造の研究には入り込む隙間があったと。
はい、少し不純な動機かもしれませんが(笑)。
最後は具体的な研究プロセスについて伺います。