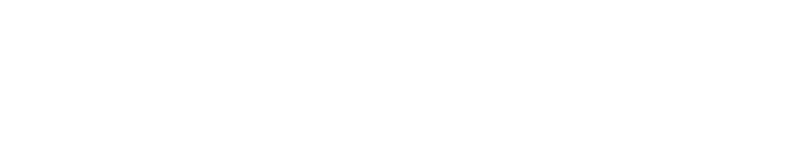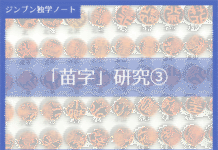ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第二十三回となる今回のインタビューでは、哲学と文学の境界を越境し、ハイデガーの根源的な「問い」と石牟礼道子の切実な「言葉」とを往還することで、現代における思索の新たな地平を切り拓く、研究者の宮田晃碩さんにお話を伺います。
探求の萌芽:俳句と哲学に惹かれた日々
——本日はよろしくお願いします。宮田さんのご研究は哲学、言語、文学と非常に多岐にわたりますが、まずはその出発点からお伺いできればと思います。現在の研究テーマに至るまで、どのような歩みがあったのでしょうか。
よろしくお願いします。そうですね、話はあちこちに飛んでしまうかもしれませんが、思いつく順にお話しさせてください。
——もちろんです。中高生の頃から、現在の研究分野に関心があったのでしょうか。
いえ、実は大学に入るまでは理系志望でした。もともと本を読むのは好きで、小学校の頃から児童小説などはよく読んでいました。ただ、学問として専門的に取り組むなら、実験など大学の研究室でしかできない生物系の分野かな、と考えていたんです。哲学や文学は、極端な話、趣味でもできるというイメージがありました。
——理系へのご関心が強かったのですね。
ええ。ダーウィンが来た!のような動物番組が大好きでしたから。ただ、そんな理系志望の私でしたが、言葉との関わりも中高時代からありました。俳句甲子園に出場した経験があるんです。
——俳句甲子園、ですか。それはまた意外なご経歴です。
高校1年と2年の時に出場しました。これも主体的に始めたというよりは、友人に誘われたのがきっかけで。中学1年生の時から天文気象部で一緒だった三村一貴くんという友人が、当時から漢文を白文で読みこなし、書道も嗜むような、少し変わった才能のある男でして。
——周りに面白いご友人がいらっしゃったのですね。
彼に「とりあえず来てみなよ」と俳句部の部室である和室に連れて行かれ、よく分からないまま句会に参加させられました。その日の終わりには、顧問の先生と握手して「じゃあ次回もよろしくね」と。気づいたら入部していました(笑)。昔から、そうやって面白いことに巻き込まれることが多いんです。
——そのご友人の慧眼だったのかもしれませんね。
そうかもしれません。結局、高校を卒業してからもOBとして部活に関わったり、句会に参加させてもらったりと、俳句との縁は続いています。
——俳句の魅力は、どのような点にあると思われますか。十七音という短い定型詩ですが。
そうですね。短いからこそ助詞ひとつにもこだわって、描き出されるものを吟味するところに魅力を感じます。十七音しかないから、AIを使えば全ての組み合わせを網羅できてしまうのではないか、とさえ思えますが、決してそんなことはない。まだまだ新しい表現の可能性があると思います。
それに、俳句甲子園は句を作るだけでなく、チームで相手の句を批評し、ディベートを行う形式です。良い句を生み出すために、事前に発表される兼題に沿って、夏合宿では一日百句作ることもありました。
——一日百句、ですか。それは壮絶ですね。
運動部のような猛練習でした。自分で作るだけでなく、他の人の句を読み、選び、推敲する。その過程で、この句の眼目、つまり作者が提示したい「景」は何だろうかと深く読み解く力が鍛えられます。批評家としての視点を持つことが、作り手としても必要になる。言葉にじっくり向き合うとはこういうことなのか、という体感を得られました。
——理系への関心と、言葉への探究心。その二つが並行して存在していたのですね。
そうですね。哲学にも、なんとなく興味はありました。ただ、哲学書を本格的に読んだわけではありません。中学の卒業文集に「自分が見ているこの世界は実在するのか、それとも自分が見ているだけなのか」といった問いを書いたり、高校の卒業文集では「言葉の意味とは何だろう」と考えを巡らせたり。哲学少年、と言えるほどのものではありませんが、根源的な問いへの関心は昔から持っていたようです。
高校時代に大きかったのは、先ほどの俳句部の友人と、今バレエダンサーとして活躍している鷲見 雄馬くんという、これまた個性的な友人と一緒に雑誌を作っていたことです。
——高校時代にご自身で雑誌を?
ええ。「自分たちの言葉で表現しよう」をモットーに、数年上の先輩が出していた『論説集』という冊子に倣って、『続論説集』と名付けた雑誌を制作していました。そこで私は、自分の考えた哲学的な文章を書いていました。学問的な裏付けがあるわけではなく、ただ自分が面白いと思ったことを書き連ねるだけでしたが、自分で考えて書く、という行為の楽しさを知った原体験だったと思います。
次回はハイデガーとの出会いについて伺います。