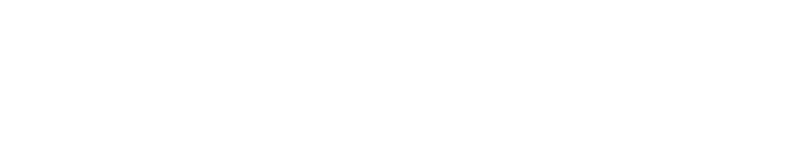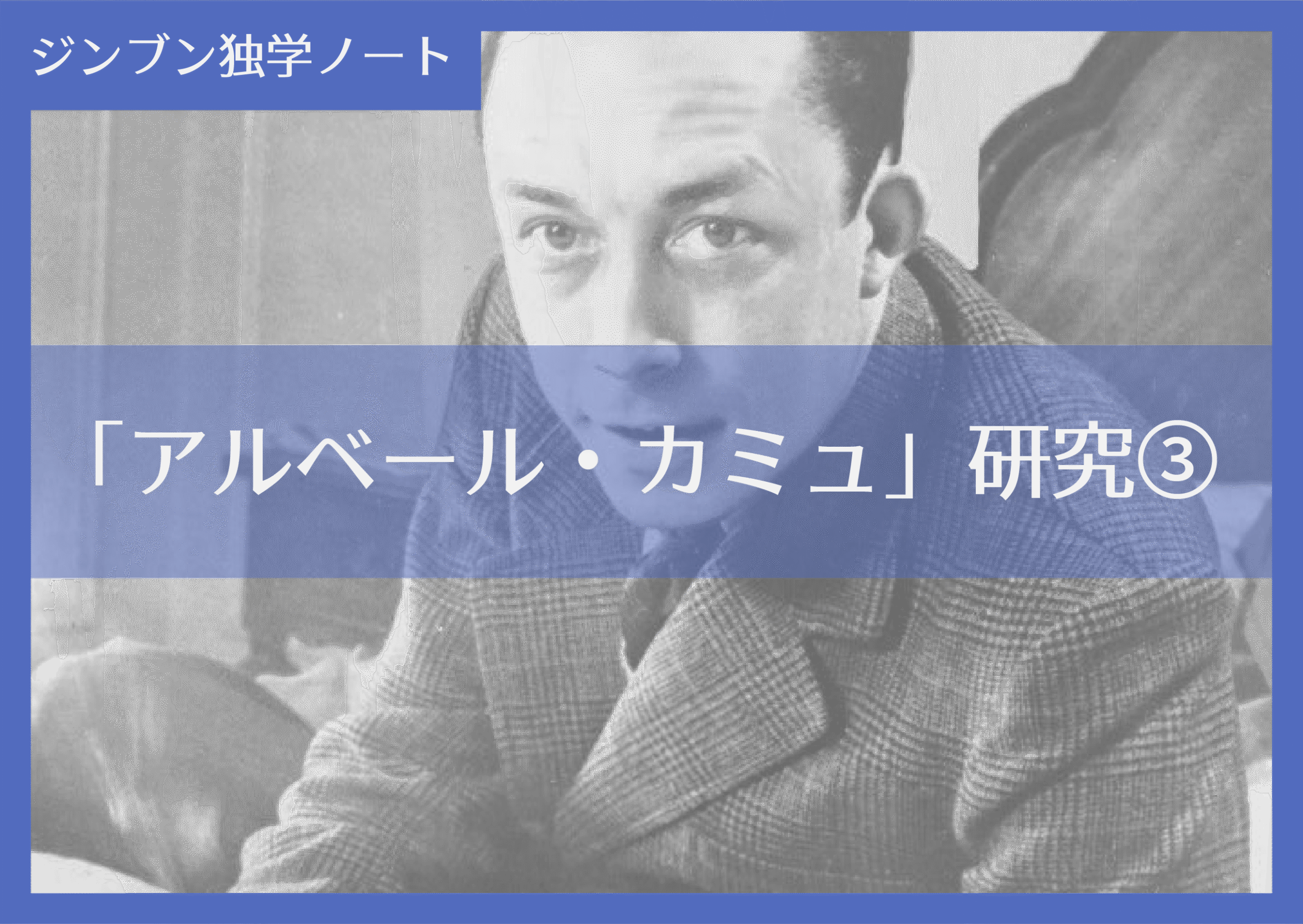ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十五回となる今回のインタビューでは、ペルシア語史料の読解を軸にモンゴル帝国史を研究し、天文学や気候学など分野を越境した学際的なアプローチで注目される歴史学者の諫早庸一先生にお話を伺います。
研究の面白さと、自分だけの武器を見つけるまで
—— なんたる恐怖体験……! そんな絶望的な状況から、どうやって食らいついていったのでしょうか。
でも、神戸大学の東洋史に入って本当にラッキーだったのは、研究室がものすごくアットホームだったことです。先輩たちが「お前は本当に何もできないな~」とか言いながらも、徹夜で辞書を引きながら予習に付き合ってくれました。その温かい雰囲気のおかげで、私も必死に食らいつき、いつしか研究にのめり込んでいきました。
—— 素晴らしい環境だったのですね。その頃から研究者になろうと?
いえ、全く考えていませんでした。就職活動も普通にして、ある大手生命保険会社から内定もいただきました。研究は面白かったけど、就職するものだと思っていたんです。
転機が訪れたのは、卒業論文の執筆中です。就職が決まった後、卒論のために初めて本格的にペルシア語の史料を読みました。その中に、チンギス・ハンの名前が出てきたとき、電撃的な感動に襲われたのです。「歴史上の人物が、この史料に出てきた!」って。13世紀に書かれた文章を通じて、当時の人間と対話しているような感覚。これはすごいことだ、面白い、と思ってしまったんです。
—— そこで研究の面白さに目覚めてしまった。
はい。それで、本当に申し訳なかったのですが、内定をいただいた企業にお断りを入れました。それに、私の父は大学でロシア文学を教える研究者だったのですが、母が研究の世界の厳しさを知っているだけに大反対でした。「あなたには父親のような才能は一切ない。この世界は九割が屍になる世界だから、やれるわけがない」と。でも、息子が母親にそんなこと言われたら、逆に燃えちゃいますよね?
—— 確かに(笑)。それで大学院に進学されたのですね。
ええ。神戸大学の修士課程に進み、本当に楽しかったです。でも、博士課程に進学した1年目の時、ふと「この研究に、自分の人生を賭けられるのかな?」と正気に戻ってしまったんです。どうしようかと迷っていた時、のちに私の指導教員となる羽田正先生(東京大学)が書かれた『イスラーム世界の創造』という本に出会いました。ご自身の専門分野である「イスラーム世界」という概念そのものを問い直す、非常に衝撃的で魅力的な議論に心を揺さぶられ、「この先生の話を聞きに行きたい」と。
—— また新たな出会いがあったのですね。
羽田先生のゼミは、私の専門とは全く違う分野の人たちと議論を交わすような、非常に学際的な場でした。最初は「ついていけない」と思ったのですが、じわじわとその魅力に気づき、結局、神戸大の博士課程を中退して東大の大学院の試験を受け直しました。
そこから、地域の専門家を育てるという方針のもと、イランに留学することになりました。受け入れ先を探していた時、国際学会でたまたまバスで隣に座ったのが、イラン人の科学史の先生でした。「暦の研究をしています」と言ったら話が合い、そのご縁でテヘラン大学の科学史研究所に留学できることになったのです。
—— ここでもまたすごい偶然が。
ただ、そこは物理や数学を学んだ理系の学生たちが、歴史に興味を持って集まるような場所でした。彼らはペルシア語がネイティブな上、科学文献で使われるアラビア語も息をするように読んでいく。私は語学力では到底彼らに敵わない。「この人たちに勝てるのか?」と絶望しました。
その時、ふと思ったんです。彼らが読んでいるモンゴル帝国時代の天文学の文献には、時々、中国の暦に関する記述が出てくる。この中国暦の部分は、いくらペルシア語やアラビア語ができても、東アジアの暦の知識がないと読めない。となると、「これは僕しか読めないんじゃないか?」と。
—— なるほど!これまでの全ての経験が繋がった瞬間ですね。
そうです。ペルシア語がある程度読めて、イスラム科学の知識も多少あり、かつ東アジアの歴史・文化の素養がある人間。それは、ある意味で唯一無二の存在になれるかもしれない、と。そこから「ペルシア語で書かれた中国の暦」を本格的に読んでいこう、と決めました。それが私の博士論文のテーマになりました。
最終回は分野を越境し「環境史」に至るまでついて伺います。