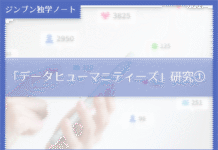──でも多くの人文系研究者は、そこまで踏み込まずに来たわけですね。
そうですね。大学の中だけで「哲学は役に立たないからこそ価値がある」なんて言っていると、気づいたときにはその大学の哲学科自体が縮小されていたりして。本当は哲学を面白いと思う人が、企業や社会のなかにも一定数いる。にもかかわらず、その架け橋が不在だったのが今までの状況です。なので、僕としては「むしろそこにこそ大きな可能性がある」と考えています。
──具体的には、どんな形で企業と関わっているんでしょうか。
たとえばカメラを作っている企業では、自然科学系の大学院を出た方は多くても、写真論や哲学的な視点には触れていない人がほとんど。でも、そこに哲学が入り込めば、研究開発自体をアップデートできる可能性がある。逆に、現場の人が実際に世界でモノを売っていて、ユーザーの声を聞いている実態を、哲学者側は知らないことが多いわけです。そうしたギャップを埋めると、アカデミアも変わるし、現場のイノベーションも深まります。
──まさに理系と文系、研究と実践の垣根を耕している感じがしますね。
ええ。自分でも意外ですが、ここに来て「新規事業に参加する哲学者」になるとは思っていなかった。でも、「民間に就職したくないから研究者を選ぶ」という消極的な理由だけでは、こうした動きには結びつかなかったと思います。最終的には「自分が積極的にやりたいかどうか」が残る。それだけのことですが、結果として非常に面白い場所に行き着きました。
──今まさにそういうプロジェクトの真っ最中なんですね。
そうなんです。だからこそ、これから高校生や大学生、人文系の研究室にいる人たちに伝えたいのは「こんな選択肢もある」ということ。たとえばカメラの開発に写真論の視点を持ち込んだり、哲学対話の方法を組織変革に活用したり。実際にそういう道筋はできつつあります。要は「哲学をやっている人も、たくさんの場所で必要とされる時代が来ている」と知ってほしいんです。
──今日は本当にいろいろなお話を聞かせていただきありがとうございました。企業の新規事業に哲学者が入り込んでいるというのは、正直とても新鮮でしたし、「実際にこういうキャリアがあり得るんだ」と思うと、迷っている人たちの大きな希望にもなると思います。では最後に、今まさに哲学や人文系の学問を学ぼうか迷っている方へ、一言メッセージをお願いします。
そうですね……「哲学は何の役に立つの?」ってよく言われますけど、実はそういうことを問い直すのがまさに哲学の本領なんですよね(笑)。今の時代、企業でも学校でも「そもそも何のためにやっているのか」を考える場面が増えていますし、それを自由に掘り下げられるのが哲学の面白さだと思います。だから、興味を持ったらぜひその気持ちを大事にして、「自分が面白い」と思うことをとことん追いかけてほしいですね。想像もしなかった形で、学んできたことが活きてくると感じています。