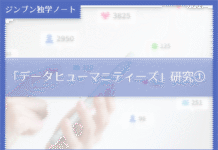——そこから、大学ではどんなふうに学びを深めていったんですか?
まずは哲学科の環境にどっぷり浸かりましたね。研究会や自主ゼミに入り浸って、同じ志を持つ人たちと議論するのが本当に楽しかったんです。中高時代にたまっていた鬱屈を一気に解放できた感じもありました。
——上智は中世哲学、特に形而上学に強い印象がありますが、その伝統に疑問を持つことはなかったのでしょうか。
もちろん、中世哲学や神学的テーマを深く掘り下げる人もいたんですけど、僕自身は途中から「もっと現実的な問題も哲学的に考えたい」という気持ちが芽生えました。大学の授業で政治哲学や社会哲学に触れる機会があり、その非常勤で来られていた先生(お名前は伏せますが)の影響でプラグマティズムの哲学者であるデューイを知ったんです。形而上学とは全然違う「哲学が経験を豊かにする」という視点に衝撃を受けて、「これも哲学なんだ!」と目が開かれる思いでした。
——中世の形而上学とはかなり離れた世界ですね。
そうなんです。だから大学院に進む道を考えたときも、「上智でそのまま伝統的な思想史や文献学的な研究を深めるか、もっとほかの大学で現実社会との接点が大きい哲学や応用を見越した理論研究を学ぶか」で迷いました。結果的には場所を変える選択をしてみることにしたんですね。
——大学在学中に休学もされたとか。
はい。今でいうギャップイヤーみたいなもので、一年間「積極的休学」をとりました。単位はほぼ修得していたので、その期間を使ってほかの大学の授業に参加してみたり、研究会に出てみたり、いろいろな本を読んだり。とにかく外の空気を吸いたかったんです。上智の環境は素晴らしかったけれど、そこにずっといると視野が狭くなるかもしれないと思って。
——いろいろな学問領域をつまみ食いしてみたわけですね。
ええ。政治系のゼミにも顔を出したりして、周囲には「変わった人だな」と思われたかもしれません(笑)。でも、哲学って本来そういう自由なものでいいんじゃないかと感じたんですよ。自分自身も、将来は研究者を目指すのか、別の道に進むのか、はっきりとはわかっていなかったし、とにかく「いま興味があることを探求したい」という気持ちが強かったですね。
——そういう自由な活動があってこそ、視野を広げられたんでしょうね。
おかげで「学びほぐす」みたいな作業ができたと思います。大学四年から五年生くらいのときが、一番自由に使える時間でした。単位はほぼ取り終えていたので、卒論を書くことも焦りすぎずにできたし、自分の中の固定観念が崩れる瞬間を楽しめた。やっぱり大学だからこそ味わえる特権ですよね。
——そうして卒業論文を書いて、いよいよ進路選択を迫られたわけですね。
はい。いざ「研究者としてやっていくか?」となると、伝統的な研究スタイルに染まるのはどうなのかな……という迷いが出てきて。「自分が本当にやりたいのは何だろう」と自問するようになりました。正直に言うと、「哲学研究の面白さがどこにあるのか、いまいちピンと来ない部分があるな」とも思っていたんですよ。
——研究って、どうしても訓練的な面が強いですからね。
そうなんです。論文のフォーマットや先行研究の検討手法といった“お作法”を学ぶことが研究の基本になるので、それが楽しいという人はもちろんいるでしょう。けれど、僕はもっと「自分の興味」や「社会と結びつくこと」を重視したい気持ちが強くて。大学院に進むにしても、どこでどういうアプローチができるかを考えながら、場所を選んでいきました。
——そのあたりの思考が、やがて「企業における哲学的思考と対話の実践」というテーマにもつながっていくんですね。
ええ。結果的に、哲学をどう社会に役立てるのか、それを実際の組織のなかでどのように取り入れていくのか、という課題意識が芽生えました。そこにプラグマティズム的な視点も活きてくるわけですし、大学での基礎的な学びや自由な探究がすべてつながっている気がします。
次回は今につながる哲学対話の活動について伺います。