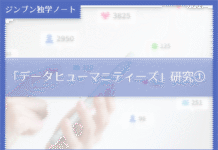ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十一回となる今回のインタビューでは、堀越耀介先生にお話をうかがいます。堀越先生は東京大学共生のための国際哲学研究センター(UTCP)特任研究員として、学校や企業など様々な場で哲学対話の実践と研究を行っています。
大学入学後の出会い
——最初から上智大学の哲学科を志望していたんですか?
はい。もう上智大学の哲学科一本でした。早稲田や慶應なども考えず、とにかく上智大学に行きたかったんです。先生方の専門分野や、どのような哲学教育を行っているかなども、事前にかなり調べました。
当時の上智大学の哲学科の説明を読むと、
「哲学を学ぶことで、言葉を洗練させ、的確に表現する力を養う」
というようなことが書いてあって、研究者養成の側面も当然あるわけですが、「考える力を育むための哲学教育」を掲げていたんですよ。それに強く惹かれました。
——なるほど。本質的ですね。
そうなんです。ただ、一方で上智大学は中世哲学の研究が非常に盛んで、そこはある意味ニッチな領域でもありますよね。デカルトやカントといった近世・近代の哲学者のほうが人気が高い印象なのに、上智は神学的な問題に重きを置く伝統もあります。でも実際には、一般的なスキル(言語力や論理的な思考力)を身につける場でもあったので、そこが独特だなと思いました。高校生のときにオープンキャンパスに参加して、その雰囲気を実感しました。
——高校生の段階で直接足を運んだのは大きいですね。
はい。大講堂で文学部全体の説明会があり、英文学科、仏文学科、新聞学科などが順番に紹介されていって、最後に哲学科だったんです。ほかの学科は割と高校生にも「面白そう!」と興味を持たれていましたが、哲学科の番になると、どんどん席を立って帰っていく人が多くて(笑)。
でも、登壇した当時の学科長が最初に「お帰りになりたい方はどうぞ。無理に残らなくても大丈夫です。哲学科はこれまで哲学的なことを考えたくても考える環境がなかった人たちのための場です」とさらっと言って。そこで、「ここは自分がずっと求めていた環境かもしれない」と直感したんですよ。
——自分に向かって語りかけられているような感覚だったんですね。
まさにそうです。ここしかないと思いました。学費は確かに高いですが、僕にとってはそれに見合うだけの価値がある大学でした。教員の専門性や学生との関わり方も含めて、自分の性格や興味に合っていたので、「この大学しかない」と確信しました。
——そういうフィット感は大切ですね。パンフレットではわからない部分もあるので、実際に足を運ぶのは大事だと思います。
そうなんです。直感的に「ここは違うな」という場合もありますし、「ここだ!」とハッキリわかる場合もある。大学で学ぶのは、本を読むだけじゃなくて、同じ関心を持つ仲間との出会いや、教員との対話も大きいですから。