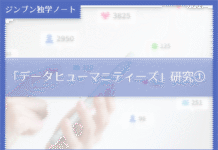ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十一回となる今回のインタビューでは、堀越耀介先生にお話をうかがいます。堀越先生は東京大学共生のための国際哲学研究センター(UTCP)特任研究員として、学校や企業など様々な場で哲学対話の実践と研究を行っています。
これまでの歩み
──本日はどうぞよろしくお願いします。いま取り組んでいるテーマを一言で表すとなんでしょうか?
「企業における哲学的思考と対話の実践」を軸にしています。ビジネスの現場で哲学がどんなふうに活かせるのか、その可能性を探っているんです。社会全体というよりは、まず組織としての企業に焦点を当てています。
──そのテーマに至るまでの道のりを、今日はじっくりうかがいたいですね。
もちろん。最初から一直線というわけではなかったので、お話しできることはいろいろあります。
──そもそも、哲学への興味は子どもの頃からですか?
そうです。小学生のころから、「なぜ人は生きているのか」とか「宇宙の始まりはどうなっているのか」といった問いに自然と惹かれていました。昔の哲学者の中にも、自然科学と哲学を行き来する人が多かったように、僕も単に好奇心が強かっただけなんだと思いますが、とにかく「人間の存在理由」みたいなものに興味を持っていたんです。中学生になると『14歳からの哲学』のような入門書を読みはじめ、「あ、自分が探していたのは“哲学”っていうんだ」と気づきました。
──そういった話は、周りの友人とはしにくかったのではないですか。
まったく話せなかったですね。学校の話題はテレビの番組やゲームのことばかりで、人生とか存在とかの話をすれば浮いてしまう。だから、本のなかに答えを求めていました。最初に哲学の本を読んだときは、同じようなことを考えている大人がいるんだと驚きましたね。家でも自分の部屋にこもって読んでいたし、図書館で母が借りてきてくれた本―さきほど話をした『14歳からの哲学』―が、今思うと大きなきっかけでした。
──中学・高校でも同じような仲間は見つからなかったのでしょうか?
そうですね、同志のような人は周りにいませんでした。高校に進学しても似たような状況は続いて、学校生活もあまり楽しいとは感じられませんでしたね。中学生の頃にはもう「哲学をちゃんと学びたい」という気持ちがあったので、周りと深い話ができないもどかしさもあって、今思うと「時間を無駄にしていたな」と感じるほどです。そんな中で大学受験が近づいてきて、『大学では本格的に哲学を学ぼう』と(哲学科への進学を)決意したときに、ようやく道が開けたような気がして、希望を見いだせたんです。