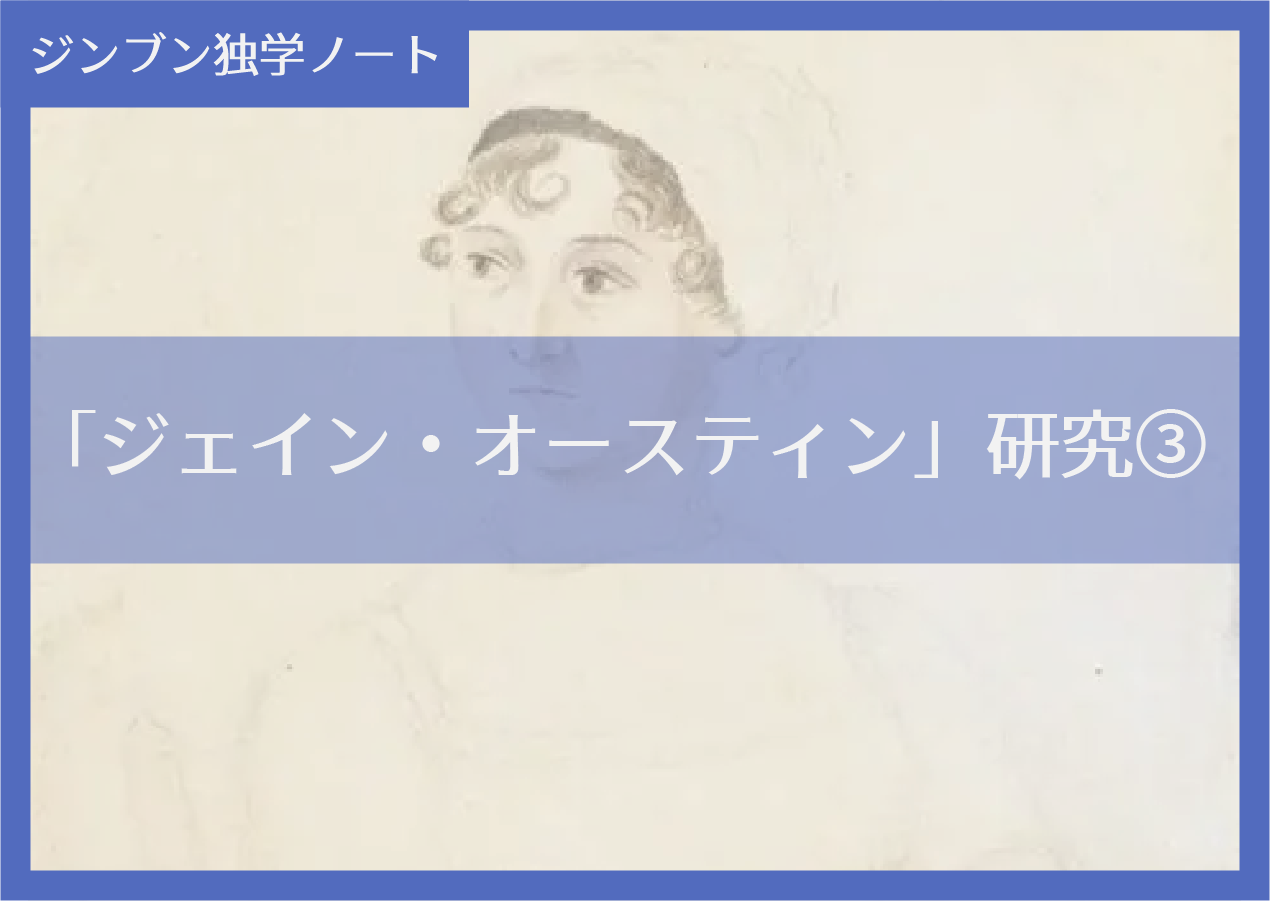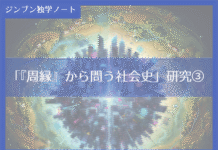ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十九回となる今回のインタビューでは、歴史が「何を」語るかではなく「いかに」語られるかという視点から、ジェイン・オースティンの作品を読み解き、文学の新たな価値と可能性を切り拓く、英文学研究者の広本優佳さんにお話を伺います。
導かれるように研究の道へ
——現在は、研究者としてだけでなく、東京科学大学で教壇にも立たれています。理系の学生たちに、ご専門である英文学やリベラルアーツを教えるなかで、感じることなどありますか。
彼らに英語を教えていて感じるのは、多くの学生にとって、英語がまだ「目的」になってしまっている、ということです。受験英語の影響で、「英語力を上げるために英語を勉強する」という意識が強い。でも、本来、言語は何かを学んだり、行動を起こしたりするための「手段」でもあります。
——英語を使って、何がしたいのか、という目的を見つける手伝いをしたい、と。
はい。だから授業では、自分の留学経験を雑談として話したり、映画の映像を見せたりして、「英語が使えると、こんなに広大な世界が待っているんだ」というワクワク感を伝えようとしています。ただ、そこにはジレンマもあって。
——と、言いますと?
大学で英語を教えるという立場上、私が、グローバル化を推進するために、世界共通語としての英語を押し付けているように見られてしまうことがある気がします。先ほどお話ししたように、私はむしろ、個別の言語や文化の固有性に惹かれて研究をしているので、そういった思想を相対化する立場のはずなのですが。自分がたまたま英語を研究で使っているがゆえに、意図せず言語帝国主義の側に勝手に動員されてしまっているような感覚を覚えることがあります。
——もう一つのジレンマとして、小説という「原作」を読んでもらうことの難しさも挙げられていました。
ええ。授業でオースティンの原文を少し読んだあと、その映画化作品を見せることがあります。そうすると、学生たちは、映画版に強い興味を示すことが多いと思います。活字より、映像のほうがすぐに理解できますから。オースティンを紹介しようとするあまり、肝心の小説から学生を遠ざけてしまっているのではないか、と。小説を裏切り、映画に魂を売ってしまったかのような気持ちになることもありますね(笑)。映画という媒体は、それはそれとして大好きですが。
——原作に触れることの価値を、どう伝えていくか。
とても難しい課題です。ただ、学生たちがフィクションに興味がないわけではないと思います。アニメや漫画を愛する学生は多いですし、原作と映像化の違いといった「翻案」という現象自体にも、強い関心を示してくれます。専門分野は違えど、何かを「好き」という気持ちにおいては、文学研究者と何も変わらないと思います。その興味の入り口から、どうやってテクストを読む喜びにたどり着いてもらえるか。今はその方法を、毎年、学生たちに教えられながら模索しているところです。自分の研究を専門外の人に分かりやすく伝える、という練習の場にもなっていて、非常に得難い経験のできる環境だと感じています。
——本日は興味深い話をありがとうございました!
ありがとうございました!