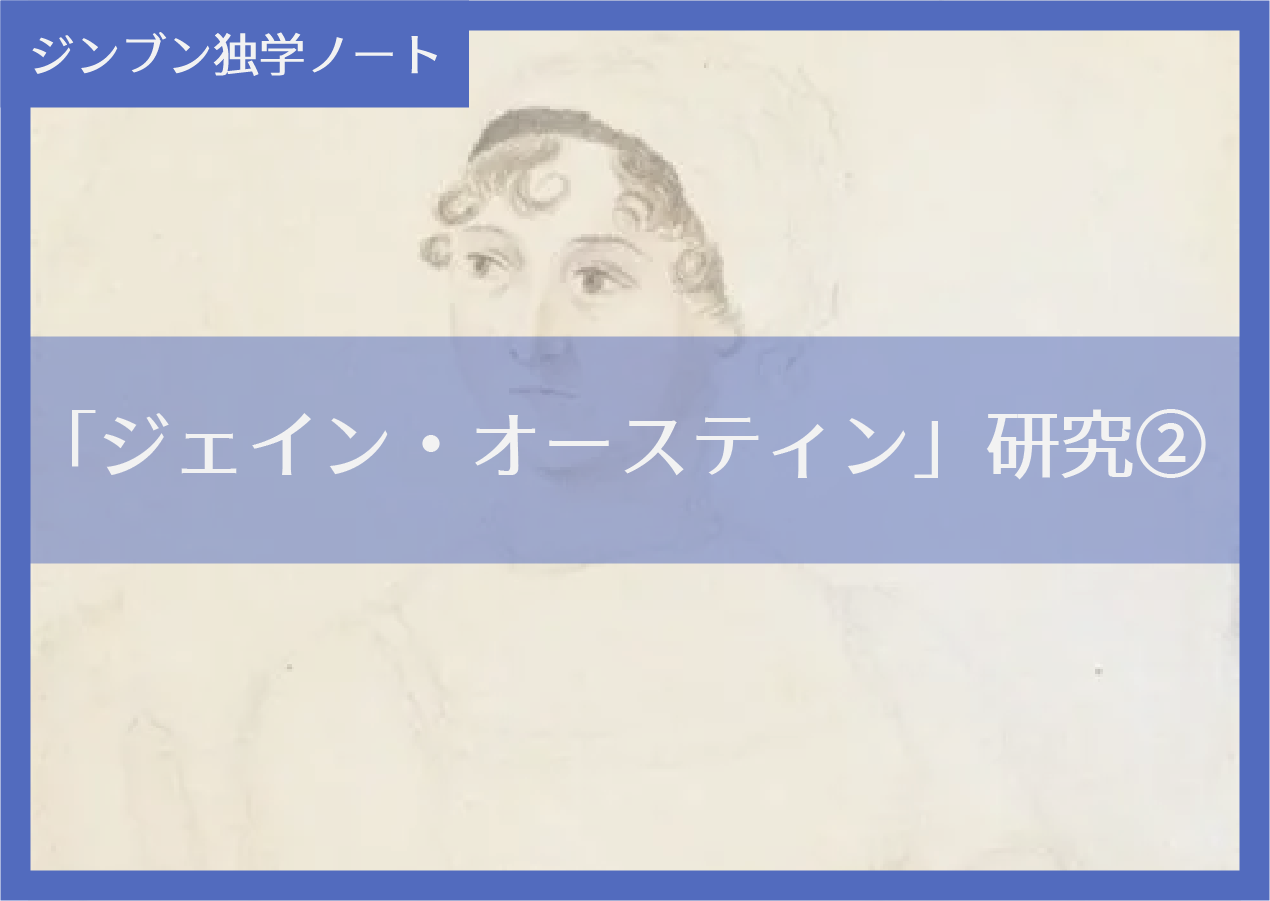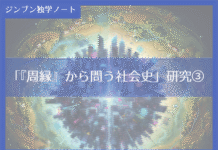——なるほど……研究テーマに対して、「それはあなたの人生とどれくらい関係があるの?」という、「説明責任」が求められる風潮への、抵抗みたいなものでしょうか。
説明責任ですか、確かにそうですね。ただ「自分とは違いすぎて、面白いから」ではダメなのだろうか、と。もちろん、突き詰めれば、その他者との違いの中に何らかの共通性を見出す、という反転は起こりえます。しかし、その入り口は、必ずしも自分語りと直結している必要はないのではないか、というのが私の考えです。
——その視点は、現在の研究テーマである「ヒストリー(歴史)」の扱い方にも繋がっているように感じます。
そうですね。あるとき、オースティンの小説に「ヒストリー」という単語が頻繁に出てくることに、まず気づきました。オースティン研究において、「歴史」は非常に重要なキーワードです。というのも、かつて彼女は、同時代の【フランス革命】といった激動の歴史を全く描かず、平和な田舎の日常ばかりを書いた作家、という評価が定着していました。
——歴史に無関心な作家、というイメージ。
それが1970年代後半から、「いや、オースティンは歴史を知ったうえで、あえて直接的には書かず、地方社会の日常生活の描写に、歴史を間接的に反映させているのだ」という、歴史的文脈で読み直すアプローチが主流になりました。私もその研究から多くを学びましたが、一方で違和感もありました。
——どのような違和感だったのでしょう。
「オースティンは歴史的事件のこれも知っていた、あれも書いていた」という議論が過熱するあまり、彼女の作品そのものが置き去りにされているように感じたんです。もし同時代について書くことだけが目的なら、わざわざフィクションという形式を選ぶ必要はない。もっと直接的な、例えば政治パンフレットのようなものを書けばよかったはずです。私は、もっと作品本体に、その言葉遣いや文体、レトリックといった言葉の質感・形状的側面に立ち返りたい、と思いました。
——そこで、「ヒストリー」という言葉の使われ方に着目された。
はい。ただ、これまでの研究のように「何の歴史が書かれているか」という‘what’を問うのではなく、「歴史はどのように(‘how’)語られるべきか」という、方法論に関心を移したかったのです。
——歴史の「中身」ではなく、「語り方」に注目する、ということでしょうか。
例えば、私たちが世界史の教科書を読むとき、その文体が美しいか、どうかを考えませんよね。書かれていることは全て客観的な「ファクト」であり、文章はそれを伝えるための透明な媒体だと無意識に見なしています。しかし、オースティンの生きた18世紀後半は、歴史叙述が非常に文学的だった時代なんです。
——現在の「歴史」観とは、ずいぶん違いますね。歴史が、むしろ「物語」に近かった。
そうです。当時、「ヒストリー」という言葉は「ストーリー(物語)」と同義で使われることがよくありました。歴史を語るには、その内容にふさわしい格調高い文体で書かねばならない、という意識が強くあった。
歴史=ファクトという考え方は、実は近代の歴史学、特に【ランケ】以降に確立された、比較的新しい価値観なんです。私は、そうした「歴史の語り方」そのものが、オースティンの想像力にどう影響を与えたのか、あるいは彼女がそれにどう反発したのか、という点を知りたかった。これまでのオースティンと「歴史」をめぐる研究から、視点をずらしてみたかったのです。
最終回は教える中での気づきについて伺います。