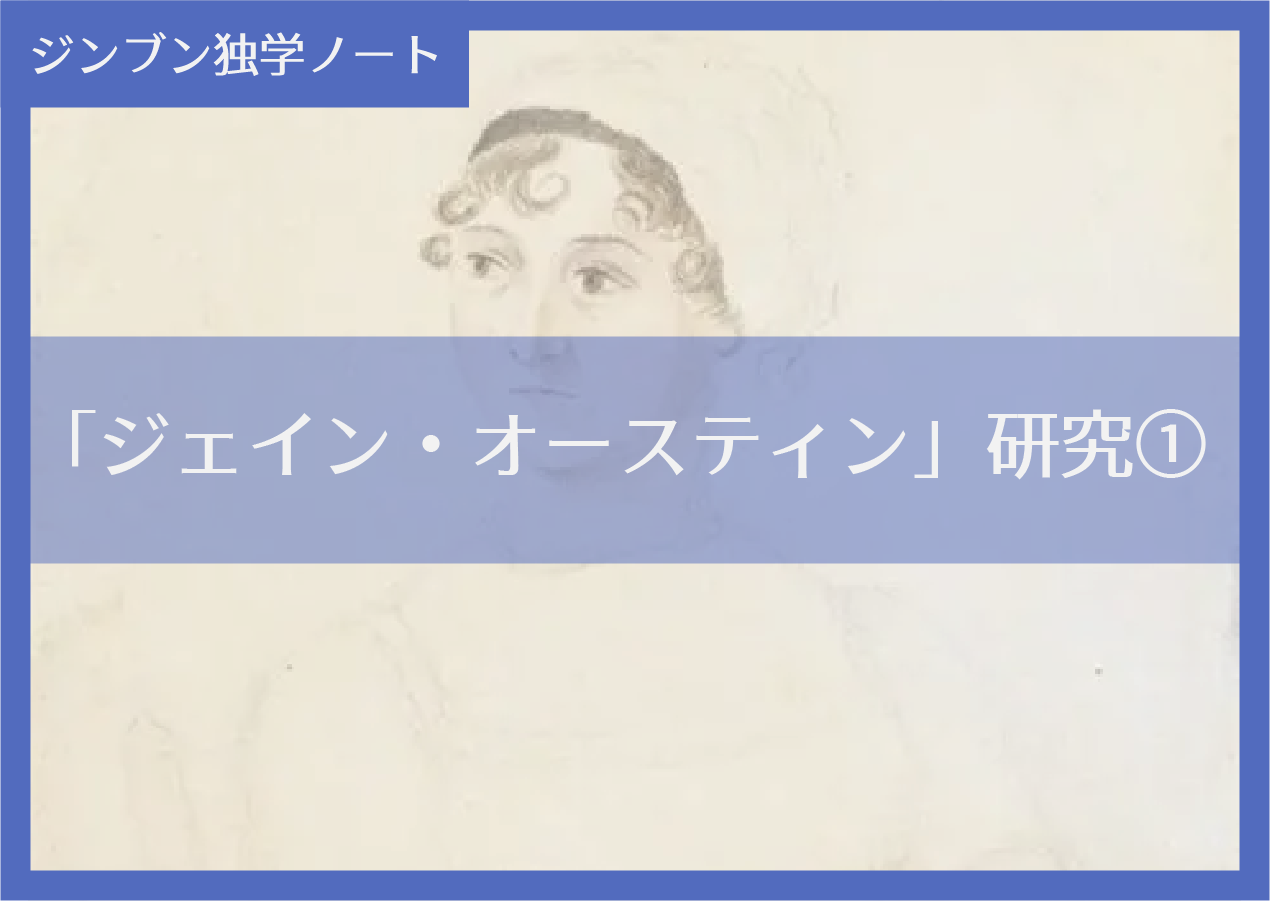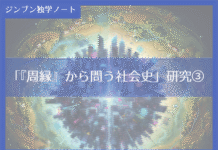ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十九回となる今回のインタビューでは、歴史が「何を」語るかではなく「いかに」語られるかという視点から、ジェイン・オースティンの作品を読み解き、文学の新たな価値と可能性を切り拓く、英文学研究者の広本優佳さんにお話を伺います。
導かれるように研究の道へ
——本日はどうぞよろしくお願いします。今回は、英文学研究者でいらっしゃる広本さんが、現在に至るまでの歩みや興味関心の変遷について、じっくりとお話を伺えればと思います。
よろしくお願いします。
——まずは、ご専門であるジェイン・オースティンとの出会いからお聞きしたいです。幼い頃から文学に親しんでいらっしゃったのでしょうか。
子供の頃は、年相応のものを読んでいましたね。ハリー・ポッターや『守り人』シリーズのような、ファンタジーや冒険物が大好きでした。いわゆる児童文学の古典も一通り読んでいたと思います。親の仕事で転勤が多く、人と話すのが少し苦手で、手持ち無沙汰な時間に本に救われていた、という事情もあって。
——本が、孤独な時間を埋めてくれる存在だったのですね。
そうですね。ただ、面白いことに、文学研究者になった今、その本が逆に私を孤独から引っ張り出してくれる窓口にもなっています。学会は人と話す機会に溢れていますし、作品を通して他者と対話することで、人との話し方を学んだ部分も大きいので。本は使い方次第で、孤独を培養するツールでもあれば、世界と繋がるためのツールにもなるのだな、と実感しています。
——児童文学から、専門で扱われる作品には、どの段階で興味が移っていったのでしょう。
私の読書遍歴は、実のところ下心だらけでして(笑)。少し背伸びをして、大人っぽいものを読む自分を意識して悦に入るという「ファッション読書」から入っだと思います。純文学を読んでいる自分、いいな、という感覚ですね。その中で出会った一冊がオースティンでした。背伸びして手に取ったつもりが、これが驚くほどしっくりきて、すっかり夢中になってしまいました。
——以前、インタビュー記事の中では、オースティンを「面白いことを言う頭のいいお姉さん」と表現されていましたね。ユニークな捉え方だな、と。
オースティン自身は妹なのですが、カサンドラという非常に仲の良い姉がいて、姉妹間で交わされた手紙もたくさん残っています。私が本当になりたいのは、オースティン本人というより、彼女の一番の理解者であったカサンドラかもしれません。あのジェイン・オースティンの才能を一番近くで目撃し、その本音を独り占めできる存在であったなら、と。
——最も近しいファンでいたい、というような。
それに近いです。ジェインになるのは恐れ多いけれど、カサンドラにはなりたい、と。ただ、有名な話ですが、オースティンの死後、カサンドラはオースティンの手紙の多くを燃やしてしまっているんです。それが研究者の間では議論の的になっていて。
——なんと! 貴重な手紙が失われてしまったんですね。
はい。残された手紙にもかなり不謹慎なことが書かれているので、燃やされた分にはもっとすごいことが書かれていたのか、それとも純粋にプライベートを守るためだったのか……。後のヴィクトリア朝的な、体面を重んじる上品な文化に合わせて処分した、というのが通説ですが、私からすれば同志カサンドラに裏切られたという失望の念でいっぱいです(笑)。私なら絶対に燃やさずに後生大事に保管して愛でていたでしょうね。
——(笑)。オースティンに魅せられ、高校生の頃に初めて読まれたのが『高慢と偏見』だったそうですが、最初の印象は覚えていますか?
それが、不思議とあまり覚えていないんです。オースティン研究者がよく言うことなのですが、彼女は「再読をさせる作家」なんです。二回目、三回目……と、読むたびに新しい発見がある。伏線が張り巡らされているので、再読するごとに「ああ、ここも繋がっていたのか」と驚かされる。だから、最初の感動よりも、発見を重ねていく喜びで、常に記憶が更新され続けている感覚です。去年、大学の授業で扱ったときも、まだ新たな発見があって。何度絞ってもまだ味わいのある、スルメ的な作家ですね。
——オースティンという存在に出会い、そこから研究者としての道を意識されるようになったのは、いつ頃からだったのでしょうか。
いえ、実は最初から研究者になろうという気持ちは全くありませんでした。教員になろうかな、くらいに考えていて。ただ、大学院に行きたい、という気持ちだけは漠然とありました。それも「修士」の響きがかっこいいから、という理由で、相変わらず形から入るタイプなんです(笑)。
——形から入って、いつの間にか本気になってしまうと。
そのパターンが多いですね。いつのまにか好きにさせられているといった具合です。卒論指導の先生に感銘を受けたこともあって、もっと研究を続けてみたい、と思うようになり、修士課程に進みました。そこでもさらに探求したいことが見つかって、博士課程へ、と。結果的にずるずるとここまで流れ着いてしまった、という感じです。研究者という職業は、目的ではなく、あくまで結果として後からついてきたものです。
次回は彼女の核となる考え方ついて伺います。