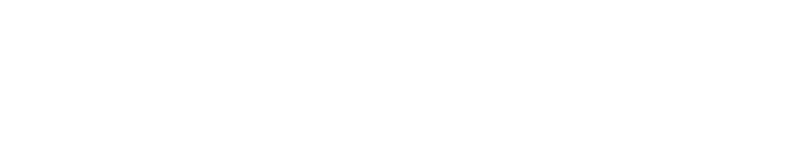ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三十三回となる今回のインタビューでは、中国哲学や高村光太郎研究の視座を活かし、独自の「哲学する」教育を実践されている国語科教員、平居高志さんにお話を伺います。
学問への違和感と「今を生きる思考」の探求
——本日は、平居先生のユニークな学問的経歴と、教育現場における「哲学する」ことの実践について、深くうかがいたいと思います。特に、中国哲学へのご関心から、現在の教育実践に至るまでの歩みをお聞かせください。
よろしくお願いします。
——平居先生のご経歴を拝見すると、中国哲学が大きな軸になっているように思いますが、どのようなきっかけで関心を持たれたのでしょうか。
あの、中国哲学に対する関心って言われると、なんだか恥ずかしいんだけども、元々はですね、ドイツ哲学をやろうと思って大学には入ってるんですよ。
やっぱりその、哲学というものが世の中を深く考えていく上で、すごく有効なんじゃないかっていう直感みたいなものは高校時代にあって。私にとっての哲学っていうのは、ドイツ観念論かな、みたいなものがあったんです。
ただ、私が進学した大学はその3年生からしか専門に分かれない。それで、高校時代に金谷治(かなや おさむ)さんという方が訳注を書いた岩波文庫の『論語』が結構好きで読んでいたんです。
——有名な『論語』の訳注ですね。
金谷先生はその当時、東北大学の教授だったので、一度この訳者の方にお会いしてみたいなと思って、研究室をお尋ねしたんです。そこで外国語選択の話になり、「私は英語とドイツ語を取ろうと思っています」と言ったら、「英語なんて高校まででやったんだから、いいじゃないか」と。
——なかなか大胆なご意見ですね。
文学部というのは、外国語は二つ取れば何でもいいという話だったので、「ドイツ語と中国語でどうだ」と言われて。
当時、中国語の選択者っていうのはものすごく少なくて。確か、全学部合わせて50人くらいだったんじゃないかな。2300分の50。今では考えられないですよね。先生も癖の強い方で、人間関係も濃密。
それで、だんだんだんだん足をすくわれ、絡め取られ……。もう「西洋のことをやりたい」とは言えない雰囲気が出来上がっていき、いつの間にか「中国哲学専攻します」っていう風に首を縦に振ってたっていうのが、非常に情けない経緯です。
——それは、まさに「いつの間にか」という感じですね。
『論語』は今でもスタンダードだと思います。ただ、当時は「考えることが好き」というよりは、自分なりにいろんな悩みがあったので、どういう風なものの考え方をしたら、もっとすっきり世の中が見えてくるんだろう、みたいな問題意識というか、憧れというか、それはもう高校時代からあったと思いますね。
——そのようにして進まれた中国哲学の道ですが、最終的には修士を終えたところで大学院を止められています。そこには、どのような心境の変化があったのでしょうか。
いやあ、やっぱり中国哲学が最終的にしっくり行かなかったから、大学院を止めたというところがあって。
私の最初の本が『「高村光太郎」という生き方』という本なんですけども、高村光太郎のものの考え方と、私が大学時代に研究していた王陽明(おうようめい)の考え方って、その思考の根っこにある部分、「自我を大切にする」という考え方がすごく似ているんです。
私としては、王陽明を研究することによって、そういう思考の原点みたいなものを考えていくよりは、同時代人である高村光太郎を通して考えた方がしっくり来た。ですから、陽明学のフレームを使いながら高村光太郎を読んでいった、というところがあるんです。
——中国哲学のフレームを、日本の近代詩人である高村光太郎に当てはめていった、と。
やっぱり、約500年前の中国というのは、その時代背景の違いとかを理解するのが非常に大変で。その一方、高村光太郎は言葉もすごく平易だし、背景もやっぱり理解しやすいところがある。何も無理して王陽明にしがみついてる必要はないなと。それが私の高村光太郎論の原点なんですよね。
——大学での「哲学研究」という営みそのものに、難しさを感じられた部分もあったのでしょうか。
それはありますね。やっぱり「考える」っていう作業は、研究の形でやってしまうと、「過去の人間がどう考えたか」っていう事実報告になっちゃうわけですよ。
ところが、「考える」っていう作業は、今目の前で展開される様々な出来事に対して、自分がどうアプローチするかを考えざるを得ないわけです。
すると、過去の出来事を分析することと、今自分が目の前の事象に対してどう考えるかってことの間に、ズレというか、ギャップというか、それがだんだん違和感として大きくなってくる。そういうことなんだろうと思うんですね。
——あくまで「今を生きるために考える」ということが重要だったのですね。
考えるっていう作業そのものは、やっぱり今を生きるために考えるべきであって。過去の先人たちの考えたことが、そのための参考になるんだったら研究するのもいい。
でも、そうじゃなくて、事実をどうやって報告するかという形での論文を書く作業は、私にはちょっと違和感があった。過去の哲学者についてきちんと理解ができなければ、今私が目の前にある出来事について何も考える権利がないんだ、っていう風にしてしまったんでは、話にならないわけです。
——その後、博士号は中国史の論文で取ったとお聞きしたのですが、それはどういうことですか?
思想と違って、歴史は事実報告そのものに価値があるから、論文を書くことに違和感がなかったんです。
大学を止めて教員になった後は、たまたま知った冼星海(しょうせいかい)という作曲家と、彼が生きていた20世紀前半を研究対象として、厳しい時代状況の中で知識人がどんな生き方をしたのか、というようなことをネチネチネチネチと研究してきたわけです。
資料集めを始めた時から数えると20年ほどかかったその仕事が一段落したので、今は本丸、毛沢東の権力掌握過程に対象をシフトしています。別に役に立つことを求めてやっているわけではありませんが、今の中国政府を考える上でも面白いな、とは思いますね。
次回は教師になったきっかけについて伺います。