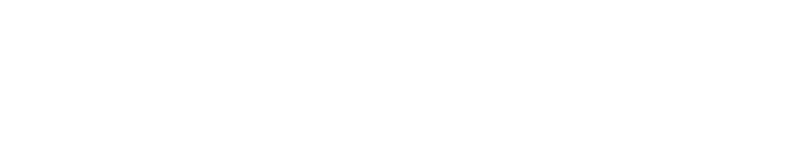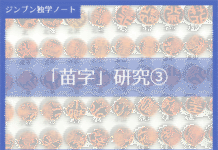ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三十八回となる今回のインタビューでは、奈良市教育委員会で発掘調査の最前線に立ちながら、測量技術やデジタル機器を駆使して古墳時代の社会構造解明に取り組む考古学者、柴原聡一郎さんにお話を伺います。
「3階建て」の研究プロセスと現代的視座:客観的記録から歴史の再解釈まで
——研究スタンスについて具体的にお聞かせください。現在は奈良市で発掘調査に従事されていますが、研究はどのように進んでいくのでしょうか。
考古学の研究プロセスは、大きく「3階建て」になっています。
1階部分は「発掘調査」です。これは完全に客観的でなければなりません。発掘とは、一度掘り返せば二度と元には戻せない「破壊行為」でもあります。だからこそ、誰が掘っても同じ記録が残るよう、科学的な再現性が求められます。
この段階では、私個人の「こうあってほしい」という歴史観は邪魔になります。心を無にして、検証可能なかたちで事実を記録する。技術者としての厳密さが求められるフェーズです。
——そこでは、柴原さんの得意な「測量」が生きるわけですね。
そうです。従来の考古学は、手書きで図面を描くアナログな手法が主流でしたが、どうしても描き手の主観が入り込みます。私はそこにドローンによる空撮写真測量や、レーザースキャナによる3次元計測を導入しています。デジタル技術で対象を丸ごとスキャンすることで、手書きの図面よりも第三者が検証しやすい記録を残すことができます。
——そして、2階部分が……?
「報告書の作成(資料化)」です。発掘で得られた成果を、自分以外の研究者も使えるように整理して公刊する作業です。ここでもまだ客観性が重要ですが、どう整理するかという点では、ある程度の編集能力や視点が必要になります。
そして最後の3階部分が「論文執筆」です。ここで初めて、自分の解釈や歴史観を展開できます。「発掘されたこの事実から、当時の社会はこう考えられる」と論じる。
この3つのステップを行き来するのは、頭の切り替えが非常に大変ですが、自治体の埋蔵文化財センターにいるからこそ経験できる醍醐味でもあります。
——論文を書く、つまり歴史を解釈する際、柴原さんが特に意識されていることはありますか?
「歴史観は、常に現代の価値観と合わせ鏡である」ということです。
例えば、20〜30年前までの古墳時代研究では、「倭王権が強力なリーダーシップを持って、主体的に日本列島を統一していった」という、中央集権的な見方が主流でした。
しかし近年では、「倭というのは、あくまで各地の有力な豪族たちの連合体であり、大王はその神輿(みこし)として担ぎ上げられた存在だったのではないか」という、より緩やかなネットワーク型の社会像が支持されるようになっています。
——トップダウンから、ネットワーク型へ。大きな転換ですね。
なぜこの変化が起きたのか。新しい遺跡が見つかったこともありますが、それ以上に、現代を生きる我々の価値観が変わったことが大きいと思います。
インターネットやSNSが普及し、中央からの発信だけでなく、個人のネットワークが世界を動かす時代になりました。そうした現代の空気を吸っている研究者が過去を見たとき、「古代も実はもっと多元的なネットワーク社会だったのではないか」という新しい仮説が生まれるわけです。
——私たちの生きる現代社会の変化が、過去の見え方を変えてしまうと。
そうです。ですから、私が今書いている論文も、20年後の研究者から見れば「2025年頃の人間はこういうバイアスで歴史を見ていたんだな」と分析される対象になるでしょう。でも、それでいいんです。歴史研究とは、絶対不変の真実を固定することではなく、その時代ごとの切実な問いを過去に投げかけ、対話することですから。
そう考えると、下水道のない古墳時代には行きたくありませんが(笑)、現代という時代に足をつけて過去を覗き込む今の仕事は、やはり面白いなと思います。
——最後に、今後の展望をお聞かせください。
先月、ようやく博士論文を提出しました。研究者としてのひとつの区切りですが、キャリアとしてはまだまだこれからです。
考古学の世界では、発掘現場での「場数(ばかず)」を踏むことが重要視されます。現場を知らないと、机上の空論になってしまいますから。
奈良市というフィールドは、若手でも重要な調査を任せてもらえるチャンスが多く、非常に恵まれた環境です。ここでしっかりと「1階部分(発掘)」の足腰を鍛えつつ、いずれは大学などの研究機関に戻って、より広い視点で「3階部分(歴史の解釈)」を突き詰めていきたいと考えています。