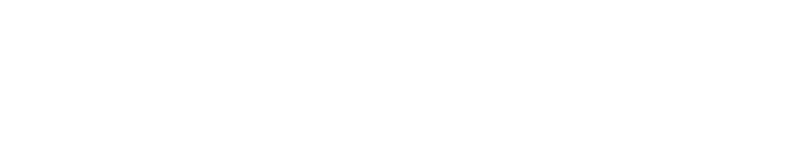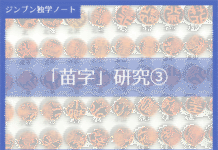ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三十六回となる今回のインタビューでは、近代日本の災害史における行政対応を研究する傍ら、中学校の教壇に立ち、アカデミズムと教育現場の架け橋として「考える歴史」の実践に取り組む、寺谷嘉泰さんにお話を伺います。
外交史から災害史へ——大蔵省議事録に見る「官僚たちのリアリズム」と研究者の使命
——そうして文学部の日本史学研究室に進まれるわけですが、最初から現在の専門である「災害史」を選ばれていたわけではないそうですね。
はい。実は当初、外交史、特に昭和戦前期の日ソ関係をやりたいと思っていました。
——日本とソ連の国際関係ですか。なかなか大きなテーマです。
中高の授業でソ連が出てきても、つかみどころのない国のようなイメージだと思うんです。「この得体の知れない国を、当時の日本政府や軍部はどう捉えていたんだろう?」という疑問が中高時代からずっとあって。学部3年のときに受けたゼミでも、意気揚々と「日ソ関係をやりたいです!」と宣言しましたね。
——先生方の反応はいかがでした?
先生方も本気で向き合ってくれて、「で、結局、日ソ関係の何をやりたいんだ?」と詰められました(笑)。まだ学部3年生ですから、「いや、日本がソ連のことをどう捉えていたかが気になって……」としどろもどろになりながら、当時の自分なりに答えましたね。
そんなとき、転機が訪れました。鈴木淳先生の「関東大震災と東京帝国大学」という講義を受けたんです。
——鈴木淳先生、近代史の研究者としてよく知られていますね。その先生の講義を受けたと。
はい。それを受けて「地震と歴史学って、意外と面白い組み合わせだな」と気づかされました。それと同時に、ふと自分のルーツを思い出したんです。私の実家のお墓が、兵庫県の豊岡市というところにありまして。
豊岡といえば、1925年(大正14年)に発生した北但馬地震の被災地なんです。「あ、そういえばあの地域も地震に遭っているよな。しかも大正時代、1925年……」と。鈴木先生の講義と自分のルーツが繋がったような瞬間でした。それで、北但馬地震における政府の対応、特に税制措置や救済融資をテーマにしようと決めました。
——外交史から災害史へ、しかも自分の地元と関係のある話題を見つけた。劇的な転換ですね。しかし、外交史に惹かれていた寺谷さんらしく、「政府や行政がどう動いたか」という視点は一貫しているように感じます。
そうなんですかね。災害史というと、地元の復旧・復興の様子を追う「地域史」、「地方史」のアプローチが多いんですが、私は「地方で地震が起きたとき、中央政府はどう対応したのか」に関心がありました。
実は、北但馬地震の2年前、1923年に関東大震災が起きています。未曾有の大災害を経験した直後の政府が、その経験をどう地方の地震に応用したのか。そこには何か連続性があるはずだと考えました。
——なるほど。関東大震災という巨大な「前例」が、その後の災害対応にどう影響したのかを見るわけですね。実際の調査はどのように進められたのですか?
まずは豊岡市立歴史博物館に通い詰めました。1925、1926年の町会議事録を見せてもらい、そこに並んでいる数字をひたすら書き写して再計算する地味な作業から始めました。「町長、こんな演説してたんや」とか、生々しい記録が残っていて面白かったですね。
それと並行して、中央政府の動きを追うために史料を探していたら、なんと東京大学経済学図書館に、当時の大蔵省の議事録が奇跡的に残っていたんです。
——大蔵省の内部文書が、なぜか東大に。そんなこともあるんですね。
「なんでここにあんねん」と思いましたが(笑)、先生からも「これ結構貴重だから大事にしてね」と言われて。その議事録を分析していくと、非常に興味深い事実が見えてきました。
政府内で被災地への融資額を決める際、「関東大震災の被害規模がこれくらいで、今回の北但馬地震の被害規模はこれくらい。だから、金額も関東大震災時の『何分の一』にする」という議論が、明確な数字ベースで行われていたんです。
——感情論や政治的パフォーマンスではなく、けっこう冷徹な計算式があったと。
はい。非常にお役所的ではあるんですが、「関東大震災の対応基準」が明確に引き継がれていることが分かりました。「前例踏襲」と言うとネガティブに聞こえるかもしれませんが、未曾有の災害で得た知見や制度を、ノリや雰囲気ではなく、客観的な数値に基づいて地方の災害に適用しようとした。その当時の官僚たちのリアリズムを実証できたのは、卒論の大きな成果だったと思います。
——学部生でそこまで一次史料に食らいつき、新たな視点を提示できたのは素晴らしいですね。そのまま修士課程に進まれたのは、やはり「まだやり残したことがある」という思いからでしょうか?
そうですね。卒論では1925年の北但馬地震という「点」しか見られませんでした。でも、災害史全体を理解するには、23年の関東大震災はもちろん、その後の昭和期の地震も含めて「線」や「面」で捉え直さなければなりません。「4万字の卒論じゃ終わらん!」という気持ちが強かったですね。
それと、これは少しおこがましい、「天狗」的な発想かもしれませんが……。
——天狗的な発想?
いろいろ調べていく中で、「災害大国と言われている割に、歴史学の分野から災害復旧・復興や制度を研究している人が少なすぎるんじゃないか?」と思ったんです。外交史や政治史にはたくさんの研究者がいますが、災害史となるとプレイヤーが極端に少ない。「誰もやってないなら、俺がやるしかないやん」という妙な使命感がありました。卒論執筆や院試の勉強中、精神的に追い詰められそうなときは「この分野は俺しかおらんねん」と自分に言い聞かせてメンタルを保っていました(笑)。
——その「勘違い」こそが研究者の駆動力になりますよね(笑)。
本当にそうです。先行研究の少ないブルーオーシャンにたどり着けた幸運には感謝していますが、同時に難しさも感じています。研究が進めば進むほど、自分の研究を歴史学全体の中でどう位置づけるか、その「位置づけ」の言語化に苦労しています。「で、それが分かって何になるの?」という問いに対して、まだ胸を張って答えきれていない。それが今の最大の課題ですね。
最後は教育現場での実践について伺います。