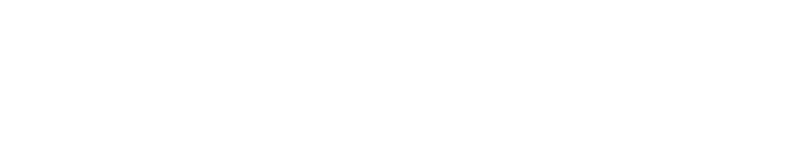ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三十五回となる今回のインタビューでは、日本語母語話者と非母語話者の接触場面における相互行為(アコモデーション)を専門とし、言語の構造だけでなく言葉の背後にある心理や態度の分析に注力する日本語教育研究者、張瀟尹(ちょう・しょういん)さんにお話を伺います。
日本語との出会いと、留学先で直面した「研究の壁」
——本日はどうぞよろしくお願いします。まずは、瀟尹さんの原点からうかがいたいと思います。現在は日本語教育、特に「日本語を母語とする話者と、日本語を母語としない話者との接触場面」における会話の研究をされていますが、日本語との出会いはどのようなものだったのでしょうか。
実は、日本語を本格的に学び始めたのは18歳、大学に入ってからなんです。それまでは全く知識がなくて、アニメやドラマを字幕付きで見ていた程度でした。振り返ると、私の原点は「英語があまり好きではなかった」というところから始まっているかもしれません(笑)。
——英語がお好きではなかった、というのは意外ですね。語学全般に関心があったわけではないのでしょうか。
当時の中国の英語教育の影響が大きいですね。完全に「試験のための英語」だったんです。問題を解くテクニックは教え込まれるけれど、実際に話すチャンスはほとんどない。英語圏の文化やコミュニケーションの面白さに触れる機会もなく、ただ点数を競うための科目という感覚で、全くワクワクしなかったんです。
そんな高校時代、仲の良い友人が日本のアニメやドラマを教えてくれました。それを見て直感的に「あ、いいな」と思ったんです。言葉の響きなのか、醸し出される雰囲気なのか、英語には感じなかった親近感を覚えました。それで、大学進学の際に「英語よりは日本語のほうが自分に向いているかもしれない」と、なかば直感で日本語学科を選びました。
——直感的な「相性の良さ」を感じられたのですね。
はい。それと、これは少し恥ずかしい話なのですが、当時の私の中に「外国語を流暢に話す女の子」への憧れみたいなものがあったんです(笑)。外国語大学で専門言語を操る女性って、なんだかおしゃれで自立していて、かっこいいイメージがあったんですよね。
周囲からは「女の子なら会計や経済、経営を学んだほうが将来安泰だよ」とよく言われました。でも、当時の私は少し反骨精神があったのか、「将来の安定のために、今やりたくもないことを勉強するのはダサい」と思ってしまって(笑)。
——「安定よりも、自分が心から惹かれるものを」という選択だったわけですね。
そうです。打算で選ぶ人生は面白くない。自分が本当にかっこいいと思える自分になりたい。そんな気持ちで日本語の世界に飛び込みました。
いざ学び始めてみると、すぐに「これは楽しい!」と夢中になりました。読み書きだけでなく、初めて日本人教師と話が通じた時の喜びは強烈でしたね。「あ、通じた」「聞き取れた」という達成感の連続で。そこからはもう、日本語沼にどっぷりです(笑)。もっと上手くなりたい、日本人のような自然な話し方がしたい、と強く思うようになりました。
——具体的に影響を受けた作品などはありますか?
二つ、忘れられない作品があります。一つは岩井俊二監督の映画『Love Letter』です。雪景色の映像美、繊細な心理描写、そして音楽。すべてに衝撃を受けました。「こんなに静かで美しい世界があるんだ」と。
もう一つはドラマ『プロポーズ大作戦』です。これはもう、当時の私にとって「理想の青春」そのものでした。というのも、中国の高校時代は本当に勉強漬けだったんです。毎月、毎週のように試験があってランキングが発表される。恋愛も禁止、遊びに行くのも制限され、制服はジャージのような可愛くないデザインで……。だから、日本のドラマの中にある、制服を着て、放課後に友達と恋バナをして、文化祭で盛り上がるようなキラキラした高校生活に、強烈な憧れを抱いたんです。「私もこんな青春を送りたかった!」って(笑)。
——その「日本文化への憧れ」が、学習への強力なエンジンになったのですね。
そうですね。大学のクラスには20人ほどの学生がいましたが、実はそこまで熱心に「日本人と話したい」と思っている子は少なかったんです。多くの学生にとって日本語はあくまで専攻科目の一つで、卒業後に日本語を使って仕事をしたいとまで思う人は一握りでした。
でも私は違いました。とにかく生の日本語に触れたくて、大学にいた日本人教師に積極的にアプローチしました。授業の後で「先生、ご飯行きませんか?」と誘ったり、休日には「私の実家に遊びに来てください!」と招待したり。
——先生をご実家に招待されたんですか? それはすごい行動力ですね。
実家が大学から車で1時間半ほどの場所にあって、近くに観光地もあったんです。「美味しい上海蟹がありますよ」なんて言って(笑)。先生とそのご友人を招いて、祖父母や両親と一緒に食事をしました。とにかく「教室の外」で、教科書ではない日本語を話したかったんです。そうやって自分でチャンスを作っていく過程も楽しかったですね。
——そうした熱意を持って、大学院への進学、そして日本への留学へと進まれるわけですね。
はい。中国の大学院に進学した後、短期留学の制度を使って念願の日本へ来ることができました。最初は一橋大学の研究生として受け入れてもらったのですが、ここで私は研究者としての最初の大きな壁にぶつかることになります。
——壁、ですか。
はい。日本に来る前、私は中国で「断り」や「依頼」といったテーマについて研究計画を立てていました。例えば、中国人日本語学習者が日本語で誘いを断る時にどういう表現を使うのか、といった語用論的な分野です。中国国内にいた頃は、まだ研究の余地があるテーマだと思っていました。
ところが、日本に来てみると、その分野の研究はもう10年も前に最盛期を迎えていて、「それはもうやり尽くされたテーマだよ」という雰囲気だったんです。「えっ、今さらそれをやるの?」と(笑)。
——それはショックですね……。「最新の研究」だと思って海を渡ったら、現地では「過去の話」だったと。
もう、目の前が真っ暗になりました(笑)。日本が本場ですから当然なのですが、自分の情報の遅れと、研究のトレンドを把握できていなかった未熟さを痛感しました。ゼミでの発表形式も、議論の仕方もわからない。日本語には自信があったはずなのに、学術的な議論になるとついていけない。最初の半年間は、自分の無力さに打ちひしがれていました。
次回は談話分析との出会いを伺います。