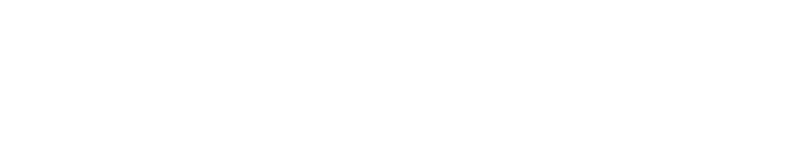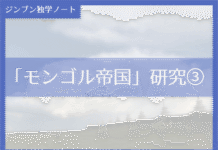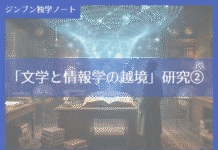ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三十一回となる今回のインタビューでは、アルベール・カミュの研究を専門とし、フランス各地の資料館を巡る「アウトドアな研究者」でもあるフランス文学者の渡辺惟央さんにお話を伺います。
留学中の転機とカミュ研究の「発見」
——そして、実際にフランスへ留学されるわけですね。
2年生の時に応募して、1年間の交換留学の枠を一つ勝ち取ることができました。ただ、社会学系の留学先は人気なため、3、4年生が優先される傾向にあると聞いていたので、2年生の私は文学系の枠を狙いました。それで、フランスのパリ第3大学の文学科に留学することになりました。
そこでは当然、必修科目はフランス文学の授業ばかりです。私は勝手に、選択科目で社会学やメディア論の授業を取っていたのですが、必修だったフランス文学の授業を受けるうちに、ものすごく面白いことに気づいたんです。
——面白かった、というと?
学部1年生向けの文学演習でした。最初の課題で、テオフィル・ゴーティエという作家の文庫本と、3色以上のマーカーを用意せよ、という指示がありました。それで学生全員が本とマーカーを持ってくると、教員は、文中に出てくる全ての名詞と形容詞を、そこから連想する感覚に応じて色分けしていけ、と指示しました。青は寒さや冷たさ、赤は暖かさや温もり、茶は重さや硬さ、黄は軽さやしなやかさ、といったふうに。
言われた通りにマーカーで塗っていくと、物語の序盤では登場人物の不安や恐怖を表すように青色のマーカーが中心で、物語が進むにつれて、次第にページ全体のマーカーの色が青から赤へ、また茶から黄へと変化していくのがはっきり分かりました。読んで、なんとなく感じ取っていた登場人物の感情の移ろいを、他人に説明できるように可視化する。このような文章読解の基礎を、マーカーで色分けするという作業で教えてくれたのです。
言葉にすると簡単ですが、授業中のアクティビティとしては非常に考えられた教案になっていて、感動しました。18歳に文学をどうやって教えるか、どうやって小説を論じる方法を教えるかが、完璧にシステム化されていた。その後も、文中の動詞をリストアップしたり、特定の形容詞が何回使われているかを数えたりといった課題が出され、小説を分析するテクニックをたくさん教わりました。
「これなら研究できるぞ」と思いました。文学研究というものが、初めて地に足のついた学問として感じられたんです。社会学の授業よりも、断然面白かった。
——そこで初めて、文学研究そのものに惹かれていったのですね。
そこから本気で、フランス文学の授業を受けるようになりました。ちょうどその頃、アルベール・カミュとも出会いました。それまでは、代表作の『異邦人』は一応読んでいたけれど、長編小説の『ペスト』にはどう近づいていいか分からず、という感じで、カミュに特に関心があったわけではありませんでした。
それがある時、あまり知られていないカミュの短編集があることを知って、短編なら読み切れるだろう、と手に取ったんです。これが、とても面白かった。
——また、少し中心から外れたところを。
あまのじゃくなので(笑)。代表作ではない作品から面白さに気づけたことで、カミュに興味が湧きました。しかも、個人的に面白いと感じただけでなく、そこに「発見」があったんです。
——発見、ですか。
その短編集には六つの短編が収められていたのですが、読んでいくうちに「あれ?」と。一つ目、三つ目、五つ目の短編が、同じセリフで終わっていることに気づいたんです。ところが、先行研究をいろいろ調べても、誰もそのことに言及していない。
「これは、自分が最初に指摘するだけでも価値があるかもしれない」と思いました。ただ、発見したことをアピールするだけでは物足りない。なぜカミュはこんなことをしたのか、その狙いは何だったのか。そこまで掘り下げてみたい、という強烈なモチベーションが湧き上がってきたんです。
——ご自身の内側から湧き出た問いだったのですね。
そうです。誰かに「これが偉大な作品だ」と言われたからではなく、自分で金脈を見つけたような感覚でした。納得できるまで、徹底的に調べてやろう、と。その探求に夢中になっているうちに留学期間は終わり、帰国してから、カミュの調査に没頭しました。
カミュの出身地は北アフリカのアルジェリアなんです。もともとアフリカに興味があった私にとって、「これでフィールドが見つかった」と思いました。植民地の歴史という複雑な問題はありますが、自分の興味の原点と、研究対象が偶然にも結びついた。この出会いが、私をフランス文学研究者の道へと導いてくれたんです。
——その「発見」は、ご自身のフランス語読解力があったからこそ、ですね。
そう言っていただけると嬉しいですが、むしろ逆かもしれません。そもそも長文を読み切ることに苦手意識が強くありましたし、当時はまだフランス語を読むのが遅かった。だからこそ、一語一語をものすごくゆっくり調べたり、いくつかの短編を同時並行で読み進めたりしていて、いろいろなことに気づけたのかもしれません。「あ、この作家、他の作品のあの表現を書き写してるな」とか。こうした文中に隠れた事実に着目して、それが何を意味しているのかについて考えるのがとても楽しかったんです。
——刑事の捜査のようですね。
まさに、です。日本の大学の指導教員からは、「文学研究は妄想を書いてはいけない、事実だけを見ろ!」「テクストに向き合う時は、『現行犯逮捕』を目指せ!」と教わりました。作家が明らかに何かを「した」という痕跡、つまり「現行犯」の証拠をテクストから見つけ出し、なぜそんなことをしたのかを分析する。その繰り返しなんです。
最後は社会に繋がる研究者の姿勢について伺います