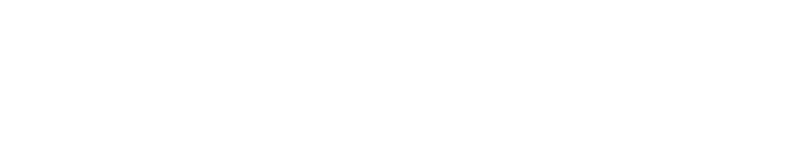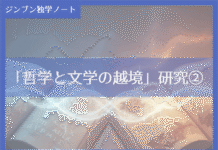ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第二十九回となる今回のインタビューでは、「国家」という当たり前の存在を歴史の中に問い直し、「石油が国家を作るとき」という独創的な視点からその成り立ちを解き明かす、研究者の向山直佑さんにお話を伺います。
「資源の呪い」への違和感から生まれた独創的研究
——そして大学院に進まれ、いよいよご自身の研究テーマを探す段階に入ります。修士課程の頃から、「石油が国家を作る」という着想はお持ちだったのですか。
いえ、最初から明確なテーマがあったわけではありません。東大での指導教員だった藤原帰一先生もおっしゃっていましたが、「リサーチクエスチョンを思いついた時点で、研究は半分終わっている」んです。それくらい、自分独自の問いを立てるのは難しい。それまで授業で良い成績を収めてきた優秀な学生でも、いざオリジナルの研究となると、クリエイティブな発想が出てこずに研究の道を諦めてしまう、というケースも少なくありません。
私も、いくつかアイデアを指導教員にぶつけてみては、あまり良い反応が得られず…という試行錯誤を繰り返していました。転機になったのは、修士課程で受講した比較政治学(異なる政治システムを比較することで一般的な知見を導こうとする政治学の一分野)の授業です。
——どのような授業だったのでしょう。
一つの学問分野の中で毎週異なるテーマ、例えば「選挙」や「内戦」といったトピックについて複数の文献を読み、ディスカッションを行う、いわゆるフィールドセミナー形式の授業でした。その中の一回で、「経済発展と民主主義の関係」を扱い、そこで初めて「資源の呪い」という概念に出会ったんです。
——「資源の呪い」とは、石油などの天然資源が豊富な国ほど、民主主義が阻害されたり、権威主義体制が温存されたりといった弊害が起こりやすい、という考え方ですね。
はい。その分野の論文を読んだ時、面白いとは感じたのですが、同時に、何か根本的なことを見落としているのではないか、という強い違和感を覚えました。というのも、この種の研究は、多くが大規模なデータセットを使っています。単純化して言えば、「石油の産出量」という変数と「民主主義の度合い」という変数の相関関係を、統計的に分析するわけです。
しかし、考えてみてください。例えばノルウェーとクウェートは、どちらも産油国ですが、全く異なる国ですよね。もちろん、統計分析では「統制変数」といって、他の要因の影響を考慮に入れることはできます。ですが、そもそもこの二つを同じ枠組みで分析すること自体に無理があるのではないか、と。国の成り立ちそのものが違うのだから、単に「石油の影響」というだけで一括りにはできないはずだ、と思ったんです。特に、「石油が見つかったから国になった場所」と、「すでに国として存在していた場所に石油が出た場合」では、全く違う話になるのではないか、と。
——その違和感が、ご著書の核心部分に繋がっていくのですね。
毎週提出していたコメントシートにその考えを書いて出したところ、授業を担当されていた前田健太郎先生が非常に面白がってくださって。「これは研究になるんじゃないか」と言っていただいたのが、全ての始まりです。
——一枚のコメントペーパーがきっかけだったとは。その先生の慧眼も素晴らしいですね。
本当にそう思います。今、自分が教える立場になってみて、学生から提出されるレポートやコメントの一つひとつに丁寧に目を通し、フィードバックを返すことがどれだけ大変なことかよく分かります。あの時、先生が私の拙いアイデアを拾い上げてくださらなければ、今の研究はなかったかもしれません。本当にありがたいことだったと思っています。
——その着想を基に、博士課程ではオックスフォード大学に留学され、研究を深めていかれます。ブルネイやカタールといった具体的な事例を、どのように分析していったのでしょうか。
基本的には、イギリスの国立公文書館に保管されている、植民地に関する資料を読み込む、という作業が中心でした。例えば、現地のスルタン(首長)がイギリスに何を要求しているか、あるいはブルネイがマレーシア連邦に参加するかどうかを巡る議論で、各当事者が何を主張していたか。そういった、植民地と本国の間の通信記録が膨大に残されています。
一日中、公文書館にこもってひたすら資料を読み、写真を撮り、後から整理してストーリーを組み立てていく。地道な作業の連続でした。
——そうした歴史的な一次資料と向き合う中で、ご自身の仮説が確信に変わっていったのでしょうか。
そうですね。もちろん、個別の事例、例えば「ブルネイの独立過程に石油が関わっていた」ということ自体は、ブルネイを専門とする研究者の間では指摘されていました。直感的にも分かりやすい話だと思います。
しかし、個別事例で何が起きたのかを解明することと、そこからある種の法則性を見出すことは、また別のレベルの話です。私のいる政治学や社会科学の分野では、一つの事例を扱うにしても、そこから「固有名詞を抜いた、何らかの関係性」を主張できるかどうかが問われます。つまり、「ブルネイではこうだった」で終わるのではなく、「ある特定の条件が揃えば、このような結果が導かれる」という、より一般的な形で説明できるか、ということです。そのレベルでは、まだ誰も手をつけていない領域だと感じていましたし、そこに自分の研究のオリジナリティがあると考えていました。
——なるほど。「歴史学」と「政治学」のアプローチの違いがよく分かります。
それぞれの学問分野に、何が良い研究とされるかの基準があります。私の場合、細かい文脈の話をするよりも、大きなマクロな話をする方が性に合っているのかもしれません。あるいは、そういう学問的トレーニングを積んできたから、自然とそういう発想になるのか。その両方でしょうね。
最後は今後の挑戦について伺います。