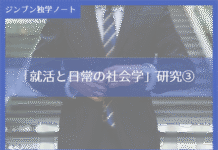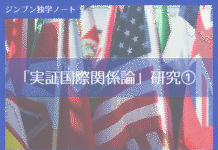ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第二十九回となる今回のインタビューでは、「国家」という当たり前の存在を歴史の中に問い直し、「石油が国家を作るとき」という独創的な視点からその成り立ちを解き明かす、研究者の向山直佑さんにお話を伺います。
研究者への道筋――国際情勢への関心と恩師との出会い
——本日はお時間をいただき、ありがとうございます。向山さんのご著書『石油が国家を作るとき』、非常に刺激的なタイトルで、その独自の視点にまず驚かされました。今回は、その斬新な研究テーマにたどり着くまでの向山さんご自身の歩みや、研究の根底にある問題意識について、じっくりとうかがえればと思います。
よろしくお願いします。
——早速ですが、向山さんは学生時代から国際関係や国家といったテーマに強いご関心をお持ちだったのでしょうか。
そうですね。国際情勢には高校時代から興味がありました。ニュースを見て、ある国で起きている事件の背景には何があるのか、なぜ戦争が起きるのか、といったことに関心があったんです。ただ、海外経験が豊富だったわけではなく、ニュースを通じて外国に興味を持っていた、というところからのスタートでしたね。より広い世界で起きていることを知りたい、という思いが、後の留学という選択にも繋がっていきます。
——大学は東京大学の文科一類に進まれていますが、最初から法学部で国際政治を、と考えていらっしゃったのですか?
いえ、そこまで明確に決めていたわけではありません。当時は弁護士や、外務省のような官僚の道も選択肢として考えていました。当時は文科一類が最も難関とされていたこともあり、将来の選択肢を広げる意味で戦略的に選んだ側面が大きいです。
大学に入ってからは、東京大学の教養学部(前期課程)のきまりで、様々な授業を受けるわけですが、その中で特に面白いと感じたのが国際関係に関連する授業でした。一つは、西洋中世史がご専門の高山博先生が主催されていた、通称「高山ゼミ」です。イギリスの週刊新聞、The Economistの記事を毎週読んできて議論するという内容で、先生のご専門は歴史ですが、ゼミでは現代の国際情勢を扱っていました。コミュニティとしても機能していて、非常に面白く、時間をかけて取り組みました。このゼミでの経験を通じて、元々あった国際情勢への関心が、より学問的な興味へと深まっていったように思います。
もう一つ、大きな出会いがありました。法学部の専門科目が始まる2年生の時、国際政治の必修科目を担当されていたのが藤原帰一先生だったんです。藤原先生の授業はとにかく話が面白く、引き込まれました。元々持っていた関心に、こうした授業との出会いが重なったことで、「この分野でやっていこう」と心が決まりました。
——魅力的な出会いが、進むべき道を照らしてくれたのですね。
そうですね。もし、例えば社会学の授業に夢中になっていたら、そちらの道に進んでいたかもしれません。それくらい、面白いと感じる授業との出会いは大きかったです。
——ただ、法学部の授業すべてが楽しかったわけではなかった、ともうかがいました。
はい。政治コースに所属していましたが、民法や憲法といった法律科目の授業も必修でした。しかし、これがどうにも面白く感じられなくて……。最初の学期で民法も憲法も「可」を取ってしまうくらい、成績も振るいませんでした。それに、国際関係の授業自体がそれほど多く開講されていたわけでもありません。学部3年生から4年生にかけては交換留学で日本を離れていたので、振り返ってみると、法学部にはあまり長く在籍していなかった、という感覚です。
——意外な学生生活ですね。それでも、研究者になろうというお気持ちは早くから固まっていたそうですね。
ええ、研究者という職業自体には、大学に入る前からなろうと考えていました。実は私の父が、分野は全く違いますが研究者でして、その仕事が非常に身近な存在だったんです。
——研究者のお子さんが同じ道を選ぶ、というお話はよく耳にします。
父の姿を見ていると、なんだかいつも暇そうだったんですよ(笑)。ずっと家にいて、よく遊んでくれましたし、あまりストレスなく仕事をしているように見えました。こういう生活ができるなら理想的だな、とずっと思っていたんです。ですから、大学に入った時点では分野は未定でしたが、いずれは大学教員になりたい、という気持ちが先にありました。
——まず「研究者になる」という目標があって、その中でご自身の専門分野を探していった、という順番だったのですね。
そういうことになります。まあ、実際に自分がなってみると、当時自分の目に映っていた父の姿より、現実の大学教員ははるかに大変だな、とは思いますけど。大学教員に求められる仕事の質も量も、当時とは大きく変わってきていますから。単に授業と研究だけをしていれば良い、という時代ではなくなりました。
——それでも、最初にポジティブな研究者像があったのは幸運だったかもしれませんね。
それは間違いなくそうですね。今の多忙な先生方の姿を先に見ていたら、もしかしたらこの道を目指していなかったかもしれません。
——学部時代に1年間、カナダのトロント大学に交換留学されています。これも研究者になるための計画の一環だったのでしょうか。
はい。海外の世界を見てみたいという純粋な気持ちはもちろんありましたが、かなり戦略的な判断でした。将来、研究者になるなら英語は必須ですし、いずれは海外の大学院、博士課程に進みたいと考えていました。その時に英語で苦労しているようでは話にならない。研究の本質的な部分に集中するためにも、語学の壁は学部のうちに乗り越えておきたかったのです。
——非常に計画的ですね。留学の成果はいかがでしたか。
手応えはありました。ただ、最初は本当に大変でしたね。授業で習う英語と、実生活で使われている英語は全くの別物です。お店で「Need a bag?(袋は要りますか?)」と聞かれても、最初は聞き取れませんでした。教科書には載っていない、生きた言葉に戸惑うことばかりでした。
それでも、こうした実生活での苦労も含めて、一度経験しておいたことは大きかったですね。この時の経験があったからこそ、後に博士課程でイギリスに行った際には、生活面で余計な苦労をせずに済みました。周りを見ていても、学部で交換留学を経験し、大学院で本格的に海外に出る、というステップを踏んでいる人は多いように思います。研究に集中するための、一つのスタンダードな道筋なのかもしれません。
次回は自身の研究について伺います。