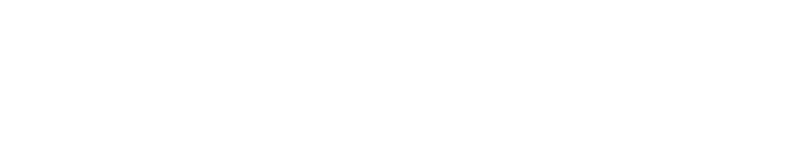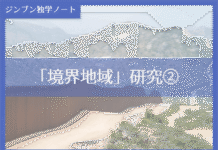ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第二十五回となる今回のインタビューでは、ご自身の歩みを社会史研究へと昇華させる実践的なアプローチで、ジェンダーや災害の問題に新たな視座を提示する、研究者の前川直哉さんにお話を伺います。
歴史への目覚めと「中央」への違和感
——本日はよろしくお願いいたします。先生は最近、ドラマ『虎に翼』でジェンダー・セクシュアリティ考証を担当されるなど、多岐にわたるご活躍で注目されています。今日は、そうした現在の活動に至るまでの、先生ご自身の興味や関心がどのように生まれ、変遷してきたのか、その歩みをじっくりとうかがえればと思います。
はい、よろしくお願いします。
——現在の先生の研究テーマというと、ジェンダー・セクシュアリティの社会史、ということになるのでしょうか。
そうですね、ジェンダー・セクシュアリティの社会史と名乗ることが多いです。ただ、本当に何でも屋といいますか、いろいろなことを調査研究しています。つい先月には『学校の「男性性」を問う』という教育とジェンダーに関する本(共編著)を出しましたし、その前にはジェンダー・セクシュアリティの教科書を共編で手がけ、私自身は概論と災害とジェンダーについて執筆しました。さらに今準備しているのはジェンダーではなく、福島のことを扱った本です。一見バラバラに見えるかもしれませんが、私の中ではすべてが繋がっています。
——ご出身の関西、研究や教員生活を送られた東京や京都、そして現在の拠点である福島。先生の人生の歩みと、それぞれの研究テーマが深く結びついているように感じます。そうした多角的な研究に至るまでには、様々な経緯があったかと思います。そもそも、先生が物事を考える上での原点は、どのようなところにあったのでしょうか。
幼い頃から、大きなもの、メジャーなもの、あるいは「中央」とされるものに対して、どこか反発心を抱く気質はあったように思います。関西出身なので、例えば東京の人が自分たちの言葉を「標準語」と呼んでいるとイラっとするとか、そういう感覚ですね。東京には、無意識に「東京=日本」だと思いがちな人も多いですから。
——私も地方出身なので、その感覚はよく分かります。
特に私は東大が嫌いでした(笑)。自分たちが日本の中心だと思っているような、あの雰囲気がどうにも好きになれなくて。私が6年間を過ごした灘中学校・高等学校は、良くも悪くも非常に濃密な人間関係の中で、強烈な個性の連中がおおぜいいる場所だったので、その印象の方が大きいのかもしれません。もちろん、じっくり付き合えば東大にもすごい人はたくさんいたのでしょうが、私自身は大学にあまり馴染めず、授業にもほとんど行きませんでした。だから、東大の表面的なところしか見えていなかったのだと思います。
——先生のアイデンティティは、東大よりも灘校での経験によって強く形作られているのですね。
そうですね。生徒として6年間学んだこと、そして後に教員として勤めた経験は非常に大きいです。灘校は、生徒に対しても教員に対しても「自由」を許容してくれる校風がありました。もちろん全てがそうではありませんが、自由度は格段に高かった。その環境が自分には合っていました。
——灘校での学びの中で、特に印象に残っていることはありますか。
歴史との出会いです。中学から高校まで日本史を教わった先生が本当に素晴らしい方で、その影響で歴史研究を志すようになりました。後に自分が教員になったときも、日本史を担当しています。中学1年から高校3年まで、一貫してその先生から歴史の面白さを教われたのは、本当に幸せな経験でしたね。
——どのような授業だったのでしょうか。
その先生は、いわゆる年号や単語の暗記といった授業は一切しませんでした。歴史的な出来事が「なぜ起きたのか」という背景や因果関係を、非常に時間をかけて丁寧に解説されるんです。重要なポイントはじっくりと、逆に「ここは読めばわかるだろう」というところは大胆に省略する。メリハリの利いた授業でした。
そして何より、一方的な教え込みではなかった。「君はどう思う?」と常に生徒に問いかけ、質問を歓迎し、対話の中から学びを深めていくスタイルでした。私はその授業が大好きでしたね。
——ご自身で考えること、対話を通じて学ぶことの面白さに、その授業で目覚められたのですね。
ええ。今でも、その先生が高校の卒業文集に寄せてくれた言葉を覚えています。「後の世代の方が優れているに決まっているのだから」と。ご自身も東大で歴史を学ばれ、いわば研究の第一線にいた方なのに、決して偉ぶることがない。次の世代の方が自分たちより優れているはずだし、そうでなければ人類は進歩しない、と。だから、中高生の拙い意見にも真剣に耳を傾ける。その姿勢は、教育の本質そのものだと感じました。次の世代を尊重する。それは私自身、教員になってからも、ずっと大切にしている考え方です。
次回は彼のジェンダー研究との出会いを伺います。