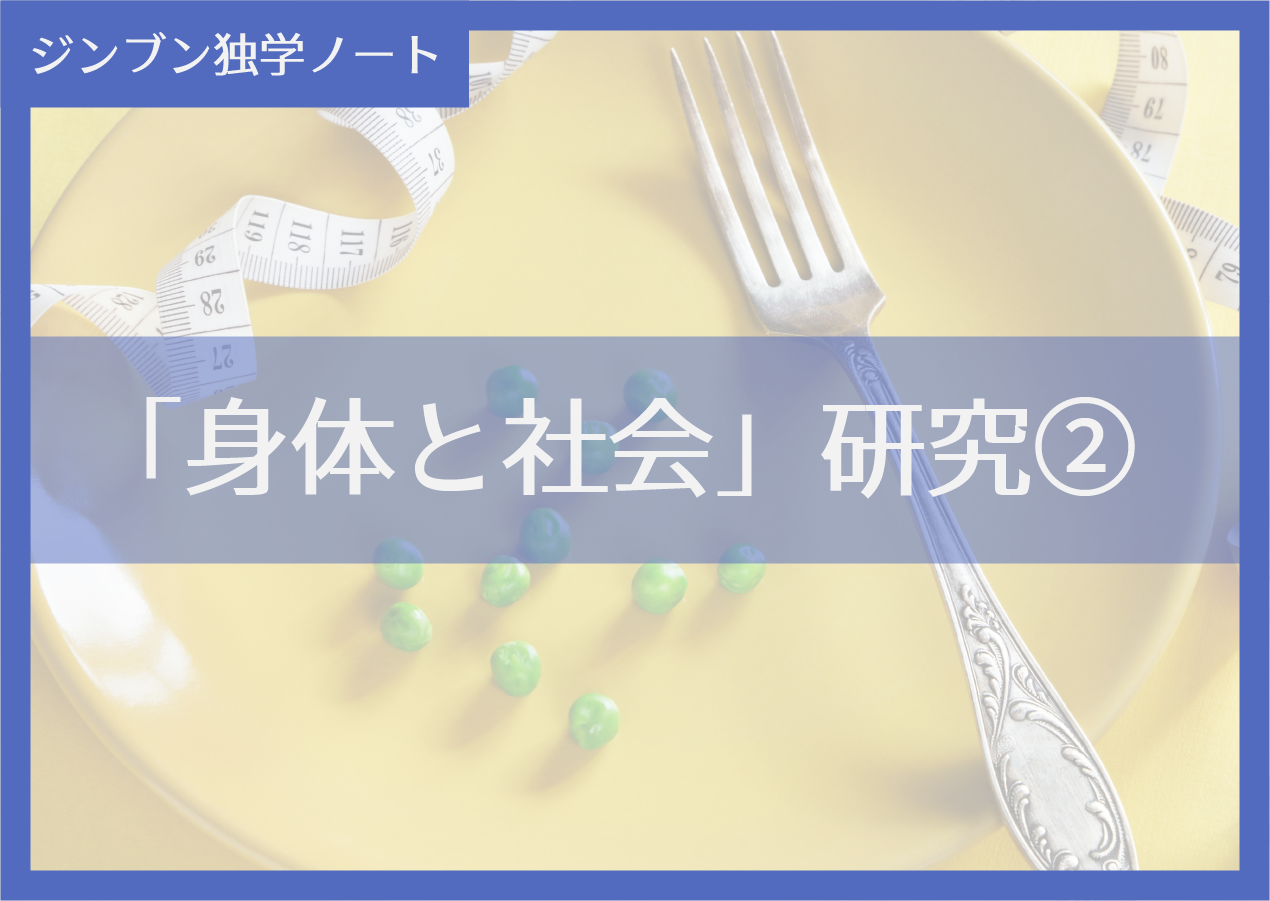ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十三回となる今回のインタビューでは、山田理絵先生にお話をうかがいます。山田先生は東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属共生のための国際哲学研究センター(UTCP)上廣共生哲学講座の特任助教として、摂食障害やタトゥーの研究を行う傍ら、シンポジウムやワークショップの企画を行っていらっしゃいます。
進学先と将来のビジョン
——留学生活から帰ってくると、そろそろ高校卒業後の進路を考える時期ですね。山田さんは大学進学を選ぶわけですが、また意外な進学先ですね。
留学前は心理学や精神医学など、人の心にかかわる分野を勉強したいと思っていたわけですが、高校時代の留学経験でまた私の考えがかわり、結果的に一浪して筑波大学の国際総合学類に進学しました。
国際総合学類には単位が互換できる留学制度があること、社会科学と自然科学を中心に文理の壁を超えて様々な科目が学べることに魅力を感じました。
——進学してみて、どんな学生生活でしたか?
同級生や先輩方が将来に対する具体的なビジョンを持っており、入学当初から大変刺激を受けました。「国連に就職したい」、「難民支援に携わりたい」、「自分で団体を立ち上げたい」など、みんな明確な目標があって、それに向かって本当に真摯な態度で勉強をしている方ばかりという印象を受けました。
友人たちと比べた時、私の問題意識や将来のビジョンはぼやけているのではないか、と思いました。
まあ、今思えば、大学時代は「モヤモヤ」しながら、少しずつ問題意識を明確にしていく期間という位置付けでも別に問題ないと考えますが、当時の私は浪人期間があり、優秀で活動的な同期に囲まれて、一人で焦っていたのでしょうね。
そんな中で、新しく興味をそそられる学問に出会いました。たまたま社会学類が開講していた社会学の授業を履修して、研究対象へのアプローチの仕方が私にとって斬新でとても衝撃を受けました。
——どんなところに衝撃を受けたんでしょうか。
子どものころから、心理学や精神医学に近い分野にはずっと興味はあったけれど、大学では結局その分野を専門とはしませんでした。なので、そのような分野とは今後関わらずに生きていくと思っていました。
ところが、社会学関連の講義を受けて、医療社会学という分野があることを知りました。社会科学の立場から、医療のあり方、精神的・身体的な病気、死などについてアプローチする研究があるということで、大変関心をもちました。医療社会学の講義を聞いて、病気や死というものが社会や文化の影響を受けて形作られているという発想、そしてそれを具体的に研究する方法論を学びました。
特に、「構築主義」という立場で医療や病気を捉える議論がとてもユニークで魅力的に映りました。
——ちょっと難しい用語が出てきました。ぜひ解説お願いします。
社会学者の赤川学先生が、構築主義のことを「ある事象Xは、自然的/客観的実在というより/ではなく、社会的に構成されたものである」という認識の形式を共有しているように思われる」とおっしゃっています(赤川 2001: 63)。
例えば「病気」について考えると、それが確固たる実体をもつ、所与のものとして存在するとみなすことが多いですが、そうではない可能性があります。異なる地域に生きていれば、あるいは、もしも現代とは異なる医療制度が発展していたら、病気の概念も違っていたかもしれない。
とくに精神疾患の場合、何が正常で何が異常とみなされるかは、社会や文化によって変化します。ある地域や時代には「病気」とみなされていなかったことが、別の地域や時代では病気・疾患として扱われることがあるでしょう。ちなみに、命の危険が生じるほどに食物を摂らない(いわゆる拒食)や、明らかに大量の食物を摂る(いわゆる過食)も、近代以前には「病気」という枠組みではなく、宗教的な枠組みで語られたり、「変な人」、「特殊な人」のようなニュアンスで報道されることがありました。
構築主義の立場で病気を研究する場合、基本的には、私たちが現在馴染みのある病気の概念が歴史的にどのような経緯で成立してきたのか、そこにどのようなアクターが関わってきたのか、といったことついて研究します。
いま私たちが「当たり前」だと考えているものが、歴史的にみると異なったあり方が見えてくるのは、病気に限ったことではありません。例えば「家族」もわかりやすい例だと思います。現代の日本の人々の多くにとって親しみがあるであろう「家族」のかたちも、時代や地域が異なれば、まったく違う形であったはずです。
入門編の社会学の授業で学んだこと、すなわち、所与のものを疑い、自分が「現実」だと思っていることを、歴史的・文化的に相対化してみるという試みはとても魅力的に思いました。
—— 確かに「疑っていい」って、ものすごいインパクトですよね。
そうですね。新しい理論を知ることは、世界を見る新しい眼鏡を手に入れることです。「こういう見方で社会を見ることができるんだ」というワクワクがありました。
次回は今に至る研究テーマについて伺います。