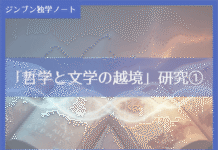ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十三回となる今回のインタビューでは、山田理絵先生にお話をうかがいます。山田先生は東京大学大学院総合文化研究科・教養学部附属共生のための国際哲学研究センター(UTCP)上廣共生哲学講座の特任助教として、摂食障害やタトゥーの研究を行う傍ら、シンポジウムやワークショップの企画を行っていらっしゃいます。
これまでの歩み
Q1. 本日はどうぞよろしくお願いします。まずは、山田さんの研究テーマについて教えてください。
よろしくお願いします。
私は、社会学の立場で研究を行ってまいりました。修士課程から現在まで一貫して取り組んでいるのは、精神的な疾患として取り扱われている食行動の異常、すなわち「摂食障害」の研究です。この摂食障害について、歴史に関する調査とインタビュー調査を行ってきました。
——摂食障害の研究をされているということは、医療や心理学などを学んだ経験もあるのですか?
いえ、医学や心理学を専門として学んだわけではなく、医療関連の資格はありません。社会学の理論や方法論を使って、医学や心理学に関連する事柄を対象として研究するというスタンスです。
——ありがとうございます。では、ここからは、そのテーマに行きつくまでの道すじをひもといていきたいと思います。山田さんは、どんな子どもでしたか? どんな教科が好きだったかとか……
どの教科もまあまあ好きでしたが、体育は苦手でした(笑)。跳び箱は最後まで跳べなかった記憶があります。
教科とは少し違いますが、小学生の頃は漢字を覚えることが好きで、確か四年生のとき漢字検定の二級を取りました。
もう一つ幼少期の関心について思い出したことを話していいですか?
——ぜひお願いします。
小学生の頃は心理学に関心を持っていました。
入り口は、大衆向けの心理テストの本やテレビ番組でした。ラジオの放送大学で心理学に関連する講座を聞いていた時期もありました。誰でも聴けるもので、番組表から心理学に関連しそうなものを探して聞いていました。心理学の専門的な議論を聞いてみたくて、内容が全部わかるわけではないのですが、講座を聴きながらノートを取ってみたりしていました。
——漢検もそうですが、興味がわいたことは、学校の授業以外でも勉強していたんですね。
そういう側面はあったと思います。小学校の時、とある好きな漫画があり、日本史に関心をもちました。歴史の授業のノートを一生懸命作っていたこともありましたね。
そういえば、苦手なのは夏休みの宿題です。漢字ドリル、計算ドリル、天気の記録に朝顔の観察…。毎年8月末は恐ろしいことになっていましたね。