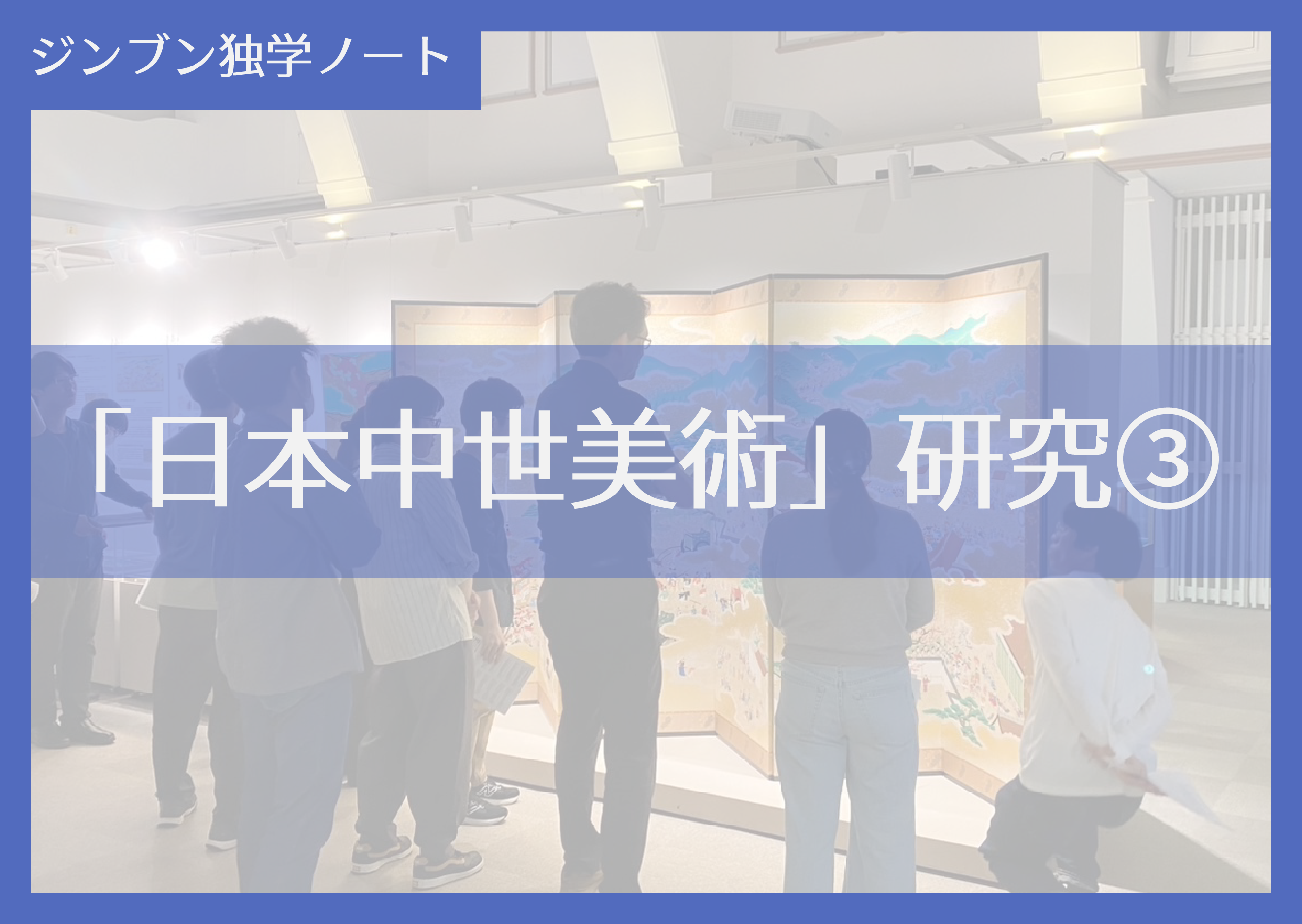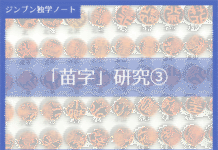──多くの仮説と格闘しながら研究を進めるなかで、どのようなときに楽しさを感じますか。
高階秀爾先生がピカソの例で書いていた[1] 高階秀爾『ピカソ―剽窃の論理』(筑摩書房、一九六四年)。ことなのですが、「作品や芸術家のこの謎を解き明かせたのは、過去も今も自分しかいないんじゃないか」と思える瞬間はやはり興奮があります。先行研究を調べても誰も言っていないとなると、「これは大きな発見かもしれない」と。ただ、すでに何人もの先輩たちが捨てた説を自分が拾って「大発見だ!」と勘違いしないようにも気をつけています。
三十代までは自分の業績に対して評価やリワードをもらうことが続きましたが、四十代になるといろいろな方にお世話になってばかりで、恩返しのような形で論文を書く場面が増えてきました。書くことは大変な作業ですし、依頼が来てもネタが思いつかないときは行き詰まります。
最近は久しぶりに長めの論文を研究室紀要の『美術史論叢』[2] … Continue readingに載せました。これは依頼ではなく、純粋に自分が書きたくて書いたもので、自由研究のような位置づけです。調べていくうちに面白くなって、どうしても世に出したいという気持ちに駆られました。絵師にまつわる言説をまとめて、古代から近代までを縦横に取り上げた連載にするつもりです。日本美術史の地下水脈を掘り起こすイメージですね。毎年の年末ごろに締め切りがあることによって何とか書けますし、自発的に書く論文には独特の楽しさがあります。
──自分で書きたいテーマと、依頼されるテーマには違いがあると思いますが、どのように捉えていますか。
与えられたテーマでも、そこに自分の関心を組み合わせることで新しい発見が生まれることがあります。ただ、それはあくまで「フレームを与えられて初めて起こる」ことで、結局は単発の仕事の集合体になりがちですね。私は手元に“ネタ帳”的なものを持っていて、話が来たらそこからアイデアを出すのですが、今回『美術史論叢』に載せたものは、依頼が来ないであろうテーマなので、自発的に始めたわけです。
自費出版でも何でもいいから、自分で作品を発表し続けられる人こそ“創作意欲を処理するため”の行為を実践していると言えるかもしれません。昔の職人は「誰かに頼まれるのが当たり前」でしたが、その中でも創作意欲を何らかの形で盛り込んでいた。私にとって自発的に書く紀要論文は、“作品性”の高いものなんです。
依頼された仕事はクライアントの満足度を優先せざるを得ないので、どうしても「落としどころ」を探って終わる形になりやすい。でも今回の論文は「読んでほしい!」と、いろんな人に配っています(笑)。
四十代くらいになると「自分の書くパターン」が見えてしまって、それが面白くない。書く前から仕上がりが想像できると自分としてはつまらない。クライアントは満足してくれるかもしれませんが、もっとクリエイティブにやりたい気持ちが出てくる。二十代、三十代の頃は「たくさん書いて自分のクリエイティビティを発揮したい」というエネルギーに溢れていました。
──今後やってみたいこと、取り組んでみたいことがあればお聞かせください。
定年まであと十二年ほどあるのですが、十二年前はちょうど東大に来た頃で、あっという間でした。これからは、世に博士論文を出すサポートをしたい。私の学生や、何らかの形で指導に関わる学生たちが博士号を取っていくプロセスを見届けたい。できれば、ある程度の数と質の論文を生み出して、それが一冊目の著書としてまとまるところまで。
私が大学院生だった一九九〇年代は、課程博士という制度が日本でようやく整備されはじめた時期でした。それ以前、文系の世界では博士論文は定年退官前の大家が著作をまとめて出すものだ、という空気でした。一方、理系では、博士論文は研究者のスタートラインであり、国際的にも博士号を取得するのが当たり前。ずっと前からアメリカでは、文系・理系にかかわらず博士号を取らなければ大学教授になることはできないのが普通でした。私が二〇代のころに、日本でも方針が変わり、博士論文にチャレンジできるようになったのは運が良かったと思っています。
ですから、これからの若手にも博士論文を書く経験をしてほしい。大変だけれども、一本一本がそれぞれの学問分野の底力になるからです。私自身は広い分野に興味がありますが、最近はまた中世日本美術史に回帰していて、最終的には学問分野の根幹に関わる貢献がしたい。自分の研究を後世の誰かが読んで「これ面白いじゃないか」と思ってもらえるようにせねばと思っています。
──実際に研究をアウトプットするうえでの喜びや工夫について、もう少し具体的に教えてください。
人文系の研究って、どうしても「宿題をこなす」感覚になりがちなんです。でも、そこにクリエイティブな喜びをうまく導入できれば、研究がもっと豊かになる。特に編集という作業は、作る喜びに直結するんじゃないでしょうか。文章全体の構成やシステムを練り上げるのは、一種のデザインともいえます。超人的な生産力を持つ方もいますが、普通はみんな試行錯誤しながらやっている。そこにテクノロジーがうまくアシストとして入れば、楽しくて質の高いアウトプットがもっと増えるかもしれないですね。
──本日はありがとうございました!
こちらこそありがとうございました。