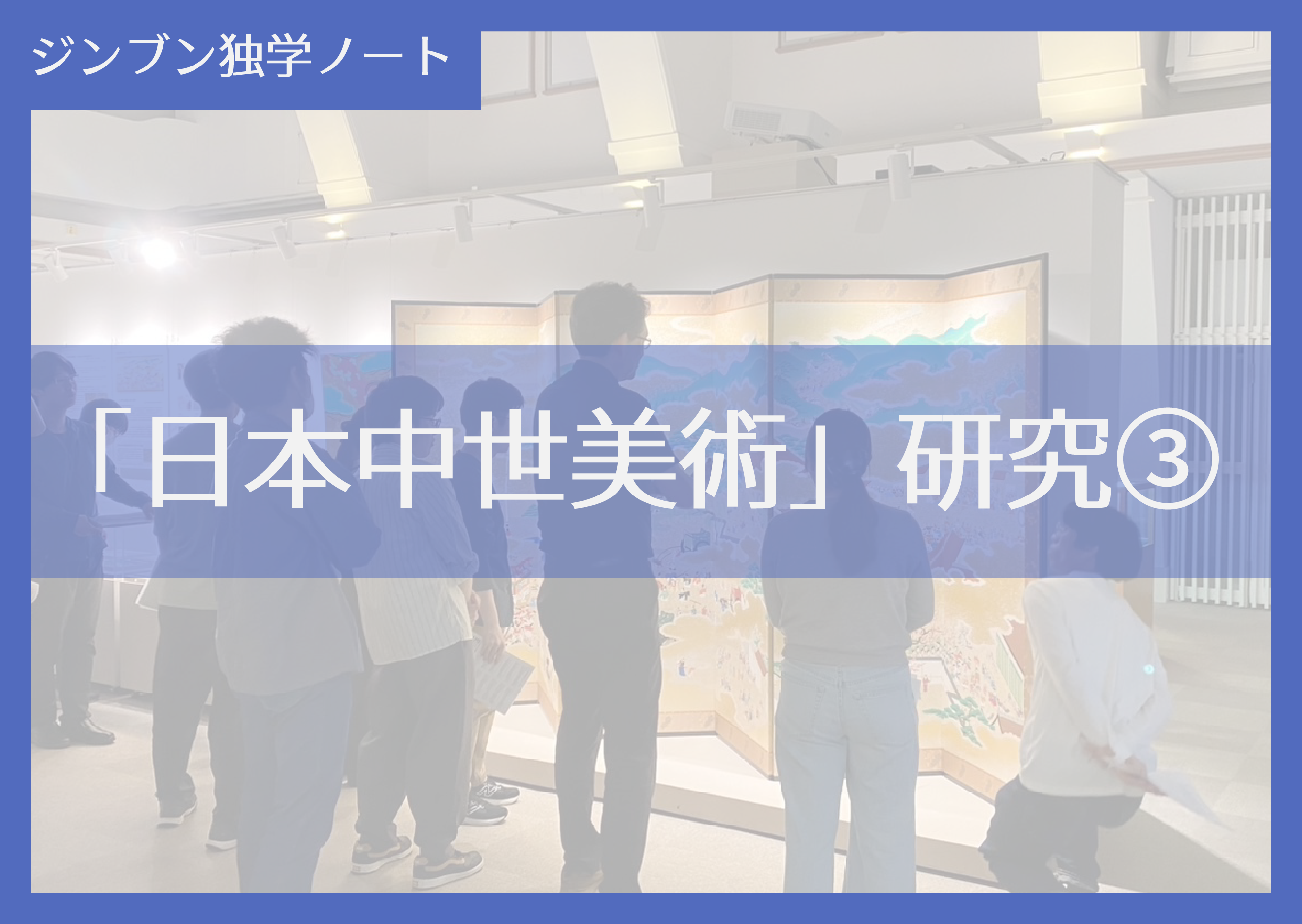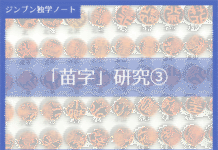ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十二回となる今回のインタビューでは、髙岸輝先生にお話をうかがいます。髙岸先生は日本美術史、特に中世絵画史を専門とする東京大学の教授です。平安時代に始まるやまと絵が中世社会でどのように展開したのかを、絵巻や障屏画などの作品と史料から探求しています。特に絵巻の研究に力を入れており、国内外の作品調査も行っています。主著に『室町王権と絵画―初期土佐派研究―』、『室町絵巻の魔力―再生と創造の中世―』、『中世やまと絵史論』があります。
研究の進め方
Q3. 中世の作品を研究される際の手順についてお聞かせください。
基本的には作品を中心に考えることから始まります。まずは現存する作品をひとつ決めて、それに関する情報を集めます。写真や画像、情報が出回っていない場合は、美術館やお寺に調査を依頼して調査・撮影を行い、一次情報を取得しますし、作家に関する本や論文も集めていきます。先行研究である程度わかっている部分と、自分が+αで何を言えるかの見取り図を描き、新規性の部分を探します。状況によっては実際に作品を調査しながら、仮説を百くらい立てて、その中から一、二個を残して残りを捨てる。選んだ一、二個の仮説を裏付けるために情報を集め、最終的に仮説を組み立てて論文にまとめていきます。
仮説を通して既存の作品や絵師の位置づけが変われば、その周囲も少しずつズレていきます。ズレる範囲の大小、従来の全体構造がどこまで変わるかが示せると、“報告”ではなく“論文”と言えるようになる。論文が十個ほど集まって時代や地域の幹の形が変わったときは、新しい森の形を提示したことになるので、それを本という形で世に出すわけです。
──仮説を立てる際には、どのような観点で進められるのですか。
年代を絞り込んでいく作業が一番多いですね。例えば、従来は一四〇〇年代とされていた作品を「実は一三五〇年頃ではないか」と示したい時は、まず「一四〇〇年頃の他作品と似ていない」ことを証明します。そのうえで「一三五〇年頃のこれと似ている」と示すために、当時の社会状況やパトロンが存在し得るかどうかを確認する。画家やパトロンの候補を出しながら「弟子の作かもしれない」「息子の作かな」「似た画風の別グループかな」などと様々な可能性を検討します。様式的には近いけど決定打に欠ける、といったときはさらに仮説を狭めたり広げたりしていきます。
足利義満[1] … Continue readingのように「パトロンのキャラクターが作品に反映されている」という仮説もあり得ます。渋めの趣味ならならこの人、金ピカならあの人かも、というような絞り込み方ですね。作品が大幅な改変を受けていない限り、「いつどこで誰が資金を出して描かせ、今のお寺に伝わっているか」が一点に収斂するはずです。消去法で「京都の可能性は高いが奈良は薄いな」といった形で切り分けていくこともあります。
ちなみに、私が卒論で扱った「日月山水図屛風」は一五世紀から一六世紀頃とされていて約二百年の幅があったんです。情報が少なくて苦労しました(笑)。それ以来、データがもう少し多い作品を選ぶようになりましたね。
References
| ↑1 | 足利義満(一三五八~一四〇八)。室町時代第三代将軍。南北朝の合一を果たし、幕府の全盛期を現出する。武家と公家を融合した新たな政権を確立し、その邸宅であった北山殿の遺構が金閣である。いわゆる北山文化の中心人物とされ、日明貿易を介した中国美術のコレクションを築き上げた。 |
|---|