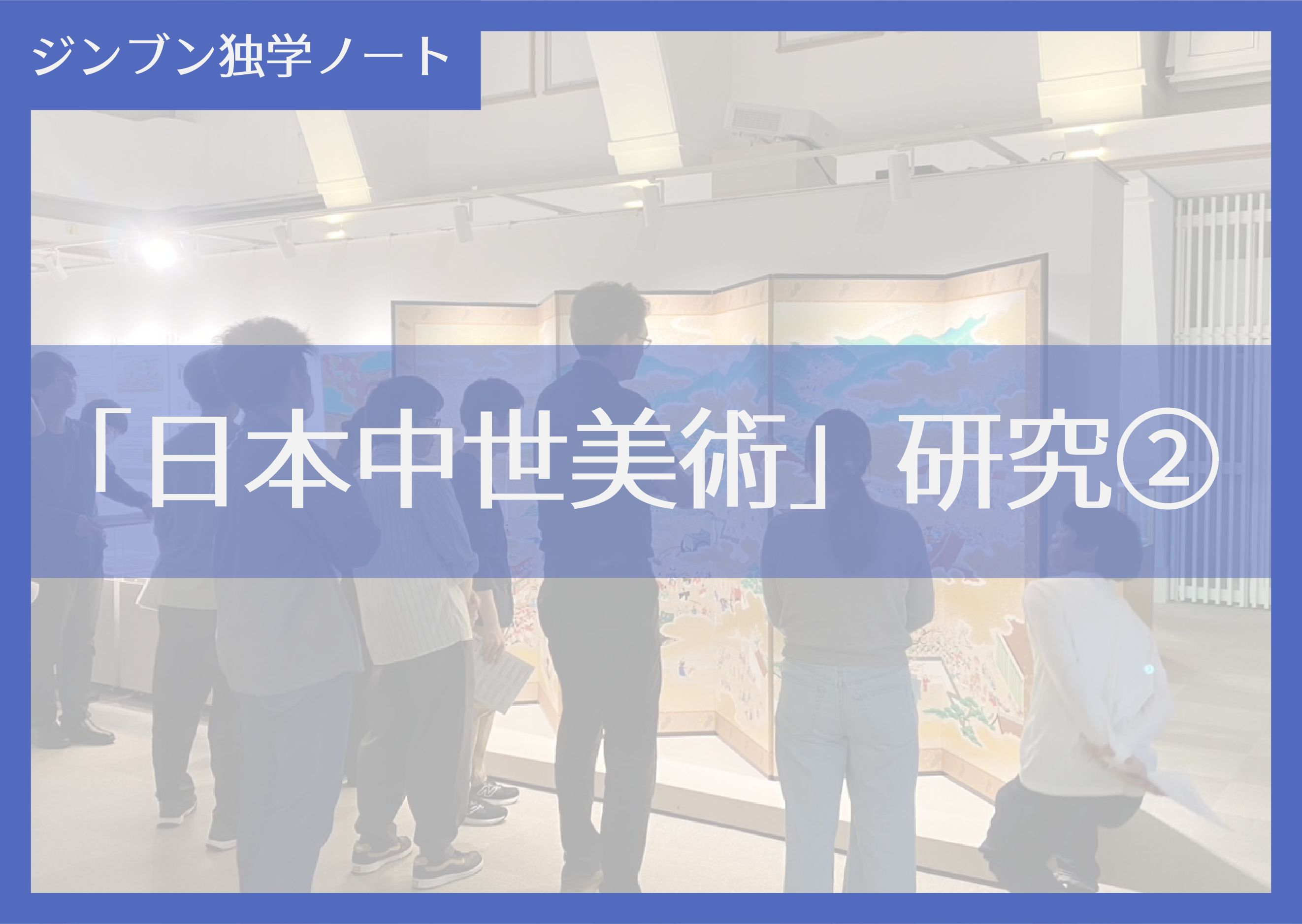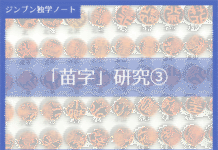——日本美術に親しみを持ったのは、なにか特別な理由があったのでしょうか。
はっきりしたきっかけがあって、「日月山水図屏風」(金剛寺蔵)[1] … Continue readingの存在です。金剛寺は大阪の河内長野市にあって、東京でいうと八王子や青梅のような山の麓ですね。私は小学三年生から高校卒業まで河内長野で育ちましたから、この作品は地元の名品として親しみのある存在でした。平安前期の「如意輪観音像」(観心寺蔵)[2] … Continue readingという仏像も市内にあって、こちらも同じように地元を代表する名品です。
そして、小学校四年生のときにNHK大河ドラマ「おんな太閤記」(橋田壽賀子さん脚本)を熱心に見るようになって、戦国時代や武士の世界に興味を持ちました。歴史の全集を参考に甲冑を段ボールで自作したり、新聞の折り込みチラシの裏の白紙を取っておいて、合戦図や清和源氏の系図を写したりしていましたね。小五の頃には「自分の専門は武士の時代、源平合戦から大坂夏の陣まで、つまり中世だ」と勝手に決めていました(笑)。
振り返ってみると、小四からずっと四〇年くらい「美術史の真似事」を続けているようなものです。中世へのロマンを感じる原点はそこにあります。実際に専門的な研究を始めたのは大学に入ってからですが、卒論では「日本の中世をやろう」と決めていて、最終的に自分の地元にあった「日月山水図屏風」をテーマにしました。
——先生は「好きなこと」と「研究対象」が必ずしも直結しているわけではないと仰っていましたね。そこはどんなふうにお考えなのでしょう。
究極的に「何がいちばん好き?」と聞かれたら、おそらく私は自分でデザインをしたり何かを作ったりするほうが好きかもしれないです。「美術史研究者という職業が自分にとって一番好きか?」と言われると、ちょっと分からない。二番手か三番手くらいかもしれません。
ただ、本や論文を書くことは「作品を作る」ことだと思っていて、そこには確かに創造性や悦楽があります。加えて、この仕事に伴う“ご褒美”みたいなものもあります。例えば調査や研究で旅行に行ったり、美術館や寺社、教会を巡ったりする機会がある。それも楽しみのひとつですね。本を出す際には装丁にもこだわりたくて、表紙や紙の質感、重さなどを編集者と相談しながら決めます。それが唯一の“ものづくり”の要素かもしれません。しかし一生で何十冊も本を出せるわけではないので、実際に手を動かしてものを作り上げている人たちに対する憧れは常にあります。
——研究者として歩む道を選んだ背景には、ご家庭の影響もあったのでしょうか。
父は化学の研究者で、大学の教師をしていました。河内長野市に引っ越す前、小学三年生までは堺市にある大学の官舎に住んでいて、そこは大学関係者ばかりが集まるやや特殊な環境でした。ちょっと変わった大人たちが周りにたくさんいて(笑)、父の大学にもよく遊びに行っていたので、私にとって大学は身近で居心地のいい場所でした。
研究室があって、そこに大学生や大学院生がいて、彼らが家に遊びに来るのを見ていると、「大学の先生という仕事」が具体的にイメージできました。逆に会社勤めをする大人をほとんど知らずに育ったので、自営業の家の子供が親の仕事を継ぐのと似た感覚かもしれないです。官舎の友達のお父さんも若手研究者だったりして、彼らの楽しそうな姿を見ているうちに、「自分も大学教師になって研究がしたいな」とごく自然に考えるようになりました。単純に、大学という場所が好きだったんでしょうね。
最終回は実際の研究の手順について伺います。