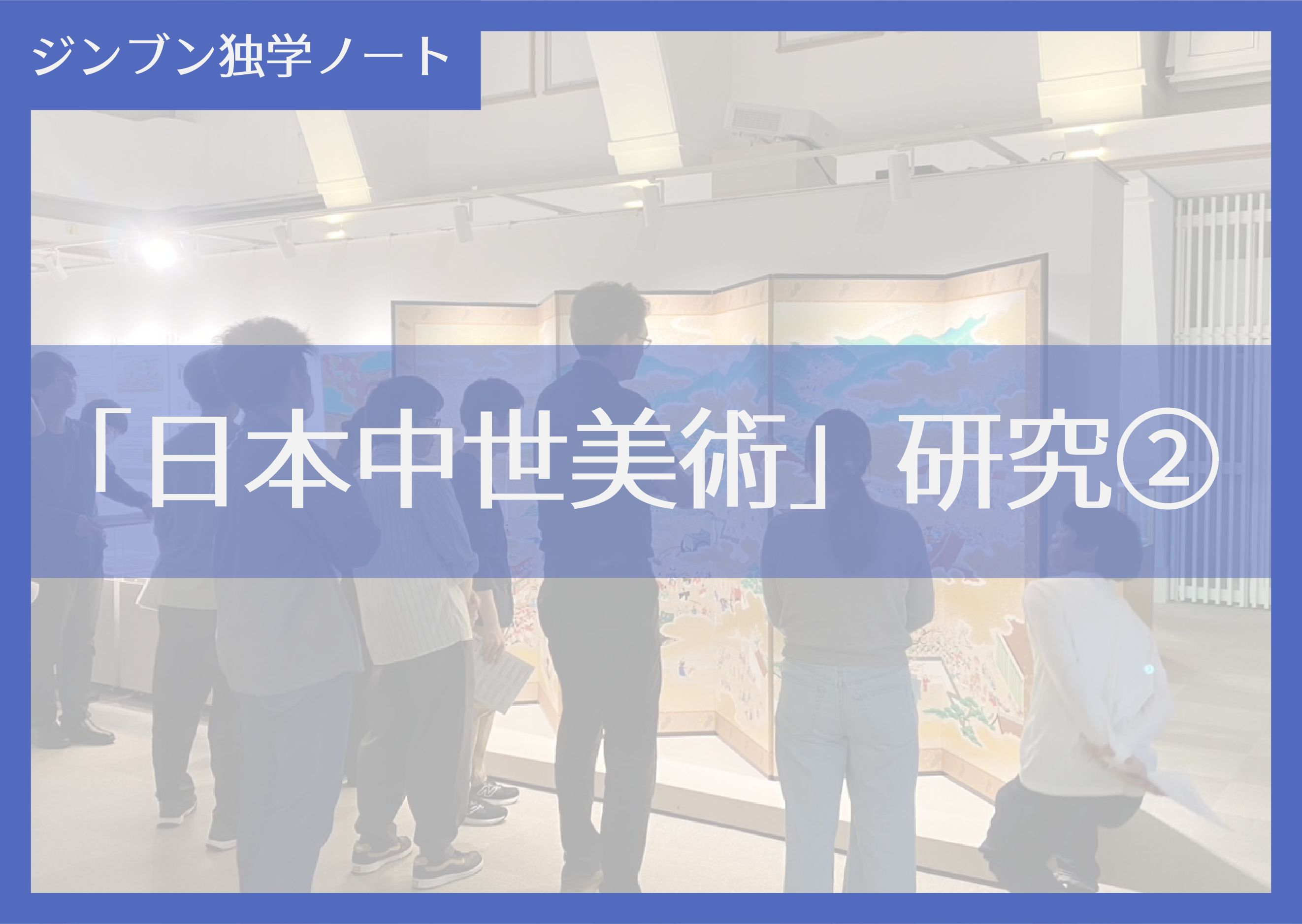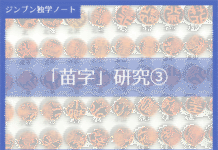ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十二回となる今回のインタビューでは、髙岸輝先生にお話をうかがいます。髙岸先生は日本美術史、特に中世絵画史を専門とする東京大学の教授です。平安時代に始まるやまと絵が中世社会でどのように展開したのかを、絵巻や障屏画などの作品と史料から探求しています。特に絵巻の研究に力を入れており、国内外の作品調査も行っています。主著に『室町王権と絵画―初期土佐派研究―』、『室町絵巻の魔力―再生と創造の中世―』、『中世やまと絵史論』があります。
これまでの歩み
Q2. 作品を広い文脈で捉えようとされる姿勢は、先生のデータベースや海外調査への関心とも関係がありそうですね。
まさにそうです。絵はそれ単体で存在しているだけではなく、互いに関係しあうデータベースの一部としても捉えられますし、寺院や美術館自体もいわばデータベースだと考えられます。日本美術史では国宝級の名品ばかりが注目される傾向もありますが、そうした名品が活きるのは脇役となる多数の作品があってこそ。作品を群として見てこそ初めて浮かび上がってくる大きな構図があります。
日本美術と外国との関係を考えても、文化や地理的な背景が異なるなかで、共通点と相違点の両方を常に意識していきたい。互いに違う世界をもっていながら、根底ではどこか通じ合うところがある。そうした関係そのものが興味深いと感じています。
——共通性と異質性を意識するようになったきっかけは何だったのでしょう—か。
藝大に入って初めてイタリア美術などの西洋美術に触れたことが大きかったですね。学部生の頃、イタリア美術史の辻茂[1] 辻茂(一九三〇~二〇一七)、東京藝術大学名誉教授、イタリア美術史。著書に『遠近法の発見』(現代企画室、一九九六年)。先生と佐々木英也[2] … Continue reading先生がいらしたのですが、私自身はボッティチェリやミケランジェロといった名前は知っていても、世界史をちゃんとやっていなかったので彼らの位置づけはよく分からなかった。藝大生は昔からみんなイタリアが好きで、先輩も同級生も多くがイタリア美術史を専攻し、実技の学生もイタリアに旅をして、「イタリアこそが美の基準だ」というような雰囲気がありました。
私は絵巻や屏風など、子供の頃から近畿地方の文化財に親しみがあったので、それらと一三~一五世紀イタリアのフレスコ画を比較すると、「確かに質感が似ているな」と感じました。油彩画のテカテカした質感に対し、フレスコは漆喰の壁に描いた絵なのでやまと絵のざらざらした感じと近く、ジョットなどの作品にはヘタウマのような雰囲気もある。イタリア・ルネサンスでも、一五世紀初め頃の作品には素朴な味わいが残っていて、「同じ時期の日本の絵画と比較して見てみたい」と思い始めました。
大学院に入った夏、院試で勉強した西洋美術史の作品を実際に見たくて初めてヨーロッパを一周したのですが、その頃からイタリアの一三~一五世紀作品を意識して見て、「この絵の作者は日本でいうと誰と同時代くらいだろう?」と考えるようになりました。当時の日本とヨーロッパの間には直接の交流はありませんでしたが、「中世的なるもの」「ルネサンス的なるもの」は日本美術のなかにもあるのではと感じ始めていました。
もし藝大で最初に触れたのが中国美術だったら、日本美術との直接の影響関係で考えていただろうと思います。しかし私の場合は、環境的な理由もあってイタリアがきっかけになりました。最初にフランス美術やドイツ美術に出会っていたなら、フランスにあるバイユーのタペストリー[3] … Continue readingを日本の絵巻と比べたり、ドイツのデューラー[4] … Continue readingの作品と日本の肖像画や風景表現を比較したりと、違う切り口が生まれていたかもしれません。ただ、これは今だから言えることで、二〇代の頃はほぼイタリアのルネサンス前後を意識しつつ日本美術を見てきたと言うことになります。
References
| ↑1 | 辻茂(一九三〇~二〇一七)、東京藝術大学名誉教授、イタリア美術史。著書に『遠近法の発見』(現代企画室、一九九六年)。 |
|---|---|
| ↑2 | 佐々木英也(一九三二~)、東京藝術大学名誉教授、イタリア美術史。著書に『聖痕印刻―ジョットの後期壁画をめぐって』(中央公論美術出版、一九九五年)。 |
| ↑3 | フランス・ノルマンディーのバイユー大聖堂に所蔵される刺繍の絵。天地約五〇センチ、長さ六〇メートルを超える絵巻状の画面に、ウィリアム征服王による一〇六六年のイングランド征服の物語を描く。平安時代の絵巻と類似する。 |
| ↑4 | アルブレヒト・デューラー(一四七一~一五二八)。ドイツルネサンスを代表する画家。ニュルンベルクを拠点とし、イタリアにも遍歴してルネサンス絵画を学ぶ。実感的な遠近法や精緻な肖像画に特徴がある。 |