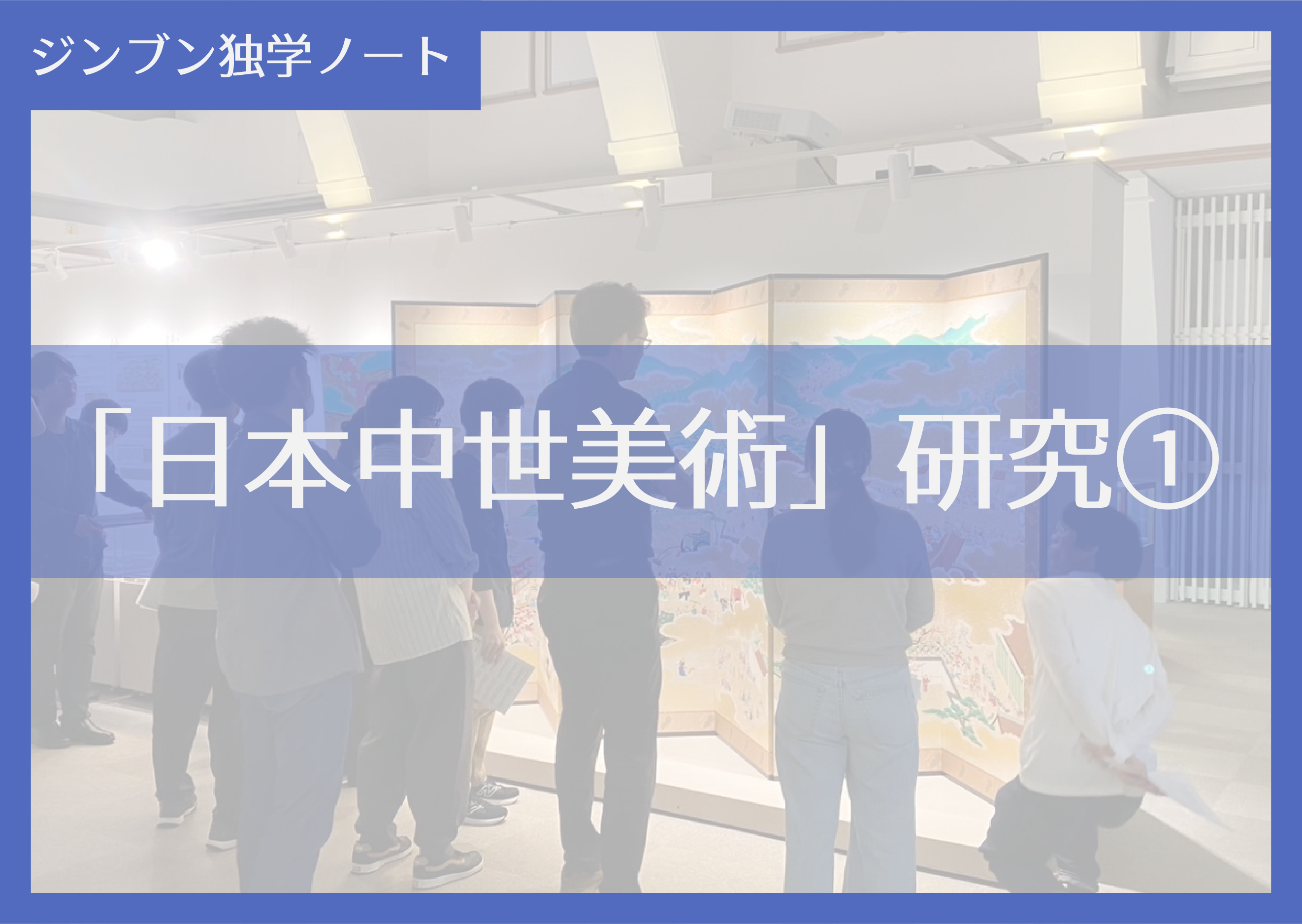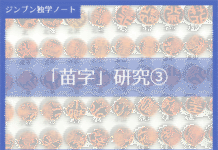——先生のこれまでの経歴をうかがいたいのですが、美術史の道に進まれたきっかけはどのようなものだったのでしょうか。
子供のころから美術には興味がありました。高校二年生くらいで将来の進路をどうしようか考えたとき、「美術をやりたいな」と思ったんです。国語、英語、理科、社会といった科目の中で、図工や美術がいちばん好きでした。美術を専門的に探究するなら東京藝術大学に行きたいと思い、美大受験の予備校に通いました。はじめは工業デザイン、特に自動車のデザインをやりたかったので、デザイン科のクラスを受講していました。
一九八〇年代の末ごろ、芸術系の大学ではデザイン科が人気で、藝大のデザイン科は倍率が五〇倍ほど。二浪や三浪は当たり前という雰囲気でした。予備校でも浪人生たちのすごく上手いデッサンや色彩構成が講師の先生に厳しく評価されていて、「合格するレベルに達するにはかなり時間がかかるな」と感じました。しかしどうしても藝大には行きたい。そこで、実技の配点よりも学科試験に重きがある「芸術学科」というのを見つけ、「とりあえずここに入ればアートに関わる仕事はできるかもしれない」と考えました。われわれは団塊ジュニア世代で、高校は一学年六〇〇名以上と大規模でしたので、大学は小規模で密度の濃いところに行きたいという気持ちもありました。当時、藝大の美術学部は一学年が二三〇名ほど、芸術学科は二〇名でしたので小さなカレッジという感じでしたね。
——幼い頃から制作の実技もお好きだったそうですね。そのあたりは研究にも通じるのでしょうか。
物心ついたころから工作をよくしていましたし、今もものを作ることに対する関心があります。作品調査で写真を撮る時もこだわりますね。美術史の資料として写真を撮るとはいえ、過去の文化財と現代の撮影技術のコラボレーションという面があるので、そこには幾ばくかの作品性があると思っています。
私が藝大で指導を受けた田口榮一先生は撮影やカメラに精通されていて、学部生のころから調査に同行し、見よう見まねで写真を習いました。一九九〇年代前半に美術史を学び始めた頃はデジタル写真は存在せず、すべて銀塩のフィルムでした。ただ、当時のリバーサルフィルムの解像度でも作品の画像は美しく、「写真の力ってすごいな」と感じていましたね。その後、二千年前後にデジタルとアナログの入れ替わりを経験できたことも大きかった。古いアナログ技術の片鱗を知りつつ、新しいのテクノロジーのありがたみもわかる。現在のデジタルカメラでも、シャッタースピード、絞り、ISO感度といった基礎の部分はフィルムカメラの原理や操作を継承している部分が多々あります。一方でデジタルならではの解像度や画質の向上は日進月歩です。技術の継承と進化を肌で感じることは、私自身がやっている研究とも深い部分でつながっています。
テクノロジーへの関心やものづくりへのこだわり、昔は不可能だったことが可能になる瞬間への驚きは、絵巻や仏像を作ってきた昔の人々も同じように抱いたのではないかと思います。中国からもたらされた新しい技術に興奮した人々の姿が想像されますし、師匠から弟子への技術の伝承というのもずっと続いてきたことで、人間と技術の関係というのは面白い。また、美術史のベースは歴史学でもあるので、私としては美術作品を通じて、それぞれの時代の社会を理解したい。たとえば、かつて絵を描くとか彫刻を彫るという行為は、現代で言えばAppleやGoogleの最先端技術と同じような意味を持っていたはずです。だからこそ技術的な変化を時間軸の中で捉えていきたいんです。
次回は日本美術への親しみの話について伺います。