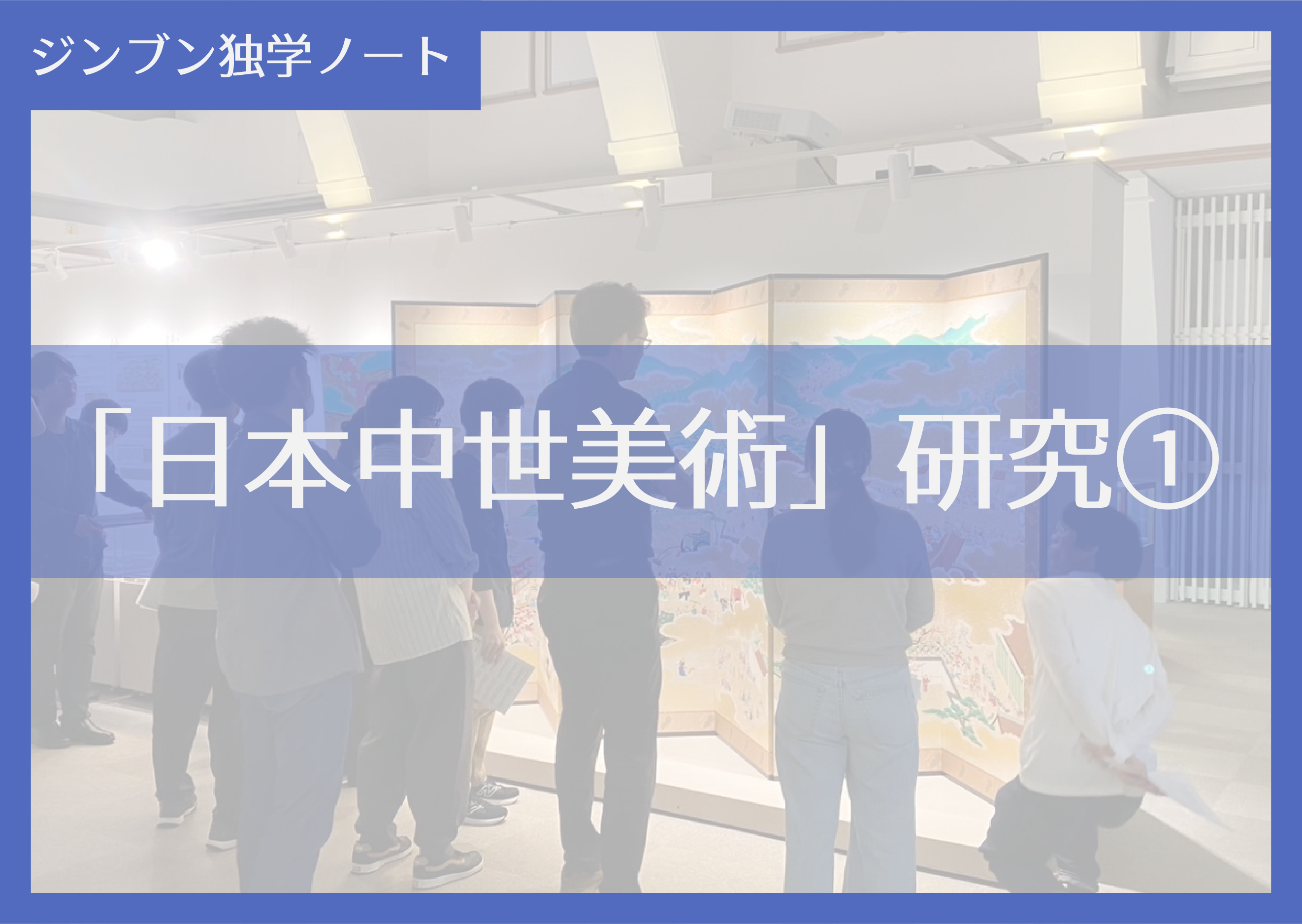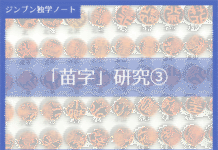——理論と実技を行き来することで、理解が立体的に深まるわけですね。
五つ目は、海外における日本美術コレクションについての研究です。専門とする中世だけではなく近世や近代の美術品も多く含まれており、ここから外交と美術というテーマも浮上します。江戸時代末期、徳川幕府と欧米列強の国々との間で美術品のやり取りが行われていました。その時に幕府が贈った屏風などがフランスのフォンテーヌブロー宮やドイツ、オランダに遺されていることが明らかになり、現地調査を進めています。
また、アメリカのボストン美術館が所蔵する日本美術作品群の調査にも取り組みました。ここに蓄積された日本美術は世界屈指の質と量を誇り、平安末期の「吉備大臣入唐絵巻」[1] … Continue readingから明治維新後の一九~二〇世紀の作品まで時代の幅も広い点が特徴です。しかし収蔵庫のなかには、まだ十分に調査されていない作品が数多く残されています。一九九〇年代から鹿島美術財団が研究助成を行って日本美術諸分野の専門家を一、二ヶ月ほど派遣し総合的な調査を継続してきました。私は二〇一九年に派遣され、二週間で二百巻ほどの絵巻を調査しました。それまで三〇年以上重ねられてきた先輩研究者たちの調査成果とともに、二〇二二年に報告書を上梓しました。
——すごい規模ですね。最初は一五世紀の日本美術から始まり、そこから広がっていったと。
このように、最初は十五世紀前後の日本美術の研究が中心だったのですが、時代的にも地理的にも関心が拡張しています。時代としては平安から明治あたりまでを対象にしています。絵画の技術的な部分への関心やコレクションの調査は、何らかの御縁があってお声がけいただくことが多いですね。
美術史の他分野の研究者からのお誘いもありますし、情報工学の研究者や海外の日本学研究者など、足場を異にする方々との御縁もできました。一五世紀の日本美術史もかなり広い分野なので、さらに深めていくこともできますが、他分野の仕事でも依頼があれば断らないようにしています。雑食性と言ってもいいかもしれません。隣接する分野の研究者と一緒に研究に取り組み、彼らの仕事ぶりを見ることで、美術史の守備範囲が明確になるとともに、自分自身の得意分野も分かってきます。
例えば作品様式分析や技法解析の話、画家の活動のありようを論理と感覚を交えて言語化することは自分のポジションだな、という具合に。サッカーのプレイヤー十一人はFW、MF、DF、GKに分かれていますが、それぞれが動く場所がおおまかに決まっているのと似ているかもしれません。美術史のなかなら、私は十五世紀が得意で、他の人はそれよりも前の時代、国文学の人となら私は絵で彼らはテキストで、というふうに境界線の可視化が行われます。違うポジションの人々と一緒にやることでお互いの住み分けが明確になるとともに、方法論の違いも分かってくるという面白さがあります。
References
| ↑1 | 黒田日出男『吉備大臣入唐絵巻の謎』(小学館、二〇〇五年)、辻惟雄、アン・ニシムラ・モース『ボストン美術館日本美術総合調査図録』(中央公論美術出版、二〇二二年)。 |
|---|