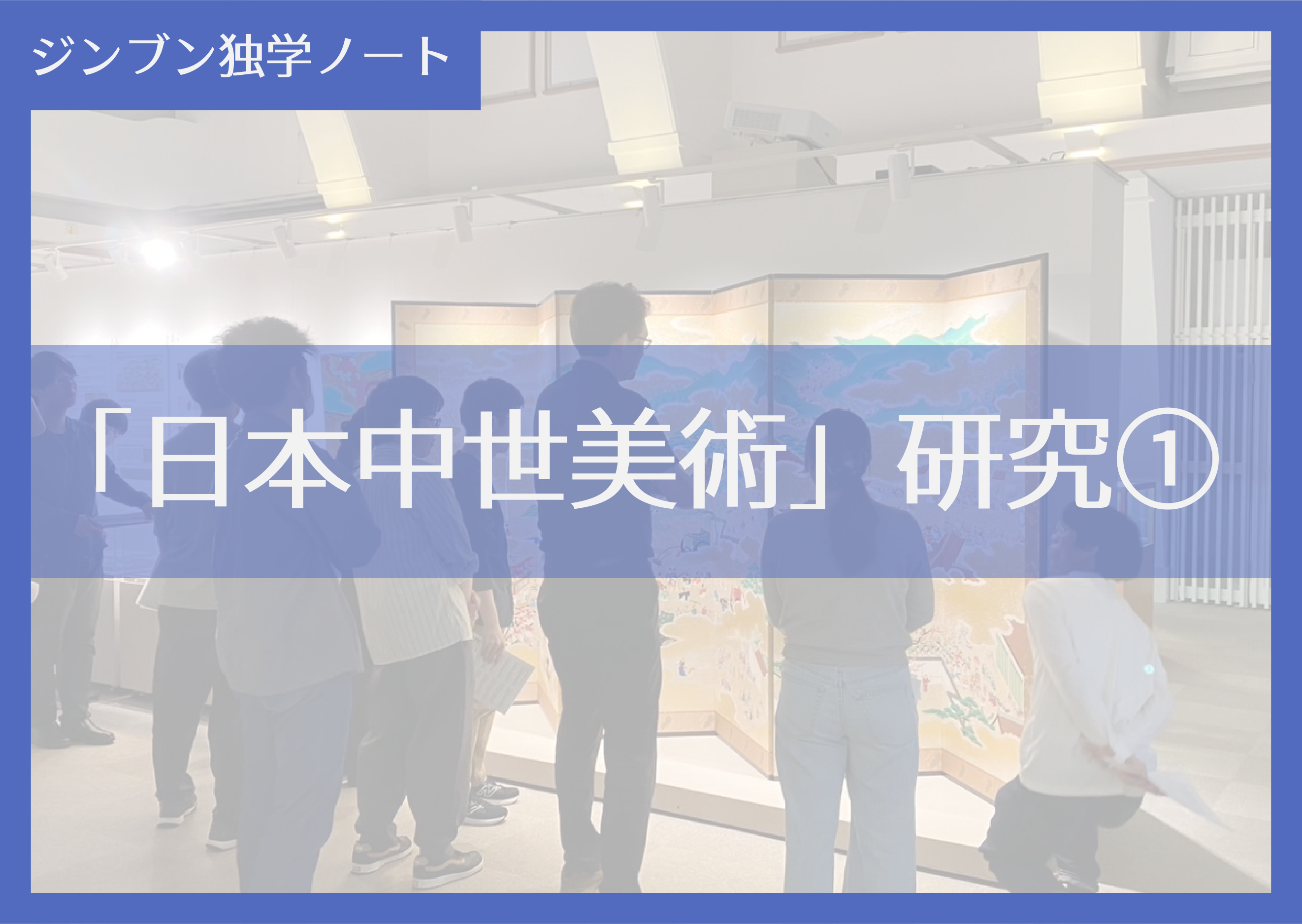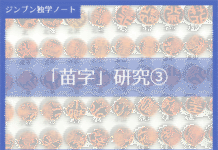ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十二回となる今回のインタビューでは、髙岸輝先生にお話をうかがいます。髙岸先生は日本美術史、特に中世絵画史を専門とする東京大学の教授です。平安時代に始まるやまと絵が中世社会でどのように展開したのかを、絵巻や障屏画などの作品と史料から探求しています。特に絵巻の研究に力を入れており、国内外の作品調査も行っています。主著に『室町王権と絵画―初期土佐派研究―』、『室町絵巻の魔力―再生と創造の中世―』、『中世やまと絵史論』があります。
これまでの歩み
Q1. 本日はどうぞよろしくお願いします。現在研究されているテーマについてお聞かせください。かなり多岐にわたると伺いましたが、まず全体像をうかがえますか。
こちらこそよろしくお願いします。いくつかの研究対象や方法を同時並行で行っており、現在は五つの方向性があります。周辺分野の研究者と科研費などの共同研究をすることが増えるにつれて、関心が広がっています。
——なるほど。五つもあるとのことですが、順番にお話しいただけますか。
一つ目は、大学院の頃から関心がある中世の絵巻物や肖像画や屏風などについてです。このような作品群が室町時代にどのように制作されたのか、つまり誰が描いて、誰がお金を出して、どのように主題が選ばれたのか。土佐派などの絵師集団や、歴代の足利将軍をはじめとするパトロンの活動を研究しています。
——制作の裏側や構造を紐解くことで、美術作品の背景が見えてきそうですね。
二つ目は、デジタルヒューマニティーズに関する研究です。IIIF(トリプルアイエフ、世界共通の画像公開規格)を活用した美術作品の様式比較、具体的には、絵巻物の顔の判定などのツール開発を行っています。情報工学の研究者と協力しながら行っており、彼らに「このようなツールがあると役に立つ」と伝え、実装してもらうという形です。
——情報工学の専門家との連携があるのですね。次のテーマはいかがでしょうか。
三つ目は、美術史と伝統的に関連の深い日本史(中世史)、日本文学(中世文学)、仏教学との共同研究です。美術作品は歴史・宗教・文学のいずれかに関わっています。隣接分野とともに絵巻を読み解く研究を行うこともあり、その際、テキストは文学研究者が、絵は私が、それぞれの専門の見地から分析する、というやり方です。
——それぞれの専門分野が組み合わさると、新しい視点や発見も期待できそうですね。
四つ目は、美術史と美術の制作・実技との関わりについてです。例えば、中世の屏風を復元する時に、私は時代考証的な部分、作品の時代背景や絵師それぞれの特徴を踏まえた指摘を行い、実際の復元作業は現役の日本画家の方々が伝統的な材料と技法で行います。美術史に基づく考証と、彼らが積み重ねている技術的な観点からの考察とをあわせることで、新たな作品理解の視点が現れてきます。