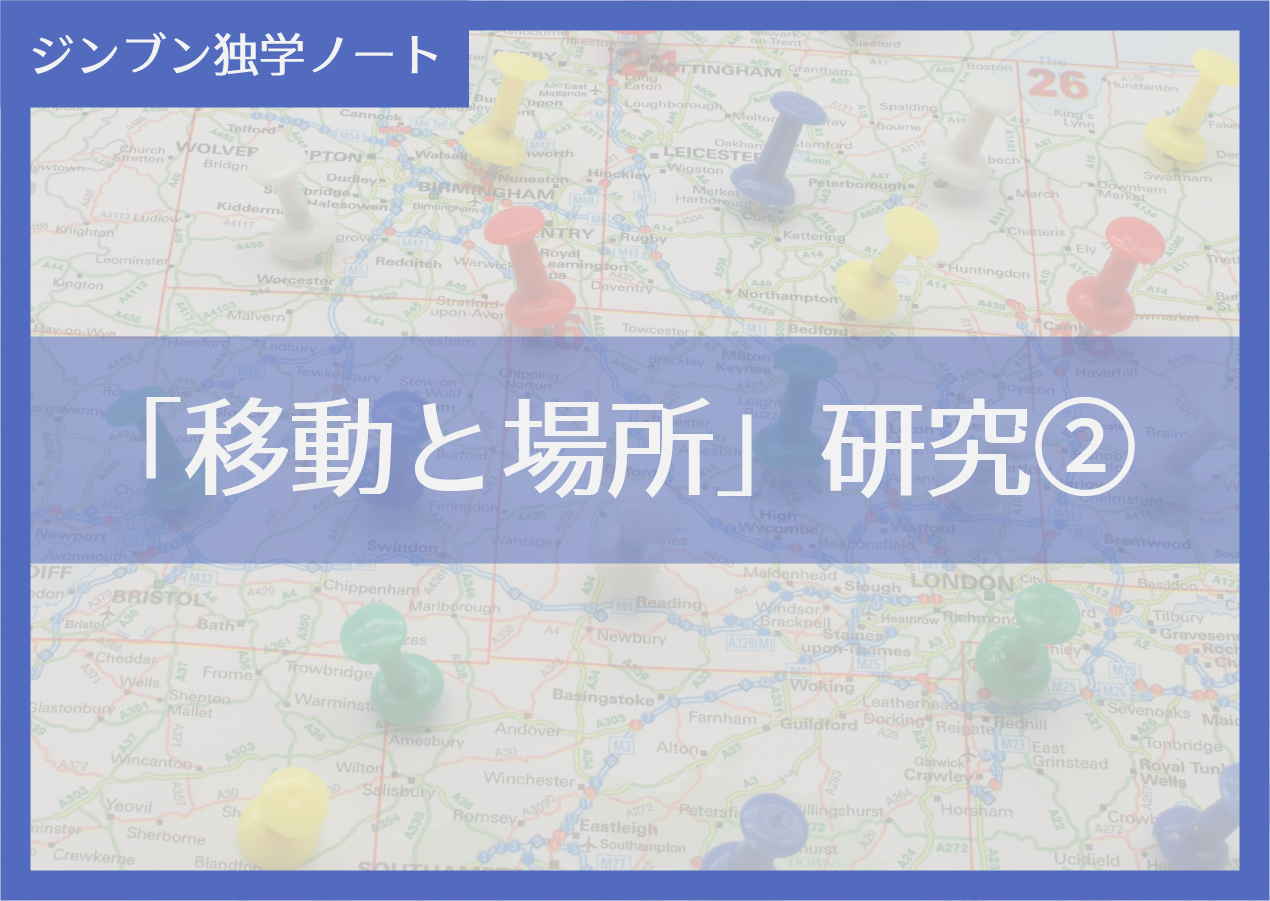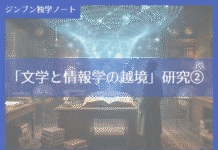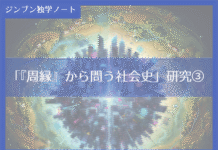ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十七回となる今回のインタビューでは、現代人の「移動」と「場所」との関わりをテーマに研究を進める、東京大学の住吉康大さんにお話を伺います。人文地理学の視点から、フィールドワークや「日記調査」といったユニークな手法で人々の生の声に耳を傾け、固定観念としての「場所」を捉え直す、その独自の研究アプローチに迫ります。
「移動」と「日記」が拓く、場所の新たな捉え方
——研究テーマとして「移動」に着目されるようになったのは、どのような経緯からですか。
進学後、クラスメートと話す中でやはり価値観の違いを感じることがありました。駒場で生まれ育ち、スケートボードで通学しているような友人に地元への愛着を話しても、なかなか理解されない。「効率を考えれば東京にいるのが一番いいんじゃないか」と言われ、憤慨したこともあります。
当時は2015年頃で、「地方創生[1] … Continue reading」が大きなテーマになっていた時期です。その流れもあって人文地理学への関心も深まったのですが、一方で、IターンやUターンを増やすといった移住者の奪い合いのようなゼロサムゲームで自治体が疲弊するだけでは意味がない、とも感じていました。
そんな時、二つの大きな発見がありました。一つは、杉並区で生まれ育ち、地元を心から愛している友人と出会ったことで、自分は田舎出身だから地元愛が強いのだと思い込んでいたことに気づかされました。「東京がブラックホールのように人口を吸い込んでいる」と悪者にするのも短絡的だと。
もう一つ、授業でオーストリアのチロル地方の話を聞きました。都会に暮らしながら、アルプスに小屋を持ち、二つの拠点を行き来するライフスタイルがある、と。こういう暮らし方が日本でどれだけ可能なのか。そう考えたのが、卒論で千葉県の南房総市周辺をフィールドに、平日は東京や横浜で働き、週末などに千葉で海や山のレジャーを楽しむという「二地域居住」をテーマにした最初のきっかけです。
——そこから、博士論文では「日記調査」というユニークな手法を取り入れられていますね。地理学の研究では珍しいアプローチのようですが。
二地域居住から、さらに複数の場所を移動する「多拠点生活」へと関心が移っていきました。ただ、コロナ禍で直接会いに行くのが難しくなり、オンラインでのインタビューにはどこか消化不良な感覚がありました。
何より、移動している人がそれぞれの場所で何を感じるのか、そのリアルタイムの感覚が知りたかった。後から振り返ってのインタビューでは、どうしても理由付けされた綺麗な物語になりがちです。もっと生の、リアルタイムの経験を捉える方法はないか。そう考えた末に、地理学の研究で使われる手法かどうかはあまり考えず、「日記を書いてもらおう」と思い至りました。必要に迫られて、ですね。
——実際に日記を分析してみて、いかがでしたか。
あちこち移動しているのだから、場所に関する記録で溢れているだろうと期待していたんです。でも実際は、「今日は仕事が進まなかった」「集中できなかった」といった、ごく日常的な記述がほとんどでした。中には夏休みの宿題を思い出していただけたらわかるように、日記を書き続ける負担は大きいので、徐々に文章量が少なくなることもありました。それはそれでリアリティがあって面白いのですが、場所に関する話は、あくまで時々差し込まれる程度。それが大きな発見でしたし、まとめる上での難しさでもありました。
でも、そのおかげで見えてきたこともあります。あえてこちらから「場所について書いてください」と指定しなかったことで、日常の中に場所がどう現れるかが見えてきました。例えば、ある場所の印象が、前回訪れた時と今回とで全く違う。その理由が、場所そのものではなく、本人の精神状態だったり、たまたま一緒に滞在していた人が違ったりすることに起因する。
これは、近年の人文地理学で言われている「場所を固定的に捉えない」という考え方にも通じます。場所とは、単なる緯度経度の位置(ロケーション)だけではなく、そこに関わる人やモノ、出来事といった、一時的な関係性の束として立ち現れる、という議論です。理論としては知っていましたが、日記調査を通して「ああ、こういうことか」と、体験として感じることができたのは大きな収穫でした。
最終回は今後の探究について伺います。
References
| ↑1 | 東京一極集中や地方の人口減少にともなう課題に対処するために2014年に提唱された、地方自治体の自律的な取り組みを支援する一連の政策のこと。 全国の約半数の自治体が将来的に消滅する可能性があるとの警鐘を鳴らした同年の「増田レポート」を受けたもので、日本の地方政策の大きな契機となった。 |
|---|