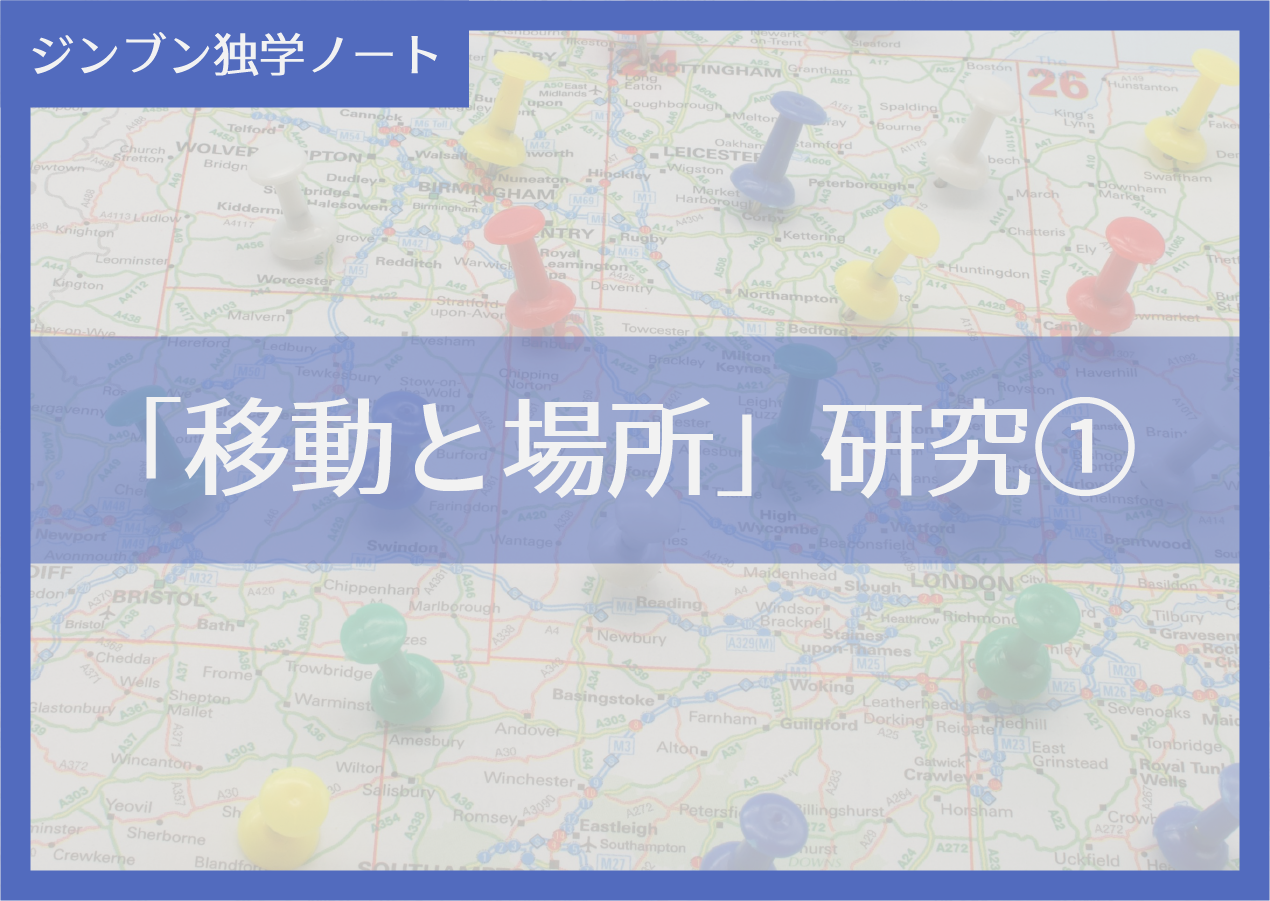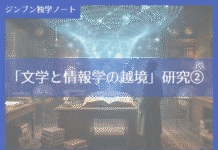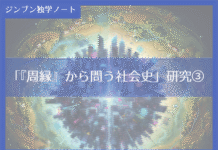ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第十七回となる今回のインタビューでは、現代人の「移動」と「場所」との関わりをテーマに研究を進める、東京大学の住吉康大さんにお話を伺います。人文地理学の視点から、フィールドワークや「日記調査」といったユニークな手法で人々の生の声に耳を傾け、固定観念としての「場所」を捉え直す、その独自の研究アプローチに迫ります。
探究心の源流、人文地理学との出会い
——本日はどうぞよろしくお願いします。今回は、住吉さんが専門とされる人文地理学の世界と、そこに至るまでの歩みについて、じっくりとうかがっていきたいと思います。まず、住吉さんが専門とされる人文地理学とはどのような学問なのか、教えていただけますか。初見の方には「人文」と「地理」がなかなか結びつきにくいかもしれません。
関心という点では本当に幅が広いです。今、大学院生が15人ほどいますが、その研究テーマも、大都市におけるお墓の分布と今後の高齢化社会での変容、離島の漁業や山間部の柑橘農業、あるいはアニメーションのようなコンテンツ産業と、実にさまざまです。
そもそも地理学という分野は、大きく「自然地理学」と「人文地理学」に分かれます。高校生の皆さんには、ケッペンの気候区分などを学ぶ自然地理学の方が馴染み深いかもしれません。それに対して人文地理学は、人間と空間の関わりを幅広く対象にする学問と言えます。人間は生まれ落ちると、どうしても場所を取り、空間との関わりが生じます。産業的な意味での空間もあれば、生活に関わる空間もある。そうした人間と空間の多様な関わりを研究する分野だと考えています。
——なるほど。自然地理学が少し引いたマクロな視点から世界の成り立ちを見るのに対し、人文地理学はより「生きている人」の側から、その関わりを眺めていくようなイメージでしょうか。
そうですね。実は、学校で学ぶ地理は、自然地理・人文地理のほかに「地誌学」の側面も強いんです。地誌学は、例えば「アメリカの地誌」のように、一つの地域を自然環境から文化、歴史、産業まで含めて、視点を限定せずに多角的に掘り下げていく分野です。
それに対して人文地理学は、もう少しミクロな視点や、特定の視点から物事を見渡すことができます。よく「鳥の目、虫の目」と表現しますが、人文地理学はどちらかといえば「虫の目」を重視します。人々の生活に寄り添いながら、特定の視点から空間と人間の関係性を見つめ、つなげていく。そんな特徴があると思います。中高生の皆さんも、教科書の中で知らず知らずのうちに、この人文地理的な視点に触れているはずですよ。
——だんだんイメージが湧いてきました。住吉さんがこの人文地理学の世界に進むまでには、どのような道のりがあったのでしょうか。ご出身は鹿児島県と伺っています。
とにかく「なぜ?」と問わずにはいられない子供でした。小さい頃、近所に並んでいる車の中で一台だけワイパーの形が違うのが気になって。親が「そういうのは、メーカーに自分で問い合わせてみればいいんじゃない?」と面白がって後押ししてくれたこともあり、知らないことを自分で調べる姿勢はその頃から育まれたように思います。
あるいは、原風景的なものへの興味でしょうか。なぜこの景色に自分は心を動かされるんだろう、と考えることがよくありました。そして、地域を元気にしたいという思いも、なぜか昔から強かったようです。小学校の自由研究では、5年生も6年生も社会科をテーマにしました。当時はなぜか農業や食料自給率に関心があって、家畜の飼料を国産の米や雑穀で賄えないか、農業試験場に話を聞きに行ったり。また、地元の特産品だった「サワーポメロ」という柑橘が大好きで、これをPRするにはどうすればいいか、農家の方にインタビューして回ったりもしました。今やっていることと、ほとんど変わりませんね。地元愛というか、地元の良いものを、もっと良くしたいという気持ちがなぜか強くありました。
——ご自身の探究心と地域への思いが、研究の原点になっているのですね。そこから大学への進学という、大きな環境の変化があったわけですが。
そこは意外と切り離して考えていました。内側から見ているだけでは分からないこともある。一度外から地元を見て、その上でもう一度考えることが大事なのではないかと。高校の同級生に、僕以上に地元愛が強くて「絶対に鹿児島大学に行く」と譲らない優秀な友人がいました。地方の進学校だったので、先生たちは「行けるやつは東大を受けろ」という雰囲気で、彼の選択が学年全体の士気に関わる、と先生たちの間で問題になったこともありました。
その彼と放課後によく話した記憶があります。「都会でしか見られないもの、全国からいろんな人が集まってくる場所でしか得られない経験も、きっとあるんじゃないか」と。それは自分自身にも言い聞かせていた言葉だと思います。もちろん、一番良い大学に行きたいという素朴な気持ちもありましたが、地元を捨てるというよりは、いずれ地元に還元できるものを探しに行く、という感覚でした。
——大学入学当初から、地理学を志していたのですか?
いえ、まったく。どの学部に進むかも決められないまま来た、というのが正直なところです。とりあえず文科一類に入って、そこから考えればいいだろう、と。進学振り分け[1]東京大学の前期課程(1・2年生)の学生が、後期課程(3・4年生)で進む学部・学科を選択する制度。現在は「進学選択」と呼ばれる。が迫ってきた大学1年の後半から2年生にかけて、本格的に進路を探し始めました。
まず法学部はないな、と思いました。地元への関心から「官僚になればいい」と勧められてもいたのですが、授業で法律を学んでみると、法律の歴史や判例の解釈など、どうも自分のやりたいこととは違う。幼少期からの「自分で調べたい」という精神と、すでにある判例に基づいて判断していく法学の世界に、少しギャップを感じてしまったんです。もっと自分で足を使って動ける学問がいいな、と。そうやって色々な選択肢を見ていく中で、たまたま人文地理学にたどり着きました。学問そのものへの興味というよりは、フィールドワークが必須であるなど、その「学び方」に強く惹かれたのがきっかけです。
——東京での暮らし自体が、ある種のフィールドワークのようだったのでは?という気もします。地方出身者としては、価値観の違う人たちに囲まれて戸惑うことも多かったのでは?
その点は、僕は鹿児島県の県人寮に住んでいたので、少し特殊かもしれません。プライベートな空間では、飛び地のように地元を引きずっていました。個室はあるけれど、風呂や台所は共同。そこでは鹿児島弁が飛び交い、先輩後輩の厳しい上下関係もあって、お互いの部屋に鍵もかけずに行き来するような、本当にオールドスタイルの生活です。ですから、大学でカルチャーショックがなかったわけではありませんが、自分の生活圏もまた特殊な世界だったので、うまくバランスが取れていたのかもしれません。
次回は移動の新たな捉え方について伺います。
References
| ↑1 | 東京大学の前期課程(1・2年生)の学生が、後期課程(3・4年生)で進む学部・学科を選択する制度。現在は「進学選択」と呼ばれる。 |
|---|