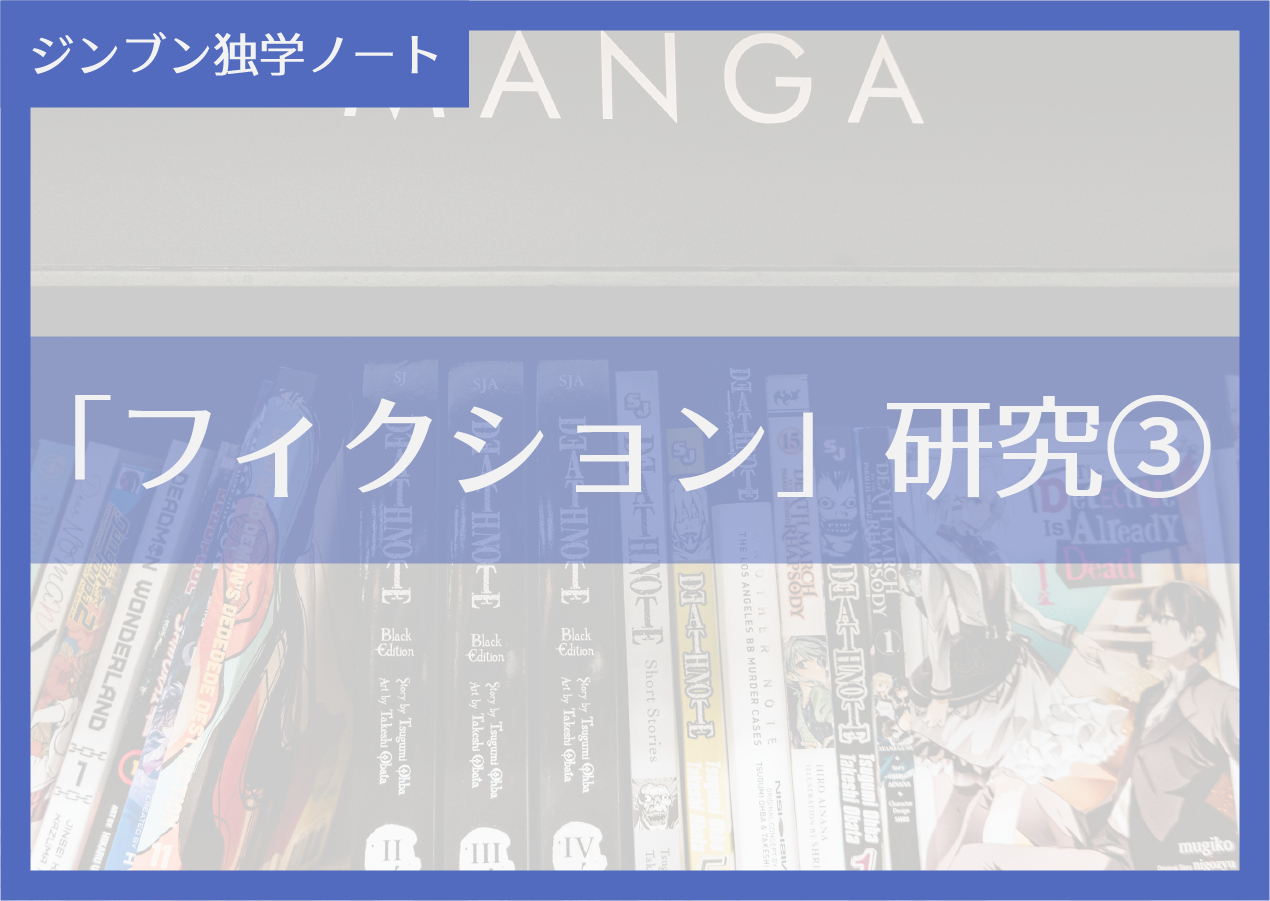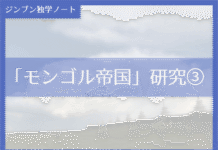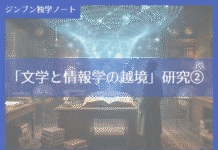Q3-2. 「想像的抵抗」「想像的抵抗」なる概念についてはなんとか理解できました。ではそのような研究にはどのような意義があるのでしょうか?
人間の心の働きは心理学や神経科学などでも研究されています。そのような研究は仮説を立てて、現実の実証的なデータで検証するという形を取ると思います。哲学の役割(の一つ)はそのような経験科学的な研究の一歩手前、つまり仮説形成に必要な概念や理論を構築することにあります。
私は今回「想像的抵抗の問題」を研究することで、「フィクション」や「想像」といった概念を分析し、明確化したと言えます。それは人間文化や人の心の働きに関する理論構築の一助となるものなのです。
Q3-3. 分析美学の営みを色々と聞くことができて楽しかったです。最後に、研究をしていてどんなところが楽しいでしょうか。
自分が何となく感じてはいたけれど言語化できていないものを、先行研究が見事に説明していたときなどは面白いですね。たとえば登場人物に「感情移入する」とよく言うが、具体的にはどういうことなんだろう?と疑問に思っていました。これが美学や心の哲学の分野で「シミュレーション」という概念で深く議論されていることを知り、面白く文献を読んでいます。
また、「フィクションが影響を与える」という言い方をしたりもしますね。分析哲学の営みは、「フィクションとはどういうこと?」「影響を与えるとはどうやって?」などを1つ1つ検証していく作業になります。私たちが生きている生活実践・社会実践を明確に記述することができるという点も、分析哲学の面白さであり、役に立つ点だと思っています。
―― あまりなじみのない分野でしたが、拝聴してとても参考になりました。どうもありがとうございました!