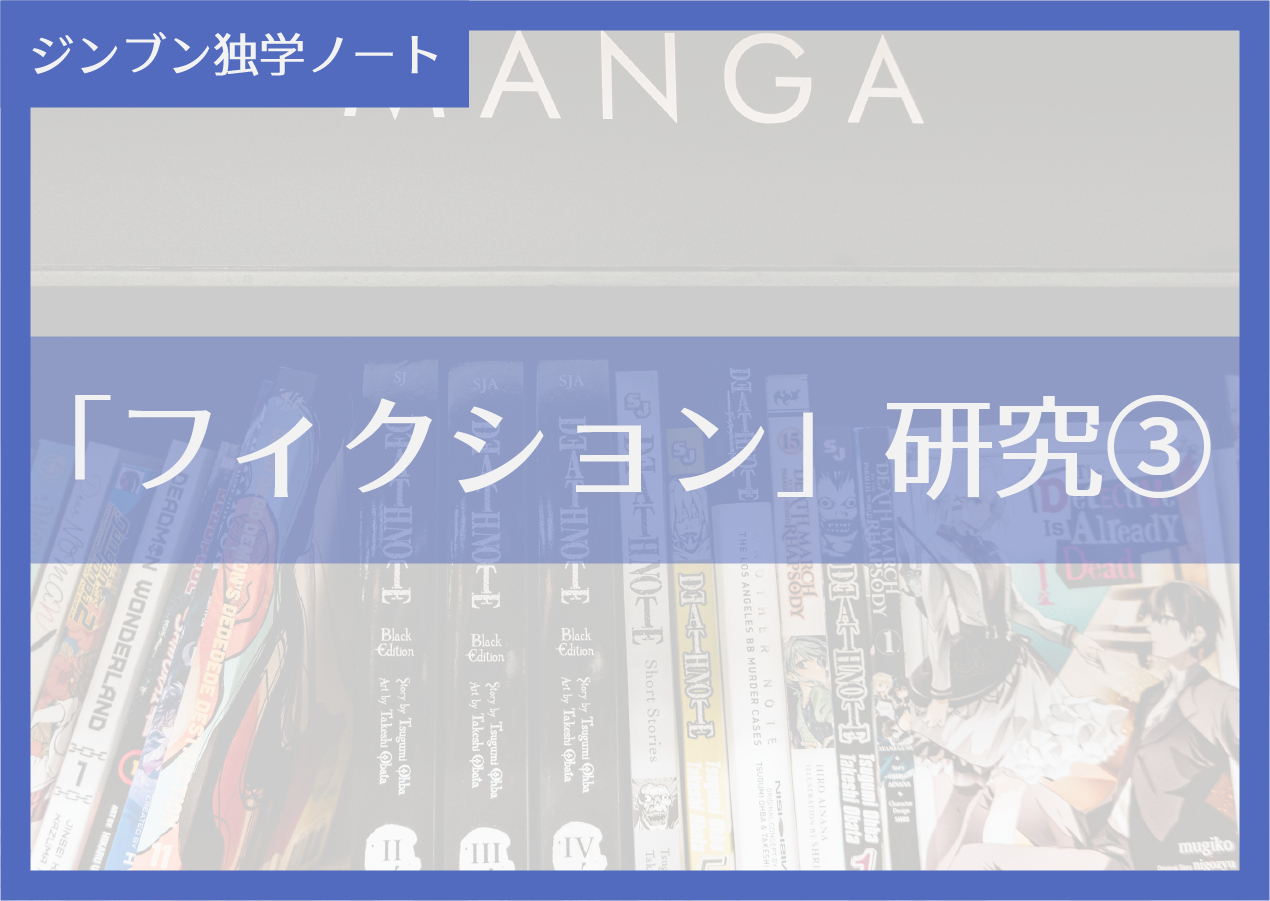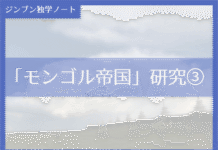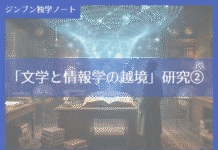ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三回となる今回のインタビューでは、岡田進之介さんにお話をうかがいます。岡田さんは、小説や映画といった「物語」を鑑賞する際の心の働きを、分析美学という哲学的な手法で研究されています。なぜ私たちは一部のフィクションの描写にだけ強く抵抗を感じるのか、という謎に「視点的想像」という新たなモデルを提示し、その仕組みの解明に挑みます。
研究の結果
Q3-1. 興味を持ったきっかけと方法について詳しく教えていただきました。最後に、どんな研究をされたのか伺ってもよろしいでしょうか。
自分が取り組んだのは、フィクションにまつわる論理的なパズルの一つを解決することです。その問題というのは、フィクション研究において「想像的抵抗の問題(The Puzzle of Imaginative Resistance)」と呼ばれてきたものです。
これはケンダル・ウォルトンという人が提起した問題です。小説などのフィクションにおいては現実では正しくない文が色々出てくると思いますが、その中の一部だけが読み手にとって受け入れられないことがある、それはなぜかというものです。例えば、「ロバが人語をしゃべる」という、現実では正しくない荒唐無稽な文章を想像することは難しくないのに、「自分の赤ん坊を殺したのだから、彼はいいことをした」と書いてあると、我々は「うわっ」となってしまって、受け入れて想像することが難しくなります。
そういう「うわっ」となる現象の本質を見つけたい、そういうことが起こってしまう原因は何なのか、というのが議論の方向になります。
ーー 道徳的に受け入れにくい、といった類のものですか。
そのような論点も含めて、ですね。
私はこれを、フィクションを鑑賞する際に持つ態度である「想像」概念をより深く分析することで、解決することができるのではないかと考えました。というのも、これまでフィクションの議論では、読み手が行う「想像」という心的態度は、「命題的想像」であるということが前提とされてきました。
これは心の哲学などの文脈で、信念や欲求のような命題的態度の一つとして想像を考えるということです。分かりやすく言い換えると、文に書かれていることが現実で真であるかどうかに関係なく、「フィクションにおいて成り立っていること」として心に思い浮かべること、と言えます。
私はそうではなく、フィクション鑑賞には「視点的想像」、つまり作品で提示される認知的・価値的・感情的な視点から想像することが必要だ、と考えました。
ーー 視点に入り込んで想像する?
読み手の視点的想像は、作品において提示された視点に入り込むことで行われます。ここでいう視点というのは、特に物語を支配する一番大きな価値観とか感情なんかのことで、読者はそれを受け入れることでフィクションを鑑賞します。身近な例でいえば、アンパンマンで「正義が悪に勝つ」とか、「食べ物は大事にしよう」とか、そういう側面を視点と呼べると思います。
このような読み方をしたときに、作品が提示する視点を理解できなかったり、指定されたような想像をしたくない、という反応が出てきたりすることが「想像的抵抗」だと分析しました。
―― それは納得のいく説明ですね。言い方が正確か分かりませんが、作品に没入しきれないと言いますか。
この辺の話はかなり前提知識が必要で、「フレーム」という概念を引用したのですが、そういった道具立てを集めるのに苦労しましたね。