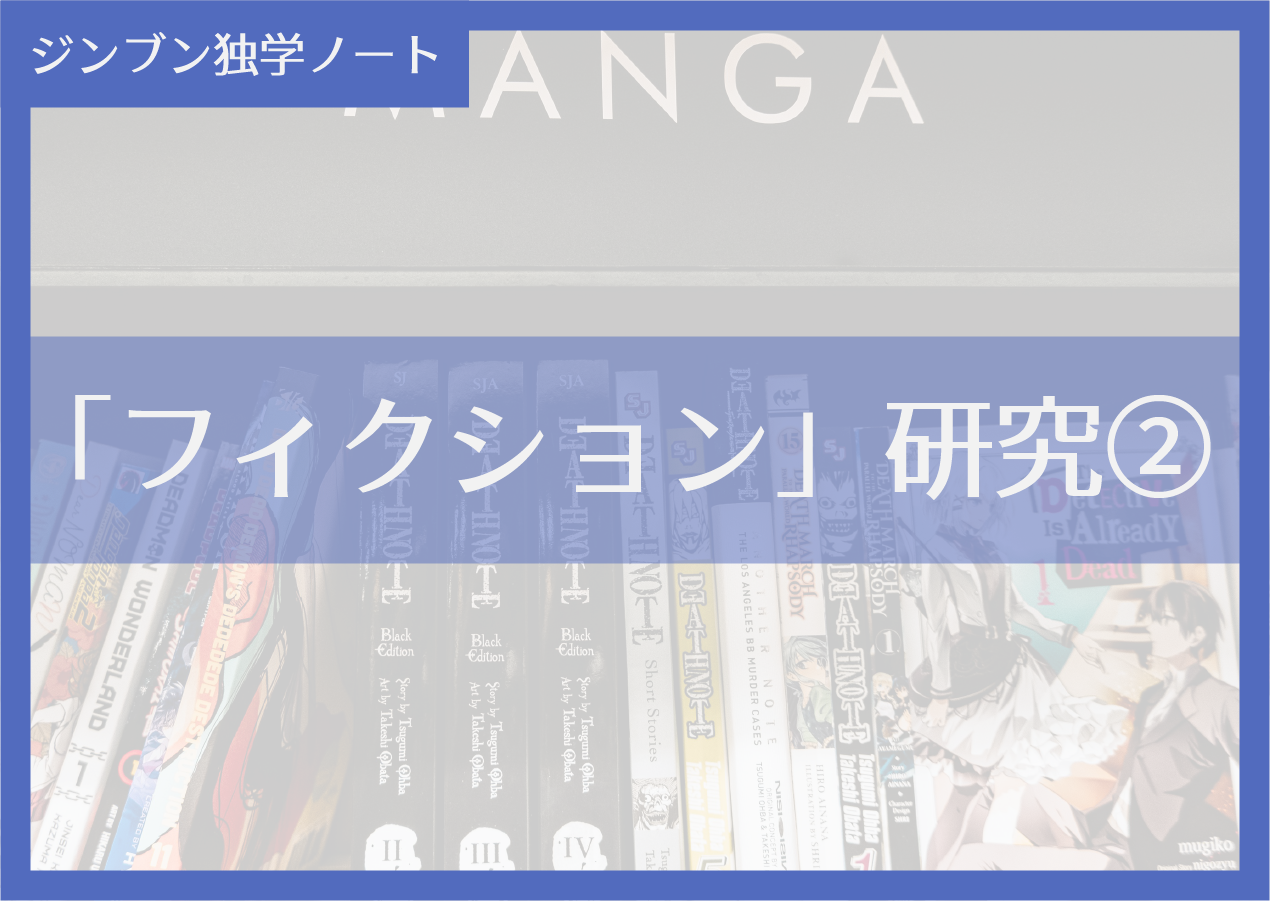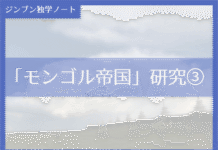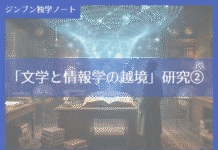ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三回となる今回のインタビューでは、岡田進之介さんにお話をうかがいます。岡田さんは、小説や映画といった「物語」を鑑賞する際の心の働きを、分析美学という哲学的な手法で研究されています。なぜ私たちは一部のフィクションの描写にだけ強く抵抗を感じるのか、という謎に「視点的想像」という新たなモデルを提示し、その仕組みの解明に挑みます。
研究の手順
Q2-1. 興味関心についてはよく分りました。では実際どんな形で研究を進めたのか教えてください。
まず、先行研究を読み込むところからですね。美学にもいろいろなジャーナルがありますが、自分が参照したのは主に英語圏の分析美学のジャーナルで、アメリカ美学会のJournal of Aesthetics and Art Criticismやイギリス美学会のBritish Journal of Aestheticsなどです。
こうした先行研究を網羅的に読み込み、どのような問題が提起されてどのように議論されているかを整理します。オリジナルな知見を提示できると思ったら、学会発表を経て論文化します。
ーー やはり本場・英語圏のジャーナルが主流なんですね。日本ではあまり分析美学はメジャーではないんでしょうか?
日本ではまだ若手研究者を中心に研究され始めたところですが、ここ数年で翻訳が進んできています。たとえばロバート・ステッカー著『分析美学入門』は翻訳ブームの代表的な作品ですね。研究者の森功次さんが、ご自身のブログで日本語文献の入門ブックリストを公開していらっしゃいます。
自分の研究については今のところ日本語文献がなく、英語でジャーナルの論文を読むしかありませんでした。ただ最近、分析美学の重鎮ノエル・キャロル『ホラーの哲学』の翻訳が出まして、こちらには一部物語に関する議論があります。
Q2-2. 分析美学、日本ではまさに最前線の分野ですね。物語論というからには、作品の分析なども行ったりするのでしょうか。
基本的に私の分野は哲学的研究に属するので、具体例として作品を引用することはあっても、作品を主題として深く読み込むということはありません。あくまで自分の理論を補強する道具としての位置づけですね。その点はさっきも言った通り、文学的研究とは異なるところだと思います。
―― 分析美学についてはよく分りました。話を聞くと、独学で進めるのはなかなか難しそうですね。
そんなことはないです!分析美学は大学でも学べるところが少ないため、特に大学の外だからといって難しい点はありません。概念さえ学ぶことができれば、自分の頭で誰でも始めることができます。
ただ原著論文を読みたくなったとき、ジャーナルへのアクセスが研究機関に所属していないと難しいかもしれません。オープンアクセスの記事もありますが、全部読もうと思うとやっぱり大学に行かないと読めないですね。
―― 海外のジャーナルへのアクセスはやっぱり課題ですね。何はともあれ、ありがとうございました。
次回へ続きます。