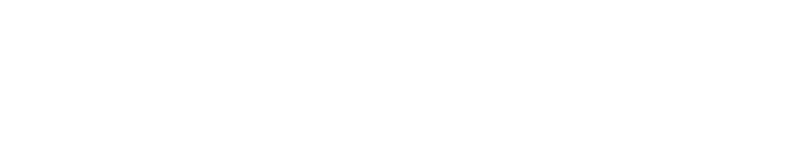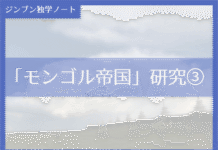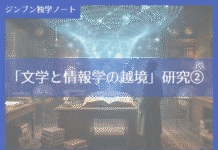ジンブン独学ノートの実践編では、実際の研究について紹介します。研究へのモチベーションから、どのように日々の調査が行われているのかまで、インタビュー形式でお届けします。
第三十七回となる今回のインタビューでは、古典文学と視覚文化の交差領域を探究し、絵巻物から現代のポップカルチャーまで幅広い視点で「受容」の歴史を読み解く、永井久美子先生にお話を伺います。
視覚への関心と文理選択における「探究心」の芽生え
——本日はよろしくお願いします。今回は永井先生ご自身の歩みや研究の原点についてうかがえればと思います。
早速ですが、先生のご専門は、中高生が触れる「5教科」の世界で言うと、どれにあたるのでしょうか。
そうですね、5教科の分類で言えば一番近いのは、国語、なんなら古文かなとは思いつつ。ただ、文章だけでなく、絵も気になる生徒でした。高校生向けの教科書にも、大体挿絵が入っていたり、参考資料で絵巻がカラーで載っていたりしますよね。
——確かに、ビジュアル資料は豊富ですね。
私の学生時代以上に、今はビジュアルが充実した教科書や参考書が多いですが、教材の世界を視覚的にイメージさせてくれる絵に、自分は惹かれるものがありました。あとは、作者の紹介で顔写真が載っていると、その写真が印象に残るとか。落書きはしない子でしたけれどもね(笑)。教科書に載っていた画像は、気になって覚えていました。この絵がどうして選ばれたのかなとか、たくさん写真があるとしたらどうしてこの写真なのかな、とか。そういう素朴な疑問を持つ子供だったかもしれません。
——ビジュアルへの関心ですか。最近、インターネット上で「国語便覧」が話題になったことがありまして。
あ、そうなんですか。
——ええ。寝殿造などの建築や、昔の装束や武具などがものすごく詳細に図解されていて、推し活や同人活動をしている人たちが「とても参考になる」と。ビジュアルに惹かれるという感覚は、思い当たる読者も多いかもしれません。
本当ですね。最近はゲームなどを入り口に、自分で創作したい方や、「推しキャラ」の分析をしたいという方にとって、身近で解説が載っている教材として国語便覧が便利なのは分かります。
自分に関してはただ、教科としての国語が得意だったかと言うと、なんでこれが正解なのかよくわからないな、と感じることもあって。そんなに得意でもなかったんです。
——得意だったから専門にした、というわけではないのですね。
はい。わざと苦しい道に行こう、という思いは特段なかったのですが……。古文は勉強し始めたら楽しくて、ちょっと得意になってきた、くらいです。
むしろ、現代文などで選択肢が並んでいて「これだ」と言われても、そうかもしれないけれども、どうしてその解釈に至るのかな、とか。疑問を残しつつ解くような、ちょっとひねたところはあったかもしれません。
——その「問い」を持つ姿勢が、研究に繋がっていったともいえそうです
今ならそうかもしれないと思います。設問にある「作者の考え」と言われても、作者がどう思っていたか、本当に読み取れるものか、とか。明らかに違うという証明はどうやってできるんだろう、とか。考えすぎてしまう子でした。
ただ、言葉への興味関心は、ずっと持ち続けていました。その対象が、自分の場合は特に平安時代の言葉だったなとは思うんですが、好きなのが古典だったので。歴史も好きでしたし、ビジュアルに惹かれるという意味では美術も好きでした。
——なるほど。中高生の頃から、すでに複数の分野へのご関心があったのですね。そこから大学の学部学科はどのように選ばれたのでしょうか。
私が通っていた高校では、3年生になるときに文理のクラス分けがあったんですね。2年の冬に希望を出さないといけないんですが、ギリギリまで迷ったんです。
——意外ですね。文学や歴史へのご関心が強かったのかと。
理系科目の方が、一応回答が明快な気がしましたし、問いと答えの関係性がクリアな世界だな、と思ったんです。
でも、自分がより追究したいと思えたのは、「分からないけど分かりたい」という気持ちがまさった、文系分野だったんだと思います。
——「分からないけど分かりたい」、ですか。
「分からないから分かりたい」というか。言語はコミュニケーションで毎日使っているし、本当に些細な会話で傷ついてみたり、感動してみたり、色々あります。多感な時期でしたし、言葉の重要性というものは実感としてあったので、分かりたいと思ったのかもしれません。
理系分野に格好良さを感じる気持ちや、物の理(ことわり)知りたいという思いは、常にありました。ただ、それ以上に、人間である自分のことを、自分はまだまだ分かってないな、と。人について知りたい、探究したいという気持ちが強かったのだと思います。
次回は研究者としての苦悩について伺います。